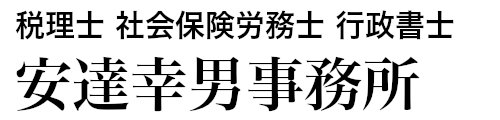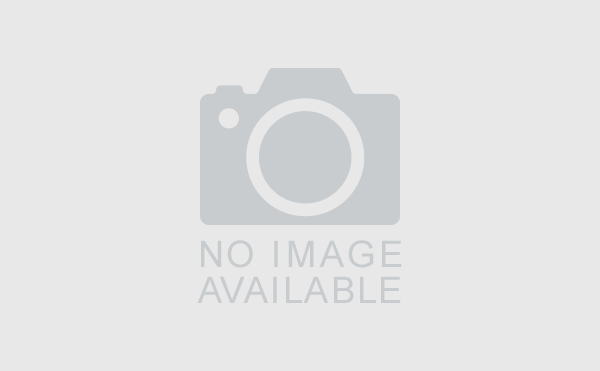基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言2)
遺言書がないとどうなるか?
遺言書がない場合には、相続人全員で一堂に集まって、被相続人の遺産をどのように分けるかについて話合いを行います。相続人間でうまく話がまとまっていけば、「遺産分割協議書」(全員が署名押印した上で、全員の印鑑証明書を添付します。)を作成して、これをもとに不動産の相続登記や預金の払戻などの相続手続を行うことができます。
もし話合いがまとまらなければ、家庭裁判所に対して遺産分割の調停の申立てを行い、裁判官や調停委員を交えて、分割内容について協議します。そこで相続人間で合意ができて話がまとまればよいのですが、まとまらなければ最後は裁判所の審判という形で裁判官が遺産の分け方を決定することになります。通常、家庭裁判所に申し立てると、民法で定められた法定相続分に近い形での決着となることが多いでしょう。このような形で決着すると、家族であっても、その後は絶縁状態になることが多いと思いますし、それまでの間に費やした時間(1年から2年近く)や弁護士費用(数十万円)などを考えると、家族にとっては決して望ましいものではありません。
遺言書がないと、このような争族争いとなることも多いのではないでしょうか。家庭裁判所の統計(遺産分割の調停・審判事件)によると、遺産総額1,000万円以下のケースが全体の約3分の1、5,000万円以下のケースでは約4分の3となっていますので、「うちは財産が少ないから大丈夫だ。」ということには決してならないことに留意する必要があります。
もし仮に亡くなった方の遺言書が残されていれば、付言事項で遺産分けの理由と感謝の気持ちがかかれていれば、財産を少ししかもらえない相続人も、たとえ心の中では不平等だと思っていても、まあ父(母)の言うことだから仕方がないなあという気持ちになるかもしれません。もちろん納得しない相続人もいるかもしれませんが、遺留分以上の請求はできませんので、それ以上紛争は生じません。
遺言書は、亡くなった方の生前の意思を尊重することができる一つの手段ですので、できれば準備しておきたいものです。