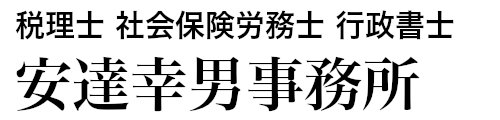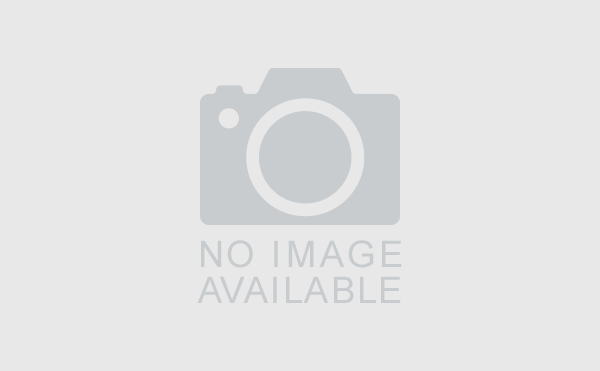基礎から学ぶ遺言相続講座(相続2)
相続法の改正は、どのようになっていますか?
相続税の改正の経緯(歴史)を知る意味は、どこにあるのでしょうか?
法律の世界の下では、紛争を解決する際には、通常、法を適用する時点での法規を適用することになっています。したがって、通常のケースでは、現行法を適用すれば足りることになります。ところが、過去の事実に関する紛争を解決する際には、その過去の時点で適用されていた法律を適用することになっています(意外と盲点になっています。)。
したがって、非常にまれなケースかもしれないが、自宅の土地建物について、曾祖父の代からずっと相続登記がしていないようなケースでは、それぞれの被相続人の死亡時の相続法が適用されて相続人及び相続分が決定されることになります。その意味で、相続事案を考える際には、過去の相続法の改正の歴史も知っていないといけないことがあるということです。
明治民法は、家の主としての戸主の地位を承継する家督相続であり、家督相続人となる後継ぎは、嫡出の男系が優先となっていました。配偶者は、家督相続の相続人にはなれませんでしたし、家督相続以外の遺産相続(戸主以外の相続)についても、直系卑属がいない場合に限って相続権を有することになっていました。
これが、戦後の昭和22年の民法改正により、家制度(家督相続)は廃止されることとなり、相続は遺産相続のみとなり、また、配偶者にも相続権が保障されるようになりました。相続人が配偶者と子のケースでは、配偶者の相続分は3分の1、子の相続分は3分の2とされていました。相続人が配偶者と父母のケースでは、配偶者の相続分は2分の1、父母の相続分は2分の1とされていました。相続人が配偶者と兄弟姉妹のケースでは、配偶者の相続分は3分の2、兄弟姉妹の相続分は3分の1となっていました。また、同順位の複数の相続人の相続分は、憲法の平等原則を受けて、均分となりました。
大きな改正でいえば、昭和55年の改正により、配偶者の相続分が引き上げられました。相続人が配偶者及び子のケースでは、配偶者の相続分は、2分の1に引き上げられました。相続人が配偶者及び父母のケースでは、配偶者の相続分は3分の2に引き上げられました。相続人が配偶者及び兄弟姉妹のケースでは、配偶者の相続分は4分の3に引き上げられました。これは、配偶者の婚姻生活における夫婦財産の清算の意味合いや、生存配偶者の生活の安定を考慮したものによる改正でした。
配偶者の相続分をさらに引き上げるべきとの意見もありますが、現時点では改正されるまでに至っていません。
子の相続分に関しては、最高裁平成25年9月4日判決を受けて、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする旧民法第900条第4項但書の規定を削除する改正を行いましたので、平成25年9月5日以降の相続事案については、嫡出子と非嫡出子とは相続分は平等とすることとされました。なお、上記の最高裁判決では、平成13年7月1日以降は、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の相続分の2分の1とする規定は違憲状態であったとされていますので、平成13年7月1日以降の相続についても、同様の取扱いになります。