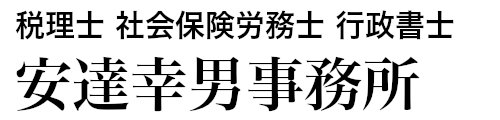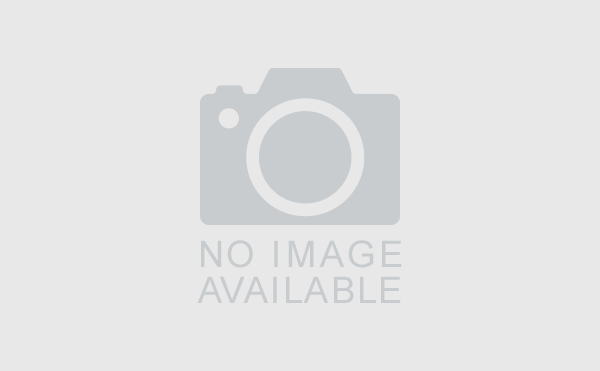基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言11)
遺言を作成するための判断能力とは?
遺言を作成するためには、どのような資格が必要でしょうか?
民法は、15歳に達した者は、遺言をすることができると定めています(民法第961条)。また、遺言には、行為能力の規定(後見、保佐、補助)の適用はないとされています(民法第962条)。
ただし、15歳以上であれば誰でも遺言を有効にすることができるというわけではなく、遺言は、財産上の効果を生ずるものですので、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうる意思能力(遺言能力)が必要とも考えられます(民法第963条参照)。
成年被後見人については、事理弁識能力を一時回復した(本心に復した)時において遺言を作成するのは、遺言能力があることが前提となりますので、医者2人の立会いの下で、立ち会った医者2人が、遺言者が遺言時に心神喪失の状況になかった旨を遺言書に付記して、署名・押印することが必要になっています(民法第973条)。
実際には、高齢者で認知症の疑いがある者の作成した遺言書の有効性は問題になることが多いので、医者の診断書を添付したり、公正証書遺言で作成(公証人が判断能力の有無を確認する)したりすることにより、作成当時には遺言能力があったことを証明することになることが多いものと思われます。