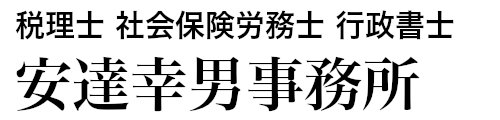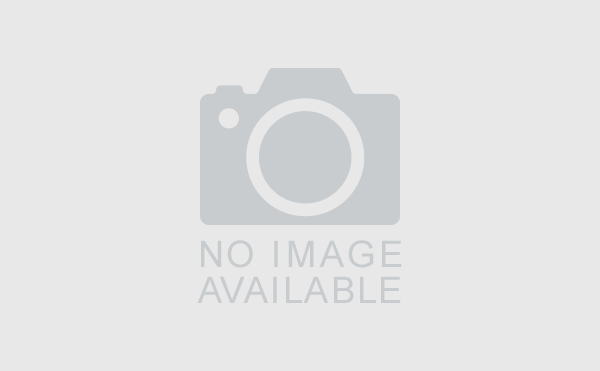基礎から学ぶ遺言相続講座(相続12)
特別寄与料とは?
特別寄与料とは、2018年(令和元年)7月1日施行の民法相続法の改正によりできた制度になります。
被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続開始後、相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた金額(特別寄与料)の支払を請求することができることとなっています(民法第1050条第1項)。この場合、請求の相手となる相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に法定相続分又は指定相続分を乗じた額を負担することになります。
特別寄与料の支払について、当事者間に協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法第1050条第2項)。
注意しなければならないのは、特別寄与料の請求を家庭裁判所に対して申し立てる期限が、特別寄与者が、相続の開始と法定相続人の両方を知ったときから6ケ月以内に申立てをする必要があり、期限が非常に短いということです。
特別寄与分制度ができた理由は、例えば、相続人である長男の妻が、被相続人の療養看護に努めていた場合、従来の寄与分の制度では相続人でない長男の妻は寄与分の主張をすることができないこと、家事審判の実務では夫(長男)の寄与分の中で長男の妻の寄与を考慮することがありますが夫(長男)が先に死亡したときは全く考慮されないことになるなどの不都合(不公平感)を解消するためにできたものです。
特別寄与料については、相続税法上の課税の取扱いが問題になります。
特別寄与料に関する相続税法の取扱いについては、特別寄与者が、特別寄与料を受け取った場合(支払うことが確定した場合)には、特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から「遺贈」により取得したものとみなされて、相続税が課税されることになります(相続税法第4条第2項)。
一方、相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人に係る相続税の課税価額から控除(債務控除)することになります(相続税法第13条第4項)。
なお、特別寄与者は、一親等の血族及び配偶者以外の者に当たりますので、相続税額の計算に当たっては、相続税の二割加算の対象となります(相続税法第18条第1項)。
もし仮に、特別寄与者である長男の妻が、被相続人から生前贈与を受けていた場合には、特別寄与者である妻は「遺贈によって財産を取得した者」に該当しますので、被相続人から生前贈与を受けていたその贈与財産については、相続開始前3年以内(※令和6年1月1日以降は順次7年以内に延長)贈与に該当するときには、生前贈与加算として相続財産に加算されて計算することになっていますので注意してください(相続税法第19条第1項)。
最後に、相続税の期限後に特別寄与料の支払が確定した場合(大半のケースがこれに該当すると想定されます。)には、特別寄与料の請求をした者は、特別寄与料の支払が確定した日から10ヶ月以内に相続税の申告をしなければなりません。これに対して、特別寄与料の支払いをした者は、特別寄与料の確定後4か月以内に限り、更正の請求(減額)をすることができますので、注意してください。