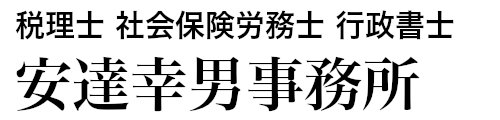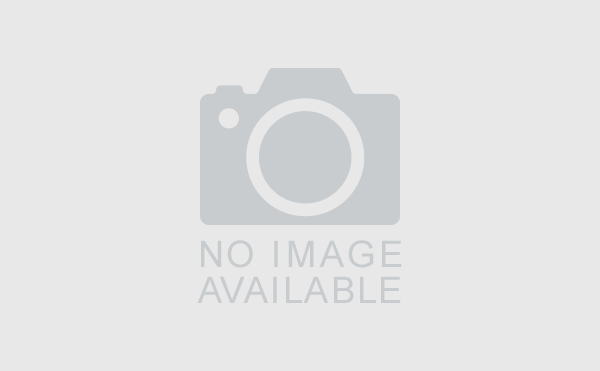基礎から学ぶ遺言相続講座(相続13)
遺産分割で遺産を法定相続分で平等に分けるってどういうことでしょうか?
一口に法定相続分で平等に遺産を分けるといっても、それを実現することは簡単ではありません。
遺産を法定相続分できっちり分けるとなると、民法の規定(特別受益者に関する第903条、寄与分に関する第904条の2)に従いますと、次のような計算をすることになります。
遺産分割時の遺産総額+特別受益(生前贈与+遺贈)ー寄与分=分配の基礎となる計算上の遺産の総額
分配の基礎となる計算上の遺産の総額(「みなし相続財産」)×法定相続分=具体的相続分
具体的相続分ー特別受益(生前贈与+遺贈)+寄与分=特別受益・寄与分のある相続人の具体的相続分
以上の計算式は、相続人間の公平を図るために、生前贈与でもらった分は一旦遺産に持ち戻して計算する、遺言でもらううことになった財産も持ち戻して計算する、被相続人の療養看護や事業に関する労務提供などで寄与した分は別枠としてもらえることになっています。
ただし、計算上は、上記の通りに計算することになりますが、現実には遺産には現金、預金、株式のほかに不動産などもありますので、特に不動産が複数あるときは、それぞれの不動産をいくらと評価するのかその評価の時点や評価方法により評価額も異なることから、数字的に完全に平等に分けることはある意味で非常に難しいかもしれません。また、特定の相続人が生前に贈与を受けていたとしてその特別受益の金額をいくらに評価するのか、あるいは、特定の相続人が被相続人の介護をしたとして寄与分を主張するとしてその寄与分の金額的評価をいくらにするか、相続人間での話合いで意見がまとまればよいですが、意見がまとまらなかったりすることも多いかもしれません。
遺産分けを円滑にまとめるためには、相続人同士が譲歩し合っていかないと、話はなかなかまとまらないかもしれません。