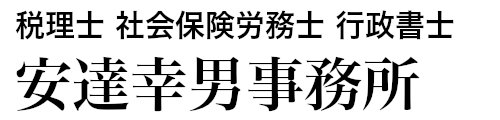(目次)
1 終活・相続に向けた準備
2 相続人の調査
3 相続財産・債務の調査
4 相続人、相続分、寄与分、特別寄与分
5 遺留分
6 遺言
7 遺産分割
8 相続税の申告・納付の要否
9 任意後見契約
10 財産管理委任契約、死後事務委任契約
11 年金手続
-
1-1 終活として相続を意識した場合、どのようなことを考えればよいでしょうか?
-
まず、ご自身が亡くなった後に、残された家族(配偶者、障害のある子供など)が、今後暮らしていける資金が十分にあるのかどうか、毎月の「収支見込み」を検討していく必要があります。
そのためには、まずはご自身がなくなった後に、今後入ってくる毎月の収入(遺族年金、配偶者や子供の給与収入、賃貸不動産の収入、株式の配当金など)の合計金額を計算してみます。また、毎月の必要となる支出(住宅ローンの返済や生活費など)の合計金額を計算します。差し引きして、今後の毎月の生活費が黒字なのか、赤字なのかを確認します。この結果、毎月の収支が黒字化赤字か、赤字なら毎月いくら不足するかを確認します。
次に、ご自身の所有する財産(預貯金、不動産、株式、生命保険、ゴルフ会員権、金地金など)が、何があるのか、どこにあるのか、いくらの価値があるのか、すぐに換金(現金化)可能か、といったことを確認します。このほか、生命保険についても、どこの会社にいくら入っているかを確認します。
他方で、債務といいますが、金融機関の借入金、カードローンなどの借金などが、どこに、いくらあるのか、といったことを確認します。
これらの調べた財産・債務は、ぜひとも「財産・債務一覧表」にしてまとめておくと便利です。「財産・債務一覧表」にまとめておくことによって、万一あなたが亡くなった場合にも、残された家族が、あなたの財産・債務を捜すことに苦労しません。市販のエンディングノートにメモしておくことでもよいでしょう。
これらの収入・支出、財産・債務を総合的に判断して、特に残された配偶者等が、今後の平均余命までの生活費を十分に手当てできているかどうかを検討します。場合によっては、介護施設に入居するようなケースを想定して、そのための費用を支払っていくことができるのかどうかも検討していくとよいでしょう。
-
1-2 終活の一環として、相続があったときのための事前の準備をしたいと思いますが、何から始めたらよいですか?
-
まずは、ご自身の「相続関係図」を作成して、相続人は誰がなるかを確認することです。
あなたが死亡した場合の推定相続人をもれなく探すためには、推定被相続人(死亡すると想定される方)の生まれてからの戸籍謄本をすべて取る必要があります。本籍地を転々としている場合は、順次、本籍地を遡っていき、そのすべての市町村の除籍謄本を取る必要があります。ポイントは、あなたが生まれてから現在までの戸籍がすべてつながっていることです。ここで注意したいのが、前妻との間の子、認知した子なども相続人になることです。
次に、推定被相続人となるあなたの財産及び債務をすべて洗い出していただき、「財産・債務一覧表」を作成することです。メモでの残してもよいし、市販のエンディングノートに書いておいても結構です。
財産は、預貯金、不動産、有価証券、投資信託、自動車、金地金、ゴルフ会員権、生命保険、年金など、すべてを拾い出します。遠方に住む子供たちは、あなたの財産が、どこに、どのようなものがあるか全く知らないことが多く、万一相続が起きた際には困ってしまいます。
債務は、銀行借入金、クレジットカードなどです。
できれば毎月払い又は年払いの公共料金の支払、携帯電話やパソコンサーバーなどの利用料金、各種の会費、保険料などもメモして拾い出しておきましょう。
このほか、パソコンのIDパスワード、携帯電話のパスワード、キャッシュカードやクレジットカードの暗証番号、インターネットバンキング、ネット証券などのデジタル財産も、一覧表にまとめて把握しておきたいところです(相続人が万一の際に照会、解約等の手続をするために必要です。)。
-
1-3 相続に向けた事前の対策のポイントは?
-
相続への事前の対策として、一般的には、①「円滑な遺産分割対策」、②「相続税の納税資金の確保」、③「相続税対策」、の3つがポイントであるといわれています。
①「円滑な遺産分割対策」とは、遺産分割を巡り争いが生じないように事前に手当てをしておくことをいいます。
仮に、相続人間で遺産分割を巡って争いが生じた場合には、預金の引出はできませんし、不動産なども売却することもできません(いわゆる資産凍結の状態です。)。
また、相続税の申告では、申告期限までに遺産分割がまとまらないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった相続税を軽減できる特例の適用を受けることができません。遺産分割が申告期限までに未了の場合は、いったんこれらの特例の適用がないものとして計算した上で、多額の相続税を一括で納付しなければなりません。
遺産分割を巡る争いを防止するためには、遺言書の作成が一番有効になります。なお、相続人が複数人いる場合で、相続財産が、自宅不動産のみとか、あるいは、大きな賃貸不動産のみといったときには、一人の相続人に相続させる旨の遺言書を作成すると、他の相続人からの遺留分侵害額請求といった問題が生じますので、できるだけ他の相続人の遺留分にも配意して遺言書を作成しておくとよいでしょう。
②の「相続税の納税資金の確保」とは、各相続人が納付すべき相続税の資金をどのようにして捻出しておくかを事前に検討しておくことをいいます。
例えば、相続財産が、自宅のみで預貯金が少ないケースや、事業用不動産を特定の相続人に承継させたいケースなどでは、仮にこれらを相続する相続人に納税資金がない場合には、結果的に相続した自宅や事業用不動産を売却して相続税を納付せざるを得ない事態にもなりかねません。
納税資金の確保の対策としては、よくあるのが相続税が非課税となる生命保険契約へ加入することです。最近では、90歳まで加入できる生命保険もありますので、持病があるとか、年齢が高いという方でも、ぜい加入できるか一度検討してみてください。
③の「相続税対策」とは、万一相続があった場合に、できるだけ相続税の納付額を減らすために、事前にその対策をしておくことをいいます。
例えば、孫養子の活用、暦年贈与の活用、子や孫への教育資金贈与制度の活用、住宅資金等贈与制度の活用、子や孫への結婚子育て資金の一括贈与制度の活用、居住用不動産又はその取得資金を非課税で贈与することができる贈与税の配偶者控除、2,500万円まで贈与税が非課税となる相続時精算課税制度の活用、土地の上に賃貸物件を建設することなどがあります。ただし、いずれもメリット・デメリットがありますので、専門家によく相談してください。
以上の3つのポイントのうち、最も重要なポイントは①の「円滑な遺産分割対策」であり、検討すべき順番も、①円滑な遺産分割対策、②相続税の納税資金対策、③相続税対策の順番になります。相続税対策に走りすぎて、遺産分割がもめたり、相続税の納付資金が足りなくなったりしては、本末転倒ともいえます。
-
2-1 相続人はどうやって調査すればよいでしょうか?
-
被相続人(亡くなった方)の出生時から死亡時までの間の連続した戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍謄本)をすべて収集します。
なお、本籍地を転籍した場合(転籍)、結婚・縁組した場合(編成)、離婚・離縁した場合(編成)、戸籍がコンピューター化された場合(改製)など、新たな戸籍が作成されている場合には、遡って従前の戸籍謄本をすべて収集していきます。
一方で、法定相続人については、現在も生存しているかどうかの確認のために、戸籍謄本を収集します(相続人が死亡している場合は、代襲相続人の戸籍謄本も収集します。)。
-
2-2 戸籍を見るときの注意事項は何でしょうか?
-
戸籍の種類は、次のとおりになります。
①現在戸籍(現在使用されている戸籍、筆頭者の本籍地に当たる市町村の戸籍簿に綴られて保管されています。)
②除籍(1つの戸籍に在籍した者が、全員いなくなった戸籍のことをいいます。)
③改正原戸籍(戸籍の様式が法律又は命令により改められた場合の編製替えの前の戸籍をいいます。)
※戸籍は、昭和23年に戸籍の記載事項が、家単位から夫婦単位に変更されました。
平成6年に戸籍が電算化されて横書きになりました。
戸籍は、①出生届により、親の戸籍に入り、②婚姻届の提出によって新戸籍が編製され、③子が出生したときは、親の戸籍に子が入り、④死亡届の提出によって、死亡した者は戸籍から除かれることになります。
これらのことに留意しながら、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍をすべて収集します。
なお、認知事項や養子縁組事項については、見落としやすいので注意します。
-
3-1 所有不動産を把握するには、どうしたらよいですか?
-
お住いの市町村の固定資産税課(資産税課、税務課など)において、亡くなった方の所有する不動産の「名寄帳」を収集することで、お住いの市町村内での所有不動産を把握することができます。
この「名寄帳」は、市町村が法務局からの登記通知(データ)に基づいて作成した土地・家屋課税台帳を人ごとに名寄せしたものであり、毎年1月1日現在の所有者で作成されています。逆にいうと、年の途中で取得した不動産はこの名寄帳には記載されていない、また、名寄帳に記載があっても年の途中で売却していることもある、ということに注意する必要があります。
このほかに注意したい点は、「名寄帳」には、非課税の不動産(私道など)も記載されていますが、記載されていないこともあることです。また、共有名義の不動産も記載されていることもありますので、よく確認する必要があります。
まれに、遠方の亡くなった人の親(父母)の住んでいた市町村に、相続した不動産を所有していることもあります。この場合、不動産の名義は、亡くなった方の亡父親名義あるいは亡祖父名義となっている物件もあります。手がかりとしては、亡くなった方の戸籍謄本などを基に、本籍地や過去の住んでいた場所の市町村において、亡くなった方の亡父名義の名寄帳などを確認する必要があります。ただし、この方法は、何らかの手掛かりによりその市町村に不動産を所有している可能性があると分かっている場合にしか使うことができません。そのため、どうしても所有不動産を把握することができないケースもあります。
この問題については、令和6年4月1日より相続登記の申請の義務化がされることになり、相続登記の漏れを防止する観点から、令和8年4月までに被相続人名義の不動産を把握しやすくなる制度として、「所有不動産記録証明制度」ができることとなっております。この制度では、全国の不動産について所有権の登記名義人で名寄せをして、請求した名義人で登記されている不動産を一覧表にした証明書が法務局から交付される予定になっております。この制度を利用できれば、被相続人名義の不動産が全国レベルで判明しますので、遠隔地の所有不動産(北海道などの原野商法で購入した土地なども)が発見できないということはなくなります。
次に、これらにより把握した不動産については、お近くの法務局(全国どこの不動産についても調査できます。)において、土地又は建物の「登記事項証明書」を収集することにより、不動産の所有名義や抵当権の設定の有無などを確認します。
発見した不動産の所有名義が亡くなった方の亡父名義などとなっている場合には、今回の相続登記を行う前に、先の相続登記を行う必要があります。
また、まれに名寄帳に基づいて法務局で登記事項証明書を請求しても、該当なしとなるケースであっても、建物が未登記となっていることもよくあります(特に田舎の家屋では多い。)。この場合には、市町村で該当する未登記建物の固定資産課税証明書を取得して、誰の名義で課税(亡くなった方の亡父名義で課税されていることがよくあります。)されているのかを確認する必要があります。
これらのケースでは、司法書士や土地家屋調査士に相談して、未登記建物について保存登記をするか、亡き祖父名義の土地建物について相続登記をしてから今回の相続登記をするかなど、事後の対応をどうするかよく検討する必要があります。未登記建物の保存登記には、多額の費用(数十万円)もかかりますし、前回の相続登記をするには前回の相続における相続人の承諾が得られるかなど、いろいろと問題もあります。
-
3-2 預貯金や株式は、どのようにして把握できますか?
-
自宅内(金庫や貴重品の保管場所など)を探して、預貯金の通帳、キャッシュカード、証券会社の報告書の封書、配当金の振込(預金通帳に記帳)などから、取引のあった金融機関や証券会社などを把握します。
預貯金については、取引をしていた金融機関が不明な場合は、近くの金融機関に対して、預金取引の有無を照会する方法もあります。
また、株式については、取引をしていた証券会社名が不明な場合や、そもそも株式の取引があるのかどうかも不明な場合は、株式会社証券保管振替機構に対して「登録済加入者情報開示請求」を行うことにより、被相続人が口座を開設していた証券会社、信託銀行等の名称の情報が確認できます。これをもとに、取引有りと把握した証券会社に対して、取引の内容を照会することができます。
最近は、インターネットバンクやネット証券での取引も多数ありますが、これらのインターネット上での銀行や証券会社との取引(デジタル遺産)については、相続人にはその取引の存在自体が分からないことも多いようです。これを防ぐには、エンディングノートなどに、デジタル遺産の有無についてメモをしておくとともに、アカウントやIDパスワードも併せてメモしておく対策をとることが必要です。スマホやパソコンのログインハスワードも分かるようにメモしておくとよいでしょう。
-
3-3 生命保険契約があるかどうかはどうすれば分かりますか?
-
郵便物や銀行口座の引落履歴などにより、生命保険会社が特定できていれば、保険会社に直接照会することにより、被相続人が契約者・被保険者又は保険金受取人となっている保険契約について回答をしてもらうことができます。一般の生命保険会社については、保険契約者が死亡したことが記載されている戸籍謄本などを添付して、保険会社所定の情報開示請求書を提出することで照会することになります。
なお、令和3年7月1日からスタートした生命保険照会制度(全42社(かんぽ生命含む))を利用すれば、相続人の方が、一般社団法人生命保険協会に対して、被相続人が契約していた生命保険契約について生命保険契約の有無を照会することができます。協会からの回答書には、被相続人が保険契約者又は被保険者となっている保険契約について、保険会社ごとに、有(〇)、無(×)のみと回答されますので、有(〇)の会社に対してさらに契約内容の照会をすることで、契約していた生命保険契約の内容を把握することができます。ただし、照会には費用(3,000円)がかかります。
-
3-4 借入金などの債務はどのように調査すればよいでしょうか?
-
自宅や所有不動産の「登記事項証明書」を確認して、金融機関などの抵当権等の設定登記がされていないかどうか確認します。抵当権等の設定登記がされている場合は、抵当権者に対して取引内容の照会をすることで、借入金の内容を確認することができます。
なお、被相続人の債務が不明な場合は、①株式会社シー・アイ・シー(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)、②株式会社日本信用情報機構(JICC)、③全国銀行信用情報センターなどの信用情報機関に対して、開示請求を行うことにより、銀行や貸金業者からの借入金の内容が確認できます。
-
3-5 配偶者居住権とはどのようなものですか?
-
配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、被相続人が所有していた居住建物(自宅)を相続しなくても、終身又は一定期間の間引き続きその居住建物に住むことができる権利をいいます。
配偶者居住権は、①遺産分割、②遺言・死因贈与、③家庭裁判所の審判のいずれかの方法によって取得することになります。
遺言によって配偶者居住権を取得させる場合には、通常の遺言書では「妻(夫)に〇〇を相続させる」とする文言を用いますが、配偶者居住権については、この「相続させる」という文言は用いないように注意しなければなりません。
この理由は、配偶者居住権について「相続させる」旨の特定承継財産遺言をした場合、いこれは遺産分割方法の指定となり、何らの手続を要することなく、被相続人の死亡時に直ちに相続により承継されることになるため、仮に配偶者居住権を拒否したいときには、相続放棄の手続によるほかなくなるからです。したがって、遺言書では、「妻(夫)に配偶者居住権を遺贈する。」と記載した方がよいことになります。
なお、配偶者居住権は、登記をしなければ第三者に対抗できません。
この配偶者居住権は、①存続期間の満了、②配偶者が死亡した場合、③配偶者が善管注意義務を怠った建物の使用・収益を行い是正しなかった場合、④所有者の承諾なく増改築や第三者への使用・収益をさせた場合、⑤配偶者と建物所有者が合意をした場合、⑥配偶者が放棄をした場合などに消滅することになります。
よく節税対策として配偶者居住権の設定を勧める専門家の方もいます。
配偶者居住権を設定した場合には、配偶者は配偶者居住権と敷地利用権を相続することとなり、これらの権利はその後に配偶者が死亡することにより消滅することになりますが、これは、法律に基づく消滅であって、相続人は相続又は遺贈により取得することにはならないとされています。したがって、消滅時における配偶者居住権と敷地利用権に相当する部分の評価額については、相続税が課税されないこととなるため、相続税の節税となるというものです。
確かにそのとおりですが、将来的に困る事態になることもあります。
配偶者居住権を設定したものの、その後において介護施設に入居することになった場合には、配偶者居住権の存続期間の満了前に、配偶者が配偶者居住権を放棄することにより、あるいは、配偶者と所有者との間の合意により解除することにより、配偶者居住権が消滅することになります。
この場合において、居住建物所有者(子)は、期間満了前に予定よりも早く居住建物の使用収益ができることとなりますが、配偶者居住権の消滅の対価を支払わなかった場合には、これにより居住建物の所有者(子)は何ら対価を支払わないで経済的な利益を受けたことになります。この経済的利益については、配偶者から居住建物所有者(子)に対して贈与があったものとみなして、居住建物所有者(子)に対して贈与税がかかることもあります(相続税法第9条)。
また、相当の対価を支払った場合には、この対価は配偶者の総合譲渡所得となりますので、所得税がかかることになります。
このようなことを考えますと、老後生活の先々のことは非常に不確定といえますので、将来の介護施設への入居の可能性も検討して配偶者居住権を設定しないと、相続税は節税できたけれども、後々になって思わぬ多額の税負担が生じるといったこともありますので注意してください。
-
3-6 「財産・債務一覧表」を作成した後は、どうすればよいですか?
-
亡くなった方が、事業や不動産賃貸業などを行っていた場合には、税務署に対して、死亡したことを知った日(通常は死亡日)から4か月以内に「所得税(消費税)の準確定申告書」を提出する必要があります。また、死亡したことを理由とする「廃業届」、「青色申告取りやめ届出」や「消費税課税事業者で亡くなった旨の届出」なども提出する必要があります。
所得税や消費税の「準確定申告書」の提出に当たっては、1月1日から死亡した日までの事業に係る収支計算を行う必要がありますので、時間的にはかなり厳しいと思って準備していただいた方がよいかと思います。
また、相続税の計算をしてみて納税額が出た方は、死亡したことを知った日(通常は死亡日)から10か月以内に「相続税の申告書」を提出することになります。注意していただかないといけないのは、配偶者税額軽減や小規模宅地等の特例の適用によって、相続税の税額が0になった場合であっても、「相続税の申告書」の提出だけは必要になることです。
-
4-1 相続が発生した場合、誰が相続人になりますか?
-
民法の規定(第887条から第890条)によると、相続人は、次の者がなります。
・配偶者(常に相続人になります。) ※内縁の配偶者は、法律上の配偶者ではなく、相続人になりません。
・配偶者と同順位で相続人になる者
(第一順位) 子(実子、養子を含みます。)
※子が既に死亡している場合は、孫が代襲相続人となります(再代襲相続もあります。)。
(第二順位) 直系尊属(父母、祖父母など) ※親等が近い者が優先します。
(第三順位) 兄弟姉妹(父母の一方を同じくする半血兄弟も含みます。)
※兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(甥、姪)が代襲相続人になります。
※伯父、伯母やいとこは、血のつながりはありますが、相続人にはなりません。
-
4-2 (遺言がない場合)法定相続分はどのようになりますか?
-
民法の規定(遺言がある場合は第902条、遺言がない場合は第900条によることになります。)によると、遺言がない場合には、法定相続分に従って相続することになります。
法定相続分は、
① 配偶者及び子が相続人である場合は、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1
② 配偶者及び直系尊属が相続人である場合は、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1
③ 配偶者及び兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1
となります。
なお、同順位の相続人が複数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなります。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。
(注)相続が発生した時期によって、適用される法律が異なりますので、法定相続分の割合が現在とは異なることがありますので注意してください。
(相続開始が昭和22年5月3日から昭和55年12月31日まで)
① 配偶者及び子の場合 配偶者が3分の1、子が3分の2
② 配偶者及び直系尊属の場合 配偶者が2分の1、直系尊属が2分の1
③ 配偶者及び兄弟姉妹の場合 配偶者が3分の2、兄弟姉妹が3分の1
(兄弟姉妹の代襲相続)
昭和56年1月1日以降に発生した相続から、兄弟姉妹の再代襲相続が認められなくなりました。
(非嫡出子の相続分)
平成25年9月5日以降に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子の相続分は平等になりました。
それ以前は、非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1となっていました。
-
4-3 おひとり様の場合、相続はどうなりますか?
-
おひとり様とは、未婚である方、あるいは婚姻していたが配偶者と離婚又は離別し子供がいない方、さらに、親が既に死亡しており兄弟がいない又は兄弟はいたが既に死亡し甥姪もいないという方をいいます。
身寄りがなく、相続人が全くいない人(おひとり様)が亡くなった場合、その人が所有していた財産は、どうなるでしょうか?
まずは、相続人が全くいないといっても本当に誰も相続人がいないのかどうか確認する手続を行う必要があります。
相続人が明らかでない場合は、とりあえずは相続人不存在として扱われ、亡くなった方の遺産は、自動的に相続財産法人という法人に引き継がれることになります。その後、この相続財産法人には、利害関係人の請求によって家庭裁判所により財産を管理する相続財産清算人が選任されて、この相続財産清算人が、相続人及び相続財産の有無の調査を行うとともに、全ての相続債権者及び受遺者に対して、2か月以上の期間を定めてその請求の申出をすべきことを公告します。
もしもそのまま相続人が見つからなければ、相続財産清算人は、債権者や受遺者に対して債務の弁済して清算を行います。
その後は、被相続人の療養看護に努めた者などの特別縁故者からの相続財産の分与請求があれば、これらの者に対して分与を行い、最終的に残った財産があれば、国庫(国)に帰属することになります。
このような形で最終的に自分の財産が国庫に帰属することを避けたいという場合には、ぜひとも遺言書を作成しておいて、財産を譲りたいと思う個人や法人に対して遺贈することで解決できます。
-
4-4 夫婦二人で子供がいない場合は、どのような点に注意したらよいでしょうか?
-
夫婦二人で子供がいないケースでは、夫婦の内の一方(夫)が死亡した場合には、相続人となるのは、配偶者である妻のほか、夫の父母・祖父母が相続人になります。仮に父母祖父母の全員が既に死亡しているときは、亡くなった方(夫)の兄弟姉妹が、妻と同順位で相続人になります。
妻と兄弟姉妹が相続人である場合、妻の相続分は4分の3で、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。兄弟姉妹が複数人いるときは、均等に分けます(民法第900条3号、4号)。
そうすると、例えば、夫の相続財産が自宅と預貯金しかないような場合には、兄弟姉妹が自宅と預貯金の4分の1を相続することになってしまい、残された妻の生活の場所や老後の資金を十分に確保することができませんし、場合によっては、自宅を売却して分配しなければなくなるかもしれません。
したがって、夫が、残された妻に対して、生活の場所としての自宅と老後の資金としての預貯金のすべてを確実に引き継ぐためには、遺言書を作成しておくことが必要となります。
これは、法定相続分で分けることになるのは、遺言書が存在しない場合に限られるからです(民法第902条)。また、民法の規定では、残された家族の生活が害されることがないように、一部の相続人(配偶者、子、直系尊属)には最低限の遺産を相続分を確保する権利が保障されていますが、兄弟姉妹にはこの遺留分がないからです(民法第1042条)。
つまり、夫は、遺言書を作成しておけば、夫の兄弟姉妹に財産の一部が渡ることがないのです。
-
4-5 夫婦二人で子供は2人とも東京に居住しており、財産は自宅と預貯金しかない場合、注意すべき点は何でしょうか?
-
仮に夫が死亡したとした場合に、まずもって考えるべきことは、残された配偶者(妻)の生活の場所と老後の資金の確保ということになります。
もし夫が遺言書を作成していなければ、妻と子2人の間で遺産分割協議を行うことになりますが、遺産分割がまとまらなければ、最終的には、民法の規定である法定相続分(妻は2分の1、子は各4分の1)により各相続人が相続することになりますので、場合によっては、自宅を売却して、自宅の売却代金と預貯金を法定相続分でそれぞれ分けるといったことにもなりかねません。そうなると、残された妻は、生活の場所も老後の資金も確保できないといった事態にもなります。
こういった事態になることを避けて、残された妻に自宅と老後の資金を確保しておくには、遺言書を作成しておくことが有効になります。
また、妻と子供のために自宅をどうするか(例えば自宅を処分して妻の介護施設の入居費用に充てるなど)について、自分の思いを決めておくために遺言書を作成しておくということもあります。
ただし、子には遺留分(このケースでは子一人当たり8分の1)がありますので、遺言書でもこの遺留分を排除することはできませんので、子が遺留分を放棄する意思表示をしない限り、遺言書の思いが100%叶うかどうかは分かりません。したがって、遺言書で全ての財産を妻に相続させるとしたとしても、子から遺留分侵害額請求があった場合に備えて、妻に遺留分の支払資金を手当てできるように、例えば、被保険者を夫とし死亡生命保険金の受取人を妻とする方法があります(死亡保険金は受取人の固有の財産となり、相続財産ではならないからです。)。
-
4-6 事実婚(内縁関係)の夫婦の場合、どのような点に気をつけたらよいでしょうか?
-
我が国の民法では、法律上正式な結婚をしていない夫婦は、夫婦として法律上の保護を受けることができません。この場合の正式な結婚(法律上の婚姻)とは、お互い結婚するという意思があり、かつ、婚姻届を市町村役場に提出して受理されることが必要です(民法第739条、第742条)。
したがって、お互いが愛し合って共同生活を営んでいたとしても、婚姻届を提出していない夫婦は、内縁関係あるいは事実婚といい、原則として法律上の保護を受けることができません。そうすると、事実婚(内縁関係)の夫婦の間では、どちらかが死亡したとしても、他方は相続をすることができません(民法第890条参照)。
このため、仮に内縁の夫が死亡した場合、内縁の夫に兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹が相続人となりますので、内縁の妻は財産を一切相続することはできません(民法第889条、890条)。
そこで、このような場合には、内縁の夫は、内縁の妻に全財産を譲るという遺言書を作成することにより、これを防ぐことができます。しかも、兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、後日兄弟姉妹から遺留分侵害額請求をされることもありません(民法第1042条)。ぜひとも遺言書を作成しておきたいケースの一つとなります。
-
4-7 離婚、再婚により、家族関係が複雑な場合、どのような点に気をつけたらよいでしょうか?
-
例えば、夫が、離婚、再婚をしており、前妻との間に子供がおり、後妻との間にも子供がいるようなケースでは、仮に夫が死亡したとすると、この場合の相続人は、後妻、前妻との間の子供、後妻との間の子供となります。
このようなケースで仮に遺言書がない場合には、法定相続分は、後妻が2分の1、前妻との間の子供と後妻との間の子供がそれぞれ4分の1となります。仮に、その後において後妻が死亡すると、後妻との間の子が後妻の財産をすべて相続しますので、結果として、後妻との間の子は、亡き父の財産の4分の3を相続することになります。
前妻との間の子供との間に交流がなく、前妻の子供と後妻の子供との間で、相続争いをすることを避けたいという場合には、生前に誰にどの財産を渡すかを遺言書にまとめておくとよいでしょう。先ほど見たように、最終的な夫の遺産の取り分を考慮して、場合によっては前妻との間の子供に厚めに財産を譲りたいということもあるかもしれません。いずれにしても、後日の相続争いを避けるためにも、遺言書はぜひとも作成しておきたいケースです。
-
4-8 事業を経営している人が、家業を子供の内の一人に継がせたい場合、どのような点に注意すればよいでしょうか?
-
事業を経営している人の相続財産が、事業用資産(店舗及びその敷地など)や経営する会社の株式が大半を占めているようなケースでは、遺産を相続人間で法定相続分により分けてしまうと、相続に伴って事業用資産が売却されてしまったり、あるいは複数の相続人で株の持合いをすることで会社としての意思決定ができないといった事態にもなりかねず、そもそも事業の継続が困難になってしまいます。
このため、事業の経営者の方が、事業を手伝っている子供のうちの一人に対して家業を引継ぎしたいという意思を持っているならば、遺言書を作成することでその子供に事業用資産や経営する株式を承継させることができます。
ただし、注意しなければならないのは、他の子供には遺留分がありますので、後日、他の子供から事業を承継した子供に対して遺留分侵害額請求がされると、結果的には、家業を引き継いだ子供はこの金額を支払う必要があります。仮に、事業を承継した子が、その金額を支払うお金を手当てできないと、事業用資産を売却して支払うことになったり、相続した株式を譲渡したりということになり、会社経営をスムーズに行うことができなくなります。
そのため、事業を引き継ぐ子供には、この遺留分に相当する金銭を支払うことができるように、別途お金を用意してあげる手当てをしておくことが大切となります。例えば、被保険者を事業の経営者とする生命保険契約を締結しておき、死亡保険金の受取人を事業を承継する子とするといった方法があります。
-
4-9 離婚し再婚した夫が、後妻に遺産を相続させた後、後妻が死亡したとき(後妻との間には子供がいない)には、前妻との間の子供に遺産を相続させたいというケースでは、遺言書を作成することでこのようなことができるでしょうか?
-
このケースでは、夫は、後妻との間に子供がいないため、夫が死亡した場合には、遺言書により一旦は後妻に財産を相続させますが、その後に妻が死亡ときは、本来であれば後妻の兄弟姉妹が相続人となるところ、後妻の兄弟姉妹には自分の財産を相続をさせたくないことから、後妻死亡後には前妻との間の子供に対して後妻の財産を相続させたいという希望を持っているものと考えられます。
このような夫の気持ちを遺言で叶えることができるでしょうか?
これを遺言で実行しようとすると、夫は後妻へ全財産を相続させる旨の遺言を作成するとともに、後妻も前妻との間の子供に全財産を相続させる旨の遺言を作成しておくことにより実現可能なようにも見えます。
しかしながら、夫死亡後に、後妻は相続した財産をどのように処分しても自由ですし、また、その後に後妻は前妻との間の子に相続させる旨の遺言を作成することも自由ですので、結局は、夫の希望は叶わない可能性もあります。つまり遺言による方法では、遺言者は、将来(次の次)の財産の承継人までは指定できないのです。
このような夫の希望を叶える方法としては、一つは「信託」という方法があり、受益者連続型信託の方法を活用すれば、このような夫の意思を実現することができます。
受益者連続型信託によれば、夫は、受益者を後妻と指定した上で、受益者の後妻が死亡した場合の第二受益者を前妻との間の子と指定することができます。このように、受益者連続型信託によれば、将来にわたって受益者を指定することができます。
以上のように、家族信託には、遺言によってはできないことが実現できますが、一方で家族信託には様々なデメリットもあります。例えば、①複数の賃貸不動産を所有している場合に、一部の不動産についてのみ信託を利用しているときは、その不動産に生じた損失は、他の不動産の所得(黒字)とは損益通算できない、②信託財産に係る収益額の合計額が3万円以上ある場合には、毎年1月31日までに信託の計算書を税務署に提出する必要があり手間がかかる、③信託の設計には専門的知識が必要であり、専門家への報酬が多額(50万円~100万円)となることなど、のデメリットがあります。
もう一つの方法としては、「配偶者居住権」を設定する方法があります。夫死亡時において、配偶者(後妻)と先妻との間の子との間で、配偶者(後妻)には配偶者居住権及び敷地利用権を相続させて、一方で、先妻との間の子には配偶者居住権という負担のついた建物及び敷地利用権という負担のついた土地の所有権を相続させることによって、配偶者(後妻)は夫の死亡後も居住用不動産に住み続けることができ、前妻との間の子は配偶者(後妻)の死亡後には配偶者居住権及び敷地利用権が法律上当然に消滅しますので完全な建物及び土地の所有権を取得することができます。
ただし、配偶者居住権は処分できないなどのデメリットもありますので、例えば、仮に配偶者(後妻)が将来介護施設に入居しようと考えて、配偶者居住権を放棄又は合意解除により消滅させると、その時点で居住建物所有者は経済的利益を受けたとして贈与税が課税されるなどの問題が生じます。したがって、配偶者居住権を利用しようとする場合には、将来の介護施設への入居の可能性も考えて専門家のアドバイスを受けることが大切になります。
以上のように、専門家と相談しながら、遺言、後見、信託、配偶者居住権などといった制度の中からベストな選択と組合せを考えていくこと重要になります。
-
4-10 相続について、単純承認、限定承認、相続放棄の違いは何でしょうか?
-
単純承認は、被相続人の権利や義務をすべて承継する方法になります。一般的には、単純承認により被相続人の遺産を承継するケースが大半ですが、借入金などの債務の額が財産の額よりも多いときには、次の限定承認や相続放棄が利用されることがあります。
限定承認は、被相続人の財産の範囲内で、債務を承継する方法になります。限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐという方法ですので、非常に有用な制度といえます。
また、債務超過であって限定承認をする場合であっても、相続人が居住する自宅を限定承認により承継したい場合には、自宅の価額相当額の債務を弁済すればその自宅を自分のものとできますので、相続放棄するよりは限定承認の方がメリットがあります。
ただし、限定承認をした場合には、税法上は様々なデメリットもあります。
一つは、被相続人の所有する不動産についてのキャピタルゲイン(値上がり益)を一旦清算することとなるため、相続人に対して相続開始時の時価で譲渡があったものとみなされますので(所得税法第59条第1項)、被相続人の所得税(譲渡所得)についての申告と納付を死亡日から4箇月以内にしなければならないことになっています。この申告は、相続人が被相続人の所得税の準確定申告という形で申告することになりますが、非常に短い期間での申告をしなければなりませんし、また、一度に多額の譲渡所得税の納税をしなければならないというリスクもありますので、限定承認をする場合には注意が必要です。なお、この場合の所得税(譲渡所得)の税額は、相続税の申告において債務控除の対象になります。
もう一つは、限定承認に係る譲渡所得税については、被相続人と相続人との間で時価で譲渡したものとみなして課税されるものですので、いわゆる族間での売買に該当し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の適用は受けられないということです。
このように、限定承認には、メリット、デメリットの両方がありますので、よく検討してする必要があります。
相続放棄は、被相続人の財産も債務もすべて承継しない方法になります。相続放棄は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄する旨を申述する必要がありますので、短期間の間に被相続人の財産及び債務を調査しなければなりません。
なお、相続放棄をしたとしても、被相続人が保険契約者で保険金受取人が相続放棄をした相続人となっている場合には、死亡保険金は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となりますので、相続放棄をしたとしても死亡保険金を受け取ることができます。相続放棄した者が受け取った死亡保険金については、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、相続放棄した者は相続人ではないことから相続税の非課税の適用を受けることはできませんので、受け取った全額が相続税の課税対象になります。
-
4-11 寄与分とは?
-
寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加に寄与をした者(寄与した者は、相続人に限ります。)があるときは、共同相続人の協議で、この者の寄与分を定めることとし、協議が整わないとき、または協議ができないときは、寄与した者の請求により、家庭裁判所が寄与分を定めることになっています(民法第904条の2)。
具体的な計算方法は、
①相続開始時の相続財産の額ー寄与分額=みなし相続財産の額
②みなし相続財産の額×各人の法定相続分=各人の具体的相続分の額
③寄与者の具体的相続分の額+寄与分額=寄与者の具体的相続分の額
これによって、寄与した者の相続分を、法定相続分よりも多くすることができる制度となっています。
なお、寄与した者は相続人に限られること、特別の寄与であるので通常の夫婦の協力扶助義務の範囲内や親子などの扶養義務の範囲内のものは寄与に当たらないこと、被相続人の財産の維持又は増加に寄与することが必要であることに注意します。
-
4-12 特別寄与分とは?
-
特別寄与分とは、2018年(令和元年)7月1日施行の民法相続法の改正によりできた制度になります。
被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務を提供したことにより、被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)は、相続開始後、相続人に対して、特別寄与者の寄与の定めた額(特別寄与料)の支払を請求することができるとなっています(民法第1050条)。この場合、請求の相手となる相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に法定相続分又は指定相続分を乗じた額を負担することになります。こちらも、特別寄与料の支払について、当事者間に協議が整わないとき、または協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。なお、特別寄与分の請求は、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6箇月以内、又は相続開始のときから1年以内に請求をしないとできないことになっていますので、注意が必要です(民法第1050条第2項)。
このような特別寄与分は、例えば、相続人である長男の妻が、被相続人の療養看護に努めた場合において、相続人でない長男の妻には寄与分の主張をすることができないこと、家事審判の中では長男(夫)の寄与分の算定上考慮されることがあるが長男(夫)が先に死亡したときは全く考慮されないなどの不都合(不公平感)があったことから、新たな制度としてできたものになります。
特別寄与料の支払及び受領があった場合の相続税法上の取扱いについては、特別寄与者が、特別寄与料を受け取った場合(支払うことが確定した場合)には、特別寄与料の額に相当する金額を被相続人から「遺贈」により取得したものとみなされて、相続税が課税されることになります(相続税法第4条第2項)。一方、相続人が支払うべき特別寄与料の額は、その相続人に係る相続税の課税価額から控除(債務控除)することになります(相続税法第13条第4項)。
なお、特別寄与者は、一親等の血族及び配偶者以外の者であることから、相続税額の計算に当たっては、相続税の二割加算の対象となります(相続税法第18条第1項)。
さらに、もし仮に、特別寄与者である長男の妻が、被相続人から生前贈与を受けていた場合には、特別寄与者である妻は「遺贈によって財産を取得した者」に該当しますので、その贈与財産については相続開始前3年以内贈与に該当するものがあれば、生前贈与加算として相続財産に加算されて相続税の計算をすることになっています(相続税法第19条第1項)。
-
5-1 遺留分とは、何でしょうか?
-
遺留分とは、被相続人の財産を相続するに当たって、一定の法定相続人に対して法律上最低保証されている遺産の割合のことであり、残された相続人の生活の保障として認めれれているものです。
この遺留分は、相続人が直系尊属のみの場合は3分の1、それ以外の場合(例えば、相続人が妻及び子供)は2分の1と定められています(民法第1042条第1項)。
なお、兄弟姉妹が相続人となる場合には、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言を作成することにより相続から完全に除外することができます。
相続人は、相続開始前でも相続開始後でも遺留分を放棄することができます。ただし、相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可が必要になります(民法第1049条)。
最後に、被相続人が遺言書を作成しており、その遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、遺留分を有する相続人は、遺留分を侵害した受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額請求権を行使(遺留分侵害額相当の金銭の支払を請求できるということ)することができます(民法第1046条)。なお、遺留分侵害額の請求は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年以内、または相続開始のときから10年以内に請求をしないと時効によって消滅しますので、注意が必要です。
-
5-2 遺留分を侵害する遺言書は有効でしょうか?
-
遺留分を侵害する遺言書であっても、法律上は有効となります。
例えば、相続人が、配偶者の妻、長男、長女の3人の場合に、被相続人が「全財産を長女に相続させる。」という内容の遺言書を作成していた場合、このような遺言書も有効となりますし、結果的に、他の相続人(長男)から、遺留分侵害額請求権の行使がされなければ、長女は全財産を相続することができます。
ただし、このような内容の遺言書を作成した場合には、後日、遺留分を侵害された相続人から、遺留分侵害額請求権を行使されるリスクは当然にあります。
したがって、遺留分権利者から遺留分侵害額請求権を行使されることを防止するためには、他の相続人の理解が得られるように、遺言書に付言事項を記載しておくことをおススメします。例えば、「遺言者は、妻〇〇の介護をすることを条件として、長女〇〇に全財産を相続させることとしたので、長男〇〇には、この点を考慮し、遺留分侵害額請求をしないように望む。」とか、そのような遺言書を作成した理由や事情などを遺言書に記載します。ただし、このような付言事項には、法的拘束力はありませんので、最終的に遺留分侵害額請求権を行使するかどうかは他の相続人の意思にかかっています。
また、上記の事例の場合、全財産を相続することとなる長女は、遺留分侵害額請求権を行使された場合には遺留分に相当する金銭を支払う必要がありますので、その辺りの資金手当て(例えば、財産が自宅しかないような場合、死亡生命保険金の受取人を長女とし、これをもって支払いに充てるようにさせる。)についても考えておくとよいでしょう。
-
5-3 遺留分侵害額請求権の行使は、どのようにすればよいでしょうか?
-
遺留分侵害額請求権の行使は、相手方に対する意思表示によってすることになっており、口頭で行使することも可能です(裁判上行使する必要はありませんし、書面にて行使する必要もありません。)。
ただし、実務上は、遺留分侵害額請求権の行使があった事実を証拠として残すために、配達証明付の内容証明郵便により書面を送付することが一般的になります。
この場合、書面には、①請求をする本人と相手方、②請求の対象となる遺贈・贈与・遺言の特定、③遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求する旨、④請求の日時を記載します。遺留分侵害額の進学を特定する必要はありません。
書面の記載例としては、例えば、「私は、Aの相続人で遺留分権者になりなすが、貴殿が被相続人Aから令和〇年〇月〇日付遺言書により遺贈を受けたことによって、私の遺留分を侵害しておりますので、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。」というようになります。
なお、遺留分侵害額請求権の行使には、次のようなルールがあります(民法第1047条、第1048条)。
① 相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈又は贈与があったことを知ったときから1年以内に行使しなければなりません。
相続開始から10年を経過したときは行使できなくなります。
② 遺言による受遺者と贈与による受贈者がいる場合には、先に受遺者に対して行使します。
③ 受遺者が複数いる場合には、目的物の価額割合に応じて按分します。
④ 受贈者が複数いる場合には、相続開始時に近い日付の贈与から先に順番に行使します。
-
5-4 遺留分侵害額請求権の行使に対する対応方法は?
-
遺留分を侵害する遺言書であっても有効ですが、仮に、遺留分侵害額請求権が行使がされた場合には、その金額に相当する金銭の支払いをしなければならなくなります。そうすると、例えば、相続財産としては、自宅しかないケースでは、請求を受けた者が万一その金銭を支払うことができないときには、自宅を処分してその代金の中から支払うしかないことにもなりかねません。
したがって、そのような相続人間の紛争を避けるためには、遺言書の中で、特定の相続人に対して全財産を相続させる代わりに、他の相続人に対しては金銭(代償金)を支払わせることでバランスを取ることも検討すべきでしょう。
遺言書の記載としては、
「1 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、長男〇〇に相続させる。
2 長男〇〇は、前項の遺産を取得する代償として、長女〇〇に対し、金〇〇円を支払う。」
と記載することになります。
また、全財産を取得する特定の相続人には、代償金の資金手当てを行うために、その特定の相続人(上記の例では長男)を保険金受取人とする生命保険契約を締結することが有効です。生命保険金は、受取人の固有の財産であり、遺産分割の対象になりませんので、他の相続人(長男)は、受け取った死亡保険金をもとに長女に対して代償金を支払うことができます。
-
5-5 遺留分侵害額請求がされた場合に、金銭の支払いに代えて、相続財産中の不動産や自己の所有する不動産を代償財産として交付することは可能でしょうか?
-
遺留分侵害額請求がされた場合に、金銭の支払に代えて、相続財産中の不動産や自己の所有する不動産を代償財産として交付することが可能です。
ただし、この場合、遺留分侵害額請求を受けた者は、代償財産として相続財産中の不動産や自己の所有する不動産を譲渡して、その金銭の支払を履行していることになりますので、所得税法上は、遺留分侵害額の請求を受けた者は、消滅した債務の額に相当する価額(遺留分侵害額に相当する金額)によって当該不動産を譲渡したものとして取り扱われますので、譲渡所得税が課税されることになりますので注意が必要です(所基通33-1の6)。
このように余分に税を負担するリスクがあることを考えると、「全財産を〇〇に相続させる」旨の遺言書を作成することが良いかどうかは非常に大きな問題です。遺言書の内容はよく検討したいものです。
-
6-1 万一自分が死んだ場合に備えて、遺言書は作成しておいた方がよいですか?
遺言書を作成するメリットを教えてください。
-
遺言書を作成することで、相続人は円滑に相続することができますし、争族争いを防止するための遺産分割対策にもなります。
民法の規定では、遺言書がない場合には、民法の規定である法定相続分によって遺産を分けることになります。もちろん、実際には、すべての相続人が集まって遺産分割協議をして分けることにはなりますので、必ず法定相続分で分けるということにはなりません。
遺言書を作成するメリットは、次の3つがあります。
①生前のご自身の希望を叶えられます(自宅は妻に相続させたい、事業は長男に相続させたいなど)。
②遺言書を作成することで、将来の遺産の分け方を巡る争いを防止することができます(遺言が法定相続に優先します。)。
③遺言書を作成することで、相続手続(遺言執行手続)がスムーズにできます(遺産分割協議が不要になります。また、公正証書 遺言や自筆証書遺言保管制度を利用すれば、家庭裁判所の検認手続が不要になります。)。
④子供がいない夫婦では、親が生存していない場合、亡夫(妻)の兄弟姉妹に遺産が相続されることを防ぐことができます(配偶者と兄弟姉妹が相続人のケースでは、配偶者の法定相続分は4分の1、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1となります。兄弟姉妹には、遺留分がありませんので、遺言書があれば、残された配偶者が全財産を相続することができます。)。
⑤相続税法上の各種の特典(配偶者税額軽減、小規模宅地の特例、相続税の納税の猶予など)を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割が成立していることが必要になります。仮に、申告期限までに遺産分割協議が成立しなかった場合には、これらの特典の適用が受けられなくなります。この点、公正証書遺言書が存在すれば、遺産分割も不要となりますので、これらの相続税法上の特典を確実に受けることができます。
-
6-2 遺言書では、どのようなことを定めることができますか?
-
遺言書に記載しておくことで法的効力が認められるもの(有効なもの)には、次のようなものがあります。
①相続分の指定又は指定の委託(民法第902条)
②遺産分割方法の指定又は指定の委託(民法第908条)
③遺贈(民法第964条)
④相続人の廃除、廃除の取消し(民法第892条)
⑤子供の認知(民法第781条第2項)
⑥遺言執行者の指定(民法第1006条)
⑦祭祀の主宰者の指定(民法第897条)
⑧未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法第839条、第848条)
⑨共同同相続人間の担保責任の指定(民法第914条、第911条)
⑩特別受益の持戻し免除(民法第903条第3項)
⑪遺留分侵害額の負担割合の指定(民法第1047条第1項第2号但書)
-
6-3 遺言で定めることができない事項には、どのようなものがありますか?
-
次のような項目は、遺言書で定めても法的効力はありませんので、遺言者の意思を実現することはできません。
①死亡直後の事務処理
死亡直後の事務、例えば、知人・友人・親戚・職場などへの死亡連絡、役所への諸手続、葬式、供養、入院代の精算、運転免許証の返納、スマホ、パソコンなどのデータや各種アカウントの削除などは、家族や生前に信頼できる友人、親戚、専門家などと「死後事務委任契約」を締結することで行ってもらうことができます。
②延命治療をしないこと(尊厳死)の意思表示
現在の日本では、病気や事故などで回復見込みのない末期状態になった患者に対して生命維持治療を中止して人間としての尊厳を保ちながら死を迎えるといういわゆる尊厳死の法律は整備されておりません。したがって、家族や本人が延命治療の中止を頼んでも、医師は延命治療をやめることはしません。延命治療は、本人、家族にとっても精神的な負担もあり、医療費の支払といった経済的な負担もあります。このような場合に備えて、公正証書により「尊厳死宣言書」を作成して、尊厳死の意思を家族に伝えておく方法があります。
③ペットの世話
おひとり様で自分が死亡した後のペットの世話を知人に依頼したい場合には、知人との間で「死後事務委任契約」を締結しておくことができます。
④婚姻、離婚、養子縁組
これらは、相手との合意が必要な事項でありますので、単独行為である遺言ではできません。
⑤債務の承継
債務については、相続発生と同時に、自動的にその相続人に対して法定相続分の割合で承継されますので、債務を特定の相続人に承継させることができません。
-
6-4 遺言書の種類を教えてください。また、それぞれの遺言書のメリット・デメリットは何ですか?
-
遺言書には、①「自筆遺言証書」、②「自筆遺言証書(自筆証書遺言保管制度を活用)」、③「公正証書遺言」、④「秘密証書遺言」の4種類があります。このうち、秘密証書遺言は、実務上ほとんど使われることがありません。
①「自筆遺言証書」は、費用がかからない、内容は誰にも分からないなどのメリットがあります。
しかし、方式・内容が厳格に定められており、方式・内容に誤りがあると無効になってしまいます。また、遺言書の偽造・変造・改ざん・破棄・紛失・未発見のリスクがありますし、さらに、遺言の執行には、家庭裁判所の検認手続が必要であり、預金の解約や相続登記などの相続手続に時間がかかるというデメリットがあります。
②「自筆証書遺言(自筆証書遺言保管制度の利用)」は、令和2年7月10日から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえる制度になります。これは、費用は安くて(保管申請に係る手数料は3,900円、しかも遺言者の死亡日から50年間(画像データは遺言者死亡後150年間)法務局が遺言書を保管してくれるので、偽造・変造・改ざん・破棄・紛失のリスクがなく、さらに遺言の執行には家庭裁判所の検認手続が不要ですので、すぐに相続手続ができます。さらに、法務局では、全国で保管してある自筆証書遺言の検索もできます。
一方で、法務局では、遺言書の形式面はチェックしますが、内容面にまで踏み込んで判断することがないため、遺言書が無効になるリスクはあります(したがって、専門家によるサポートが必要です。)。
③「公正証書遺言」は、公証役場において裁判官や検事などをやめた公証人が遺言書を作成するものになります。法律のプロである公証人が作成しますので、後で方式や意思能力が問題になって遺言書が無効になることはほとんどありません。また、公証役場で遺言書を保管(遺言者が120歳になるまで保管)しますので、偽造・変造・改ざん・破棄・紛失のおそれはありません。家庭裁判所の検認手続も不要なので、すぐに相続手続ができます。さらに、公証役場では、全国で保管する公正証書遺言の検索もできます。
デメリットとしては、証人2人に遺言の内容が知られること、費用がある程度(公証人の作成費用、専門家のサポート費用、証人の日当などで5万円~20万円程度)かかることがあげられます。
このうち、どの方式を利用するかは、遺産の多寡、相続人間での紛争の可能性、遺言内容が単純か複雑かなどによって、判断することになりますが、後日、遺言書の有効性が問題になることを避けたい場合や、遺言書の破棄・紛失といったリスクを防止したいという場合には、ぜひとも公正証書遺言によることをおススメします。
-
6-5 遺言書は、自筆遺言証書で作成してもよいでしょうか?
-
自筆遺言証書であっても、遺言書としては有効ですので、自筆遺言証書で作成することはもちろん差し支えありません。
しかし、文献などを参考に、ご自身で作成することは、よほど単純なもの(例えば、「全財産を妻に相続させる。」など)でもない限り、方式・内容に誤りがあると無効になってしまいますので、やめた方がよいかもしれません。また、訂正する場合のルールも厳格に定められておりますので、定まった方式で訂正していない場合には、遺言書自体が無効になっったり、あるいは、訂正部分が有効にならなかったりしますので、ご自身で作成するのはやめた方が良いかもしれません。
作成する場合は、専門家にサポートしていただいた方がよいと思います。
-
6-6 自筆遺言証書を作成する場合のルールについて教えてください。
-
自筆遺言証書は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、押印しなければなりません(民法第968条第1項)。
遺言書の全文を自書する必要があるため、パソコンやワープロで作成することはできません。
日付は、遺言書を書いた日になりますので、令和〇年〇月〇日と明確に記載します。令和〇年の誕生日や令和〇年元日という記載ならば、日付を特定することができますので構いませんが、令和〇年〇月吉日という記載では、日付が特定されませんので、無効になってしまいます。
署名は、自書でなければなりません。後日のトラブルを避けるために、戸籍上の氏名で記載することが望ましいです。
印は、実印でなく、認印でも構いませんが、後日のトラブルを避けるためには、実印で押印することが望ましいです。
用紙については、便せん、コピー用紙、ノートを破った紙など特に何を使用しても構いません。
筆記用具については、万年筆、ボールペン、筆といったものになりますが、鉛筆や消せるボールペンは使用しようしないようにしましょう。
遺言書が数枚にわたるときには、本文末尾に押印した印と同じ印で割印(契印)を押しておくと、一連の遺言書であることを証明できます。
最後に、遺言書は、書いた紙を裸のままにして保管してもよいですが、封筒に入れて封をして保管するのが望ましいでしょう。封をして閉じ口に押印したり、「メ」「緘」と書いて封印までしますと、遺族がこれを見つけても家庭裁判所に持ち込むまでは開封できなくなります(開封するなど違反すると5万円以下の過料に処せられます。)。
-
6-7 自筆遺言証書の訂正の仕方を教えてください。
-
自筆証書遺言について、加除、その他の変更をするときは、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して署名し、変更の場所に押印しなければなりません(民法第968条第3項)。
財産目録の記載の一部を訂正する場合には、適宜の方法で訂正をした上で、例えば、「目録(一)第三行中、二文字削除、二文字追加」等の文言を付記した上で署名するととも、訂正箇所に押印することになります。
なお、自筆証書遺言の訂正の仕方については、法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/content/001279213.pdf)を参考にしてください。
-
6-8 自筆遺言証書を書く場合の留意点は何でしょうか?
-
特に、「財産目録」の記載については、留意する必要があります。
不動産の表示については、法務局の登記簿(登記事項証明書)に記載されたとおりに、土地は、所在、地番、地目、地積を、また、家屋は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を、それぞれ正確に記載します。なお、登記事項証明書における土地の地番は、住民票上の住所を示す住所表示とは記載が異なりますので注意してください。
預貯金については、金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号、口座名義人まで正確に記載します。この際、預金金額は記載しなくても構いません。
株式については、会社名、本店所在地、株式の種類、株式数を正確に記載します。
なお、平成30年の民法改正(平成31年1月13日から施行)により、「財産目録」については、①パソコンで作成したもの、②通帳の写し、③不動産の登記事項証明書の写しなどでもよくなりました(民法第968条第2項)。ただし、毎葉(各頁)ごとに、署名、押印が必要になります(自書によらない記載がその両面にある場合には、両面に署名押印をしなければなりません。)。なお、本文と財産目録の間や財産目録の各用紙の間に割印(契印)をする必要はありません。
目録が、複数頁にわたるときには、例えば、左上に別紙1、別紙2、別紙3と記載するか、あるいは、各頁の右下に1/3、2/3、3/3と記載するとよいでしょう。
-
6-9 法務局で保管する自筆証書遺言とは、どのようなものでしょうか?
-
2020年(令和2年)7月から、自筆証書遺言の保管制度が始まり、全国の法務局において、自筆証書遺言を保管してくれる制度になりました。
手続の流れは、以下のとおりになります。
①遺言書を作成します。
→ 通常の自筆証書遺言と同様に、全文(財産目録を除く。)を自書し、署名・押印をします。なお、財産目録については、登記事項証明書や預金通帳のコピーでも差し支えありません。
②遺言書の保管場所を決定します。
→ 保管する場所は、遺言者の住所地、本籍地、遺言者が所有している不動産所在地のいずれかの法務局になります。
③申請書を作成します。
④保管申請の予約をします。
⑤本人が保管の申請をします。
→ 遺言書は、ホッチキス止めはしません。代理人による申請は認められません。
このような自筆証書遺言保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認が不要となりますので、直ちに遺言の執行に着手できますので、スムーズに相続手続ができます。
ただし、法務局では、申請書の受付に当たり、遺言書の形式面でのチェックを行うにとどまり、遺言書の内容の審査までは行いませんので、遺言書の作成に当たっては、行政書士、司法書士などの専門家のアドバイスを受けることをおススメします。
添付書類として、申請書
本籍の記載のある住民票の写し(作成後3か月以内)
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
手数料は、1通3,900円必要です。
⑥保管証を受け取ります。
この自筆証書遺言保管制度を利用した場合、手続費用が安く、しかも相続開始後の家庭裁判所による検認が不要であり、法務局が保管するので、紛失・破棄のリスクもありません。
-
6-10 遺言書は、いつ作成したらよいでしょうか?
-
作成しようと思いついた日に作成の準備をした方がよいと思います。年齢でいくつになったらということは特にありませんが、認知症のリスクを考えると、できれば65歳を過ぎたら、遅くとも70歳までには作成したいものです。
作成するタイミングとしては、自宅を取得した時、子供や孫が生まれた時、定年退職をした時、重大な病気が発見された時など節目の段階で作成するのも、一つのきっかけにはなるかと思います。
-
6-11 争族を防止するために遺言書を作成する場合のポイントは何でしょうか?
-
遺言書を作成する場合、後日争族とならないようにするためには、以下のポイントに留意する必要があります。
①遺言書を書き換える場合には、従前の遺言書をすべて撤回する旨を記載し、改めてすべての遺産について遺言を作成します。
②遺言者が死亡した場合に財産をもらう者(受遺者)が遺贈の効力発生(遺言者の死亡)前に万一死亡した場合に備えて、受遺者が先に死亡していた場合には、誰(例えば孫)に遺贈するかを記載しておきます(予備的遺言)。
③相続開始後にすぐに預貯金の解約などができるようにするため、遺言執行者を必ず定めておきます。
④遺言書の書き方として、推定相続人に対して遺贈する場合には「相続させる」と記載します。推定相続人以外の者に対して遺贈する場合には「遺贈する」と記載します。
⑤できれば安全で確実な公正証書遺言により作成します。
⑥後日の争族争いを避けるためにも遺留分に配意した遺言書を作成することが望ましいと考えます。
⑦財産についてだけではなく、債務の承継者も定めておきます。例えば賃貸マンションとマンションの借入金はセットで一人に承継させます。ただし、債務を一人が承継するには、遺言の効力発生後に銀行など債権者の同意が必要となります。
⑧特定遺贈する方式(A土地については長男に、B預金については長女に相続させること)で定めることもできます。
複数の相続人に対して、割合的に財産を相続させること(全財産を長男及び長女に各2分の1ずつ相続させること)は、共有となった財産の解消が難しいのでできるだけ避けます。
⑨財産が自宅しかなく居住する妻に自宅を相続させたいケースや、自社株式があり後継者に事業を相続させたいケースでは、相続後に争いが生じないように、そのような遺言をした理由などを付言事項として記載しておきます。
⑩お墓や先祖の供養、父母の扶養介護についての思いを記載しておいてもよいでしょう。
-
6-12 遺留分を意識した遺言書を作成する場合、どのような点に留意したらよいでしょうか?
-
遺言書を作成する場合に、特定の子供に自宅を相続させたいとか、事業を相続させたいといった場合には、特に注意が必要です。なぜなら、法定相続分通りに遺産をもらえると思ったのにもらえなかった相続人には、最低保障ともいえる遺留分(民法第1042条)の権利がありますので、当然、遺留分侵害額請求(民法第1046条)をしてくる可能性が高いからです。
この場合、遺留分侵害額請求を受けた相続人(自宅を相続した相続人や事業用財産を相続した相続人など)は、請求を受けた金額を直ちに金銭で支払う必要があります。仮にこの資金手当てができなかった場合には、結果的に、せっかく取得した相続財産を売却して支払うことにもなりかねません。しかも、この遺産を譲渡したことに関しては、別途所得税(譲渡所得)がかかります。
これを防ぐためには、①遺言者がその相続人を死亡生命保険金の受取人に指定(生命保険金は固有の財産であり相続財産にはなりません。)して、別途、支払の資金を手当てしてあげるか、あるいは、②各相続人の遺留分(民法第1042条)に配意した内容となるように遺言書を作成することになります。
-
6-13 遺言書を作成しておいた方が良いケースを教えてください。
-
次のケースは、遺言書をぜひとも作成しておくべきかと思います。
①お一人様(身寄りがなく、相続人もいない方)
②子供がいない夫婦
③夫婦2人で自宅に居住しており、子供は遠方に居住している方
④高齢(例えば80歳超)で今後認知症になった場合のことが心配な方
⑤持病があり突然病気で倒れた後のことが心配な方
もう少し詳しく解説しますと、
①のケースは、遺言書がなければ、遺産は国庫に帰属することになります(民法第959条)。自分の財産を国庫に帰属させたくなければ遺言書を作成することによって、ご自身の思いを叶えてくれるような公益法人や社会福祉法人などに寄付することができます。また、ペットを飼っていた人は、ペットを世話してくれる人に財産を遺贈することもできます。
②のケースは、夫が死亡した場合において、直系尊属(親、祖父母など)が生存していなければ、遺言書がなければ亡夫の兄弟姉妹が相続人になります。この場合の兄弟姉妹の相続分は4分の1となりますので、残された妻が全財産を相続することはできません。したがって、自宅などを兄弟姉妹に奪われてしまわないようにするには、「全ての財産を妻に相続させる。」という遺言書を作成しておけば、残された妻(夫)が全財産を相続することができます。
③のケースでは、最近は、子供たちは法律で定められた相続分を主張することが多く、しかも相続分はお金で欲しいというケースが増えております。分け合う金銭を捻出するために、自宅を売却して法定相続分で分けるといったケースも非常に増えています。このケースで残された妻が自宅にそのまま住み続けるためには、遺言書が必要になります。
④のケースでは、当然のことですが、認知症になったら事理弁識能力(判断能力)がありませんので、遺言書を作成することはできません。また、所有不動産を売却して介護施設に入居する契約をすることや、預貯金の払戻を受けることもできません。これを防ぐには、認知症にならないうちに遺言書を作成するとともに、財産の管理を任せられる家族との間で任意後見契約を結んでおくことが有効です。
⑤のケースでは、脳梗塞などで突然倒れて入院するケースなどがあります。この場合、本人に判断能力がないとなると、家族であっても預貯金の引出ができなくなるので、病院代の支払もできなくなります。仮に、万一死亡してしまった場合には、家族には、そもそもどこにどのような財産や債務があるのかすら分からない事態にもなります。もし遺言書がなければ、相続人間の話合いで遺産を分けることになりますが、場合によっては、相続争いにもなりかねません。遺言書を作成しておくことで、どのような財産があるのかが家族にも分かり、相続争いを防ぐいこともできます。
-
6-14 遺言書には、遺言執行者を定めておいた方がよいでしょうか?
-
遺言執行者とは、遺言内容を実現する人になります。具体的には、家庭裁判所での遺言書の検認請求、相続人の調査、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割までの財産の保全、管理、遺言の執行に必要な一切の行為などを行います。
遺言執行者は、未成年者及び破産者以外であれば、誰でもなることができます。
遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しており(民法第1012条第1項)、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接その効力を有することになります(民法第1015条)。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為を一切することはできませんので、これに反する行為は無効になります(民法第1013条)。
遺言書に遺言執行者を定めておくことにより、このような強い効力があります。
仮に、遺言書で遺言執行者を定めていない(又は定めていた遺言執行者がなくなった)場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が選任することになりますので(民法第1010条)、通常、遺言執行者が選任されてから、預金の解約等の手続を行うまでに数か月を要することになります。とすると、この間の葬式費用や未払の病院代の支払などは、別途自分のお金で立て替えなければならないことになります。
また、遺言執行者が定めてられていない場合には、不動産の相続登記については、相続人全員から行う必要がありますので(相続人全員の印鑑証明書が必要ということです。)、せっかく遺言書で不動産を相続するとなっていても、場合によっては、登記手続に当たり印鑑証明書の提供を受けれないなど他の相続人の協力が得られないこともあり得ます。
これに対して、遺言書(検認手続が不要な公正証書遺言や法務局保管の自筆遺言証書に限ります。)において遺言執行者を定めてある場合は、すぐに遺言内容の執行手続ができます(相続登記に添付する印鑑証明書は、遺言執行者の印鑑証明書のみでできます。)。そうすると、遺言書で財産を取得する相続人は、相続開始後、他の相続人の協力を得ないで、直ちに預金の解約や不動産の相続登記ができますので、この点は非常に大きなメリットといえます。
したがって、遺言書には、必ず信頼できる人を遺言執行者に定めておくことをおススメします。なお、遺言執行者には、子供や親類、行政書士などの専門家のうちから信頼できる人に事前にお願いしておくとよいでしょう。
-
6-15 遺言書の記載で「相続させる」と「遺贈する」の違いは何でしょうか?
-
遺言書の意味は、遺言書の記載文言どおりに判断します。
一般的には、相続人に対して財産を取得させる場合には、「甲不動産をAに相続させる。」と書きます。
ただし、例えば、相続人のうちの一人のAに対して「甲不動産を遺贈する。」旨の特定遺贈をするケースもあります。また、相続財産の全てを共同相続人全員に対して「全財産をAに6分の4、Bに6分の1、Cに6分の1の割合で遺贈する。」旨の包括遺贈をするケースもあります。
これに対して、相続人以外の者に財産を取得させる場合には、一般的には「遺贈する。」と書きます。
それでは、相続人に対して「相続させる」と、相続人以外の者に対して「遺贈する」の違いは、次のとおり、相続登記の手続が単独でできるか、共同で行う必要があるかという点、登録免許税などの税金が異なる点にあります。
相続人に対して「相続させる」旨の遺言は、共同相続人間で遺産分割協議を行うことなく、相続によって直ちにその財産が移転することになります。例えば、「甲土地をAに相続させる」旨の遺言(「特定財産承継遺言」といいます。)があると、Aは相続と同時に何らの手続を要することなしに、直ちに甲土地を相続することができます。要するに、遺言を執行する手続は不要ということです。しかも、不動産登記手続との関係でいえば、「相続」を原因とする所有権移転登記は、不動産を相続するA単独で申請することができますし、登録免許税も固定資産税評価額の1,000分の4で済みます。また、相続による所有権移転では不動産取得税はかかりません。
これに対して、相続人以外の者に対して「遺贈させる」旨の遺言は、財産移転のためには遺言執行者による執行を行う必要があります。したがって、例えば、「甲土地をAに遺贈させる」旨の遺言があると、不動産登記手続との関係では、「遺贈」を原因とする所有権移転登記は、受遺者のAと遺言執行者との共同申請(仮に遺言執行者がいなければ共同相続人全員との共同申請となりますので、登記申請には遺贈者の相続人全員の印鑑証明書が必要になります。)となり、しかも登録免許税は固定資産税評価額の1,000分の20が必要になります。また、遺贈による所有権移転については、不動産取得税が課税されます。
相続人に対する「相続させる」旨の遺言書と相続人以外の者に対する「遺贈する」旨の遺言書には、このような違いがあります。
-
6-16 包括遺贈と特定遺贈は、どう違いますか?
-
包括遺贈とは、遺産の全部又は一定の割合を指定して行う方法になります。例えば、「私の遺産の3分1をAに、3分の2をBに遺贈する。」という内容になります。
これに対して、特定遺贈とは、遺産の中から譲り渡したい財産を特定して行う方法になります。例えば、「甲土地をAに遺贈する。」という内容になります。
包括遺贈と特定遺贈の違いは、次のとおりです。
①包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますので(民法第990条)、借入金などのマイナスの財産を引き継ぐことになります。これに対して、特定受遺者は、借入金などのマイナスの財産は引き継ぎません。
②包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することから、通常の相続の放棄・承認のルールに従って、相続を知った日から3か月以内であれば遺贈を放棄することができます(民法第915条)。もし仮に3か月以内に遺贈を放棄しなければ、単純承認したものとみなされますので、資産よりも負債の方が多いときには、自分の財産を弁済に充てる必要があります。これに対して、特定受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄することができます(民法第986条第1項)。
③包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有しますので、当然遺産分割協議に参加することができます。これに対して、特定受遺者は、遺産分割協議に参加できません。
これらの違いを考慮して、遺言書の内容、書き方を決定する必要があります。
-
6-17 遺言があるかどうかは、どのように探したらよいでしょうか?
-
公正証書遺言については、相続人は、最寄りの公証役場に出向いて、遺言検索を行うことができます(遺言検索は無料です。閲覧は1回200円、謄本は1枚250円です。閲覧・謄写は遺言書を作成した公証役場においてのみ可能です。)。
※遺言検索をするには、遺言者の死亡の事実及び請求手続を行う者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等、本人確認書類(印鑑証明書及び実印)が必要になります。
また、法務局に保管する自筆遺言証書については、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局において、保管されている遺言書があるかどうかの確認をすることができます(遺言書保管事実証明書の請求は1通につき800円、遺言書情報証明書の請求は1通につき1,400円必要です。全国どこの法務局でも交付の請求をすることが可能です。)。
※「遺言書証明情報」の交付請求をするには、遺言者の出生時から死亡時までの戸籍謄本すべて、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票の写し(作成後3か月以内のもの)及び本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要になります(戸籍謄本及び住民票については、住所の記載のある「法定相続情報一覧図」でも可能です。)。
-
6-18 遺言書が見つかった場合にはどう対応すればよいでしょうか?
-
遺言書が見つかった場合には、その遺言書が、自筆遺言証書であるのか、法務局保管の自筆遺言証書であるのか、公正証書遺言であるのかによって、その後の対応が異なります。
1 自筆遺言証書の場合
速やかに家庭裁判所において検認手続を行います。家庭裁判所の検認がされた後に遺言執行を行うことができます。遺言書に遺言執行者の指定がない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てます。
2 法務局保管の自筆証書遺言の場合
家庭裁判所での検認手続は不要です。直ちに遺言書保管所(法務局)において「遺言書情報証明書」を取得します。遺言書に遺言執行者が定めてあれば、直ちに遺言の内容に従って遺言の執行ができます。
3 公正証書遺言の場合
家庭裁判所での検認手続は不要です。通常公正証書遺言には遺言執行者が定めてありますので、直ちに遺言の内容に従って遺言の執行ができます。
このように遺言の執行(相続手続)のことを考えると、遺言書は公正証書遺言かそれとも法務局保管の自筆証書遺言が良いでしょう。
-
6-19 認知症の場合、遺言書を作成することはできますか?
-
判断能力(意思能力)のない者は、契約や遺言をすることができません(民法第3条の2)。
認知症といっても、本人の判断能力のレベルは様々であり、まだら認知症といって、その日の天候や時間帯によって差が生じることもあります。
認知症といっても、すべての法律行為(契約や遺言など)が一切制限されるというものではなく、具体的事実の中で、本人がその状況を把握(判断能力がある状況)した上で意思表示を行ったのであれば、その意思表示は当然に有効となります。
したがって、認知症であるということをもって、遺言が直ちに無効になるとは限りません。
しかしながら、事後の紛争を防止するために、客観的な証拠を残すという観点からすると、できれば医師の診断書を取得した上で、公証人が本人の意思確認を行う公正証書遺言によって作成した方がよいといえます。
-
6-20 成年被後見人は遺言書を作成することができますか?
-
成年被後見人であっても、事理弁識能力(判断能力)を一時回復した時において、医師2人以上の立会いがあれば遺言書を作成することができます(民法第973条第1項)。
この場合、立会いをした医師は、「遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった。」旨を遺言書に記載して、署名捺印をする必要があります。
このように、法律上は、一定の要件の下であれば、成年被後見人であっても遺言書の作成は可能であるとなっておりますが、実際には、事理弁識能力(判断能力)が明らかに回復したといえる状況にないと、遺言書の作成は困難ではないかと考えられます。
したがって、できればしっかりとした判断能力があるうちに(ちなみに、65歳以上の5人に1人、80歳以上では4人に1人、85歳以上では2人に1人が認知症に罹るといわれています。)、遺言書を作成した方がよいでしょう。
-
6-21 遺言書の有効性を争う方法は?
-
遺言書が無効であることを争うためには、遺言書の有効性を争う者が、地方裁判所に対して、遺言書無効確認の訴えを提起する必要があります。
遺言書を無効であると主張する理由としては、①遺言書が法律の形式に反していること、②遺言者は、遺言書作成当時、既に判断能力(遺言能力)を失っていたこと、の2つが考えられます。
このような遺言書無効確認訴訟に備えておくためには、次の方法が考えられます。
①の遺言書の形式が法律に則って作成されているという点については、公証役場で作成する公正証書であればほとんど問題になりません。これに対して、自筆証書遺言については、専門家によるサポートがなしに自分自身で作成するとすると無効になる可能性があるかもしれません。
②の遺言書作成当時に判断能力があったことを証明する方法としては、医者の診断書を残しておく方法があります。この点、公正証書遺言であれば、公証人が本人の状態をか観察・確認し、判断能力に問題がないと確認して初めて遺言書を作成しますので、遺言書作成当時には判断能力があったと認められて有効な遺言書であると判断される可能性が高いといえます。
費用や手間の問題もありますが、後日相続人間で遺言書の効力が争われる可能性が高い場合には、やはり公正証書遺言を作成しておくべきでしょう。
-
7-1 遺産分割とは、どのようなものでしょうか?
-
相続人が複数いる場合には、被相続人の死亡によって、遺産は相続分に応じて共有状態になりますが、これはあくまでも一時的・暫定的なものにすぎません。最終的には、相続人全員で話うことにより、被相続人の遺産をどのように分けるかを具体的に決めることになります。これを遺産分割協議といいます。
相続人間で遺産分割協議が成立した場合には、速やかに「遺産分割協議書」を作成し、各相続人が署名と実印での捺印を行います。併せて各相続人の印鑑証明書を用意します。作成した「遺産分割協議書」は、各相続人が1通ずつ保管します。
なお、「遺産分割協議書」は、できれば税理士、行政書士、司法書士などの専門家に依頼して作成してもらった方が良いでしょう。遺産分割の仕方や協議書の書き方によって、相続税の課税関係が異なることもありますので、相続税の節税を考慮するならば、事前に税理士に内容を確認してもらった方が良いでしょう。
不動産の名義変更(相続登記)をする場合や預金の払戻・解約をする場合には、この遺産分割協議書と各相続人の印鑑証明書にを法務局や金融機関に提出して行うことになります。
-
7-2 遺産分割の方法には、どのようなものがありますか?
-
遺産分割の方法には、次の3つがあります。
1 現物分割・・・個々の財産をそのまま分ける方法になります。
2 代償分割・・・特定の相続人が財産を多く取得する代わりに、他の相続人に対して金銭を支払う方法になります。
3 換価分割・・・相続した不動産などを売却してその売却代金(金銭)を分ける方法になります。
現金や預貯金は、現物分割ができますが、不動産は多数の物件があれば現物分割も可能でしょうが、自宅しかないといった場合には、代償分割の方法を取ることが考えられます。また、相続人全員が不動産はいらないので現金がほしいといった場合には、換価分割の方法を取ることもあります。最近は、相続人間で平等に分ける意識も高く、核家族化で親と別居して自分の自宅を所有するケースが多いので、換価分割を選択するケースが増えています。
-
7-3 被相続人の遺言書が存在していた場合、 遺言書の内容と異なる遺産分割協議書は作成することができますか?
-
被相続人の遺言書が存在していたとしても、相続人間で合意をすれば、遺言書と異なる内容の財産の分け方を決めても構いません(民法第907条参照)。また、相続人間で合意するならば、民法の定める法定相続分と異なる割合での遺産分割となっても構いません。
ただし、以下の①から④の条件を満たす必要があります。
①被相続人が、遺言で遺産分割協議を禁止していないこと
②相続人全員が、遺言の存在と内容を知った上で、遺言と異なる遺産分割協議をしていること
③相続人以外に受遺者がいる場合には、当該受遺者が同意していること
④遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意があること
このように、相続人全員で遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行った場合の課税関係の問題については、受遺者が遺贈を事実上放棄して、共同相続人間で遺産分割をしたものとみますので、贈与税の課税の問題は生じません(国税庁・質疑応答事例参照)。
なお、特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」旨と記載された遺言(特定財産承継遺言)については、「特段の事情がない限り、相続開始と同時に、何らの手続を要しないで、直ちに当該資産が当該相続人に承継されるので、遺産分割の余地はない。」(最高裁平成3年4月19日判決)と解されていますので、これに該当するケースでは遺産分割ができないと考えられます。
-
7-4 遺産分割協議書に署名・押印は?
-
「遺産分割協議書」を作成するに際して、氏名の記載と押印する印鑑については、記名・押印(認印可)となっています。特段、自書による署名、実印での押印は求められていません。
ただし、遺産分割が紛糾していた場合など、後日、遺産分割協議書の有効性を巡って紛争が生じる可能性があるときには、やはり自書による署名及び実印での押印を求めておく方が良いでしょう。
なお、不動産登記(相続登記)については、自書を求める規定がありませんので、記名・実印での押印(印鑑証明書添付)でも差し支えないとされています。相続登記に使用する印鑑証明書については、相続発生後に発行されたものであればよく、有効期限はありません。
これに対して、預貯金の解約手続で金融機関に提出する印鑑証明書については、一般に発行から6か月以内のものであることを求められることが多いようです。
-
7-5 遺産分割協議書の形式として、同一内容の遺産分割協議書を相続人の人数分を作成し、各相続人が別々に署名押印しているような場合は、遺産分割協議書として有効でしょうか?
-
「遺産分割協議書」は、相続人全員の合意があれば有効に成立します。できれば、1通の「遺産分割協議書」に相続人全員が署名押印していることが望ましいですが、一部の相続人が遠方や海外にいる場合には、1通の「遺産分割協議書」を郵送により回付して、順次署名押印を求めていくとなると、非常に時間がかかったり、場合によっては途中で破棄されたりする危険性もあります。
このような場合には、同一内容の「遺産分割協議書」(「遺産分割協議証明書」ということもあります。)を相続人分の人数分作成して、各相続人ごとに郵送でやり取りを行い、最終的には相続人全員分の「遺産分割協議書」(相続人が署名押印したもの)を合綴することにより、相続人全員の合意があることが確認できますので、これをもって有効に成立した遺産分割協議書として取り扱うことができます。
-
7-6 相続人の中に未成年者がいる場合、遺産分割はどうすればよいでしょうか?
-
共同相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者を遺産分割の当事者として遺産分割協議を行うことはできません。
なぜなら未成年者が法律行為をするには、法定代理人(親権者)の同意を得ることが要件とされていますが、遺産分割については、親権者と未成年(子)との間で利益相反行為に当たることから、親権者は親権を行使(同意)することができないからです。
このような場合には、未成年者に特別代理人を選任して、その特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加する必要があります。
なお、特別代理人の選任は、未成年者の親権者が、家庭裁判所に対して選任の申立てをすることによって家庭裁判所の審判によって行います。
※令和4年4月1日以降は、成年に達する年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
-
7-7 海外居住者がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいでしょうか?
-
相続人のうちに海外居住者がいる場合、その者は「印鑑証明書」を取得することができませんので、そのままでは「遺産分割協議書」に「印鑑証明書」を添付することができません。
このような場合、日本の「印鑑証明書」の代わりに、在外公館(外国にある日本領事館、総領事館)に出向いて、領事の面前で遺産分割協議書に署名(サイン)を行い、遺産分割協議書に相続人が署名した旨の証明(サイン証明)をもらい、この「サイン証明書」を遺産分割協議書に添付する方法があります。
また、海外居住者が不動産を相続した場合には、不動産登記の登記申請に必要な「住民票写し」の代わりとして、住所を証明する書類として在外公館等で「在留証明書」を発行してもらい、これを添付することになります。
なお、このような場合において、公正証書遺言書が作成されており、かつ遺言書の中で遺言執行者が定められていれば、遺言執行者は相続財産の管理その他遺言尾執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しておりますので、海外居住者に係る上記のような面倒な手続は一切不要となります。
推定相続人の中に、海外居住者がいる場合には、遺産分割手続で苦労しないためにも、ぜひとも公正証書遺言を作成しておくことをおススメいたします。
-
7-8 相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいでしょうか?
-
相続人の中に行方不明者がいる場合には、行方不明の者を除いて遺産分割協議をすることができません。
このような場合には、他の相続人は、家庭裁判所に対して、不在者管理人の選任申立てを行うことになります。
遺産分割協議は、家庭裁判所が選任した不在者管理人を含めたところで分割協議を行うことになります。
このケースも、公正証書遺言(遺言執行者の指定も行う。)を作成しておけば、時間も費用もかからずに、速やかに相続手続ができます。
-
7-9 相続人の中に成年被後見人がいる場合、遺産分割協議はどうすればよいでしょうか?
-
相続人の中に成年被後見人がいる場合には、家庭裁判所によって選任された成年後見人が本人に代わって遺産分割協議を行います。
成年後見人を選任するには、時間も費用もかかりますので、すぐに遺産分割協議を行うことはできません。また、成年後見人は、遺産分割協議において法定相続分を確保するようにしますので、相続人の思うような遺産分割をすることもできません。
ただし、既に法定後見人が選任されている場合であっても、例えば、共同相続人の中の一人である母親が認知症のために長男が成年被後見人に選任されているケースでは、成年後見人の長男が、成年被後見人である母親を代理することは利益相反行為に該当しますので、長男は母親を代理して遺産分割協議を行うことはできませんので注意が必要です。
このような場合には、家庭裁判所に対して、特別代理人の選任の申立てを行い、その特別代理人を交えて遺産分割協議を行うことになります。なお、後見監督人が選任されている場合は、その後見監督人が、成年被後見人の母親の代理人として遺産分割協議に参加しますので、この場合は特別代理人の選任は不要となります。
-
7-10 遺産分割の方法として、換価分割や代償分割をする場合に気をつけることはありますか?
-
換価分割をする場合、実務上、相続人の一人が単独名義で相続財産を取得して、当該相続人が代表して不動産の売却を進めることがあります。このような場合、遺産分割協議書の記載の仕方について気をつけないと、場合によっては、贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。
そこで、贈与税の課税の問題が生じないようにするためには、遺産分割協議書の記載から、相続人のうちの一人の名義にしたことが、単に換価のための便宜のものであることが分かり、しかもその換価代金が遺産分割協議の内容に従って実際に分配されることが必要になります。このようにすれば、贈与税の課税の問題は生じません(国税庁質疑応答事例「遺産の換価分割のための相続登記と贈与税」参照)。
したがって、換価分割をする場合は、例えば、次のように記載することになります。
「相続人○○は、相続人を代表して次の不動産(省略)を売却して換価し、売却代金から相続登記費用、遺産承継手続費用、不動産仲介手数料、境界確定費用及び測量費用、収入印紙ほか、相続手続及び売却手続の要する一切の費用並びに売却手続が完了するまでの間に要する一切の費用の合計額を控除した残額を、相続人全員で法定相続分の割合に従って按分し、各相続人に対して分配する。ただし、端数が生じる場合は、相続人〇〇が取得する。」
また、代償分割の場合は、相続税の計算において、代償金を支払う相続人は、債務控除の金額として代償金を計上し、一方、代償金を受け取る相続人は、代償金を取得した相続財産として計上して、それぞれの相続税の計算をすることになります。
したがって、代償分割をする場合は、代償金の支払関係が明確となるように、例えば、次のように記載することになります。
「1 相続人○○は、次の不動産(省略)を取得する。
2 相続人〇〇は、1の不動産を取得する代償として、相続人△△に対して、金○○万円を支払うこととし、これを令和〇年〇 月〇日限り、相続人△△が指定する預金口座に振込みをする方法により支払う。なお、振込手数料は、相続人〇〇の負担とする。」
このように、遺産分割は、単に遺産をどのように分けるかというだけではなく、できれば相続税や贈与税の課税関係にも遺産分割の内容を決めることがよいでしょう。
-
7-11 遺産分割の方法として、代償分割の方法によることとしましたが、代償金の支払に代えて、相続人固有の不動産を交付(所有権移転登記)することは可能でしょうか?
-
遺産分割の方法の中の代償分割を選択した場合に、代償金の支払に代えて、相続人固有の不動産を交付(所有権移転登記)することも可能です。
なお、この場合には、代償金の支払に代えて自己の不動産を交付することになりますので、税法的には、代償金の支払をした者は、負担することとなった代償金債務を履行するために自己が所有する不動産を移転したことになります。したがって、履行時における時価により自己の所有不動産を譲渡したことになりますので、譲渡所得税が課税されることになります。
このような結果になると、相続税のほかに譲渡所得税の負担も生じますので、望ましい遺産分割の姿とはいえません。
これを避けるためには、遺産の大半を相続する推定相続人に対して、生前に代償金の支払資金を手当てしてあげることが必要になります。例えば、生命保険契約に加入して、死亡保険金の受取人をその推定相続人としておけば、死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産となりますので、別腹で代償金の支払資金を用意することができます。ぜひとも生前に検討しておきたいものです。
-
7-12 相続人が遺産分割協議を行う場合に、気をつけた方がよいことはありますか?
-
遺産分割協議をするに当たっては、場合によっては、相続人間で遺産を平等に分けるということを考えすぎないことが大切かもしれません。
例えば、各相続人によって、子供の教育費でお金が欲しいとか、住む家が欲しいので実家の家が欲しいとか、事業を引き継ぐので事業用財産や会社の株式がほしいとか、いろいろと家庭事情が異なるかと思います。
各相続人が、余りにも法定相続分にこだわり、各自が平等の権利を主張しますと、
①せっかくある自宅を売却して金銭で分けることになり、その結果残された妻の生活の本拠がなくなってしまった
②事業用の資産を売却して金銭で分配することになり、結果的に事業を廃業することになった
③とりあえず法定相続分で不動産や株式を共有したことにより、その後に相続人間での管理・処分の話合いがまとまらなくて不動産を処分することや会社の経営方針を決めることができなくなった
といったように、非常に困った事態に陥ることもあります。
特に、不動産を共有にすると、その後にそのうちの一人の相続人が亡くなって更に相続が発生すると、関係する相続人の数が増えて遺産分割協議がまとまらないとか、あるいは、共有持分を有する相続人が自己の持分を他人に売却してしまうとか、いろいろな問題が生じます。
不動産を共有とした場合には、その物件を賃貸するとか、修繕するとか、処分するとかの際には、共有者の全員又は持分の過半数の同意が必要となりますので、不動産を共有とするのは絶対に避ける必要があります。
例外的に、不動産を共有にした方が良いケースとしては、例えば、空き家となった自宅について、相続人全員が直ちに不動産を売却することで合意している場合です。この場合には、所得税の譲渡所得の計算上、各相続人が空き家譲渡の特例として3,000万円の特別控除をそれぞれ受けることができますので、トータルでの特別控除額が一人で相続したケースに比べて多くなり、結果的に全体での所得税の納税額が少なくなります。
-
7-13 「遺産分割協議書」には、預金や不動産についてどのように記載すればよいでしょうか?
-
不動産については、法務局で入手した「登記事項証明書」に記載のとおりにそのまま記載します。
例えば、土地については、所在、地番、地目、地積をそのまま記載します。建物については、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、附属建物の表示も同様に、そのまま記載します。
また、預金については、金融機関名、支店名、預金の種別、口座番号を記載して預金を特定します。なお、預金残高の記載については、その後の手続のことを考えますと(万一遺産分割協議書の記載金額と相続開始時の預金残高が一致しない場合や預金利息、入出金などで預金残高の増減があった場合にスムーズに相続手続が行えないことがあり得ます。)、具体的な金額は記載しない方がよいでしょう。
-
7-14 「遺産分割協議書」は、1通しか作成できませんか?
預金解約のため、不動産登記のためなど、用途に合わせて複数作成することはできますか?
-
「遺産分割協議書」は、通常は、相続財産全部についての遺産分割の内容を定めた内容のものを、相続人の数に応じた部数を作成することが多いようです。このほかに、役所等の手続(相続税の申告、不動産の相続登記、預金の解約など)に必要な部数を別途作成することもあります。
ただし、相続人の中には、預金の解約手続を行うに当たって、預金以外の財産も記載した全財産の分割方法について定めた「遺産分割協議書」を金融機関に対して提示することに抵抗がある方もいます。
このような場合には、預金解約のためには、預金についてだけを定めた「遺産分割協議書」を作成したり、不動産の相続登記のために不動産についてだけ定めた「遺産分割協議書」を作成したり、それぞれの用途ごとに「遺産分割協議書」を作成して各々の相続手続をすることもできます。
-
7-15 遺産分割協議書において、相続人のうちの一人が金融機関の借入金債務を承継すると定めることができますか?
-
被相続人の債務(金融機関の借入金など)については、法律上当然に分割されて法定相続分で各相続人に承継されることになります(判例の考え方)。
したがって、例えば「遺産分割協議書」において、特定の相続人が被相続人の債務(金融機関の借入金)を引き継ぐ旨の合意をした場合には、相続人間ではその合意内容は有効であるとしても、その合意内容(相続人の一人が引き継ぐ)をもって債権者である金融機関に対して対抗することはできません。
ただし、債権者である金融機関の同意があれば、そのような合意内容(相続人の一人が引き継ぐ)も債権者に対抗できることになります。
実務的には、予め遺産分割協議書の案を金融機関に持参して、合意内容を説明しておき、事前に金融機関の了解を取っておくほうがよいでしょう(金融機関では免責的債務引受契約を締結してもらいます。)。
-
7-15 既に遺産分割協議が成立している場合において、遺産分割のやり直しはできますか?
-
既に遺産分割が成立している場合においても、当初の遺産分割を合意解除することによって、遺産分割協議をやり直すことは可能です。
ただし、税法上は、当初の遺産分割協議と新たな遺産分割協議書の内容などによって、相続人間で財産の贈与や譲渡があったとみられることもありますので、贈与税や譲渡所得税が課税されるリスクがありますので注意を要します。
-
7-16 遺産分割協議が成立しないときのデメリットは?
-
遺産分割協議が成立しない場合には、不動産についての相続登記を行うことができませんし、また、預貯金の解約・払戻手続もすることができませんので、葬儀代、病院代の支払、生活費の手当などに支障が生じることになります。
このほかに、相続税の申告(相続税法)との関係になりますが、例えば、相続人間に争いがあって、遺産分割が申告期限までに成立しなかった場合には、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、農地等についての相続税の納税の猶予、延納・物納の申請の適用を受けることができません。
したがって、相続税の申告期限までに遺産分割が成立しないと、これらの相続税法上の特例を受けることができませんので、特例を適用がないものとして計算した相続税額を納付する必要がありますので、特例を適用して計算した相続税額よりもはるかに多額の相続税を一度に納付しなければならなくなります。
相続人間で円満に遺産分割協議ができればよいですが、相続争いになる可能性がある場合には、遺言書を作成しておくことで速やかな相続手続ができますので、一度検討してください。
-
8-1 相続税がかかるかどうかは、どのようにして確認したらよいでしょうか?
-
相続税には、基礎控除といって、そもそも相続税がかからない課税最低限のラインがあります。これは、3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除の金額で計算します。
相続税がかかるかどうかを大雑把に計算するだけでしたら、次により計算してみるとよいでしょう。
遺産総額は、①預貯金は死亡日の預金残高、②株式は死亡日の最終取引価額、③建物は市町村の固定資産税評価額、④土地は国税庁の発表する路線価の金額×面積で算出した金額(路線価のない地域については、固定資産税評価額×倍率)を合計して計算します。
一方、債務は、葬式費用や未払いの病院代、公共料金のほか、金融機関などの借入金の死亡日現在の残高を合計して計算します。
遺産総額から債務の金額を控除して、差し引きの課税遺産額を計算することになります。
ここから、先に計算した基礎控除額を差し引いた金額が、相続税の課税対象になる課税遺産額になります。
ザックリと相続税がかかるかどうか計算するだけであれば、国税庁ホームページの「申告要否の簡易判定シート」を活用するのが便利です。
-
8-2 簡易判定で相続税を納付する必要があるとなった場合、納付する資金はどのように手当てすればよいでしょうか?
-
現時点で、ご自身の財産と配偶者や子供の財産の合計金額から見て、仮計算した相続税を納付するだけの預貯金や株式・投資信託があれば問題ありません。
しかし、通常、相続人が相続税を納付できるだけの固有の預貯金などを保有しているケースは余りないと思います。
また、推定被相続人の財産を見ると、相続財産としては預貯金が少なく、主な財産は自宅しかないといった場合には、最悪の場合には自宅を処分して相続税を納付するしかないこともあります。
どうしても相続税を一括で納付する資金を手当てできない場合には、相続税を分割して納付する方法(延納)といった方法もありますが、金融機関の金利よりも高い利子税がかかります。
なお、納付資金の手当てを事前に行っておく方法としては、相続人を死亡保険金の受取人とする生命保険契約を締結することが一番有効な方法になります。しかも、死亡生命保険金には、相続税の非課税(法定相続人1人当たり500万円まで)の規定もありますので、できれば生命保険契約に加入する方法は積極的に利用したいものです。
-
9-1 万一、認知症になったり、あるいは、脳梗塞で突然倒れた場合は、どうなりますか?
-
認知症になったり、あるいは、脳梗塞で突然倒れて寝たきりになった場合には、たとえ家族であっても、預貯金の引出はできませんので、病院代などの支払もできなくなります。
当然、自宅などの不動産を売却することや賃貸に出すこともできません。
また、認知症になるとリホーム詐欺などにも遭いやすいのですが、本人に代わって契約を取り消すことも難しいかもしれません。
このような場合には、法定後見制度を利用するしかなく、家庭裁判所に法定後見人の選任申立てを行い、家庭裁判所が選任した法定後見人が本人に代わって財産管理を行うことになります。家族にとっては、本人の財産を自由に使うことはできませんし、本人が亡くなるまで法定後見人の報酬を本人の財産の中から支払っていかなければなりません。このように、法定後見人制度は非常にデメリットも多い制度です。
この法定後見人の利用を避ける方法としては、事前(健常者のうち)に家族の中から万一の場合に頼める人を任意後見人に選任しておく任意後見契約を公正証書で作成する方法があります。財産管理委任契約兼任意後見契約を締結しておけば、判断能力はあるけれども足腰が悪いといった段階から、家族に財産管理を任せることができます。
-
9-2 家庭裁判所を通じて、法定後見人を選任すると、どうなりますか?
-
法定後見人の選任申立てを行うと、本人の財産管理及び身上配慮を行うために、家庭裁判所が法定後見人を選任することになります。法定後見人には、3種類あり、本人の事理弁識能力(判断能力)の程度により、後見(事理弁識能力なし)、保佐(事理弁識能力が著しく不十分)、補助(事理弁識能力が不十分)に分かれています。
財産管理が主目的の場合には、法定後見人には、通常、法律の専門家(弁護士や司法書士など)が選任されます。なお、最近では、家族が法定後見人に選任されるケースは非常に少ないようです(20%以下?)。
法定後見人は、病院代の支払のために預貯金を引き出して支払うことはできますが、自宅などの不動産を処分することは基本的にはできません(家庭裁判所の許可が必要)。
また、法定後見人には、毎月の財産管理の報酬として、本人が死亡するまでの間、最低でも毎月2、3万円程度(財産額の多寡によって増額します。)支払う必要があります。
いったん法定後見人が選任されると、その法定後見人が気に入らなくても、申立てを取り下げることもできません。
法定後見人が選任された場合には、もはや任意後見契約を結ぶことはできません。
このようなことを考えると、認知症に罹った場合に法定後見人を選任することがよいかどうかわかりません。ただし、本人に判断能力がないとなると、法定後見人を選任するしかありません。
-
9-3 認知症に備えて、あらかじめ任意後見契約を結んでおくと、どうなりますか?
-
元気で健康(判断能力が十分)なうちに、任意後見契約を公正証書で作成しておくと、万一の場合に家族は困りません。
任意後見人は、本人に代わって、財産管理事務(預貯金や不動産などの管理・処分など)や身上保護事務(生活・医療の契約や介護施設の入所契約など)の2つを行います。
しかしながら、任意後見人であっても、医療行為の同意(手術の同意や延命治療は要らないなど)や死後の事務(葬式、埋葬など)はできません。
これらについての希望を叶えるためには、別途、「尊厳死宣言書」や「死後事務委任契約」を結んでおくことが必要です。
任意後見人になる人は、自分で選ぶことができますので、家族(長男など)を後見人に選任することもできます。なお、通常は、家族が任意後見人になる場合には、報酬は無報酬とするのが一般的です。
任意後見契約については、戸籍には記載されませんのでプライバシーも守られます。
任意後見人は、法務局で後見登記がされますが、登記情報を入手できる者は任意後見人などに限られていますので、プライバシーは保護されています。
-
9-4 任意後見契約には、どのような種類がありますか?
-
将来型(将来判断能力が低下した場合に備えるタイプ)、移行型(任意後見契約を結ぶとともに、任意代理契約を結び、判断能力が低下する事前の段階から財産管理の委任をできるようにするタイプ)、即効型(判断能力が低下しつつある段階で、直ちに後見契約を開始するタイプ)の3種類があります。
このうち移行型は、判断能力は十分にあるが足腰が弱って歩けなくなる段階から、本人に代わって財産管理を行うことができて、万一認知症になった場合には、家庭裁判所に後見人の選任申立てを行い、そのまま任意後見人として財産管理と身上保護を行うことができるというように早い段階から関与できるというメリットがあります。
認知症に備えておきたい方は、「遺言書」を作成することと併せて、「財産管理委任契約及び任意後見契約」を公正証書で締結しておくことがベストといえます。
-
10-1 死後事務委任契約とは、どのようなものですか?
-
死亡直後の事務については、役所への手続、葬式、供養、入院代の精算、運転免許証の返納、遺品の整理・処分など様々なものがあります。家族がいる場合は、通常家族がこれらの事務を行いますので特に問題になりませんが、身寄りがなく相続人が全くいないおひとり様については、このような死亡直後の事務は、市町村が行ってくれる火葬埋葬などを除き、誰も行ってくれません。
また、葬式の方法についても、直葬、戒名は要らない、お墓をつくらない海での散骨、樹木葬といった希望のある方もいるでしょうが、生前に何らかの手当てをしないとその思いも叶いません。
そのような場合に備えて、自分の死後の事務処理や死後の希望を叶えてもらうために、予め信頼できる人を受任者として定めて、受任者との間で「死後事務委任契約」を締結する方法があります。
このような死後事務委任契約については、法律上の規定はありませんが、民法に定める委任契約の一つとして、委任者と受任者との間で「死後事務委任契約」を締結することができます。
できれば多少費用はかかりますが、法律の専門家に原案の作成を依頼した上で、法律上完全な証明力のある公正証書で作成することが望ましいかもしれません。
-
10ー2 尊厳死宣言書とは、何でしょうか?
-
がんで回復見込みのない場合や交通事故で回復見込みのない脳死状態になった場合に、延命治療を望まないという人は多いかもしれません。しかし、延命治療については、本人が明確な意思表示ができないケースでは、自己決定権の尊重という観点から、本人に代わって家族が延命治療の中止を決定することはできません。このような場合、家族が医師に延命治療をしないように頼んでも、医師は刑事責任・民事責任を問われる可能性がありますので、延命治療を取りやめることはありません。
このような場合に備えて、延命治療について、あらかじめ公正証書で「尊厳死宣言書」を作成しておくことによって、万一回復見込みのない状態になった場合においても、本人が延命治療を望まないという意思を明確にすることができます。
尊厳死宣言書を作成した場合には、本人が元気なうちに家族に対して尊厳死宣言書の存在を知らせておくことが必要です。
-
11ー1 年金受給者が死亡した場合、どのような手続が必要になりますか?
-
年金を受給している者が死亡した場合には、年金を受ける権利(年金受給権)がなくなります。
厚生年金の場合は、年金事務所又は年金相談センターに対して、死亡日から10日以内に「受給者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
国民年金の場合は、市町村に対して、死亡日から14日以内に「受給者死亡届(報告書)」を提出する必要があります。
届出が遅れると、後から受領した年金を返金することになったりしますし、場合によっては不正受給として疑われるといったことにもなりかねませんので、注意してください。
-
11ー2 未支給年金とは、何でしょうか?
-
亡くなった方が、老齢基礎(厚生)年金、障害基礎(厚生)年金、遺族基礎(厚生)年金、寡婦年金などの年金を受け取っていた場合には、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族に対して、未払いの年金が支給されます。これを未支給年金といいます。
未支給年金を受け取ることができる遺族は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦これ以外の3親等内の親族であり、支給を受ける順位は、①~⑦の順となります。
年金は、権利が発生した月の翌月から死亡した月まで支給されることになっており、支払月前の2か月分を偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に支払うことになっています。例えば、8月20日に死亡した場合は、直前の6月及び7月分までの2か月分を8月に支払っていますので、死亡した月の8月分の年金が未支給となっているということになります。
未支給年金の請求については、年金事務所(国民年金のみの場合は市町村役場でも可)に対して手続を行いますが、請求から5~6ヶ月後に入金されます。
支給申請書の添付書類としては、①年金証書(なければ「受給者死亡届(報告書)」を提出)、②戸籍謄本又は法定相続情報一覧図(死亡した受給権者と請求人との身分関係を明らかにするため)、③住民票除票(受給権者の死亡の事実を明らかにするため)、④世帯全員の住民票(生計同一関係を明らかにするため)、⑤預金通帳の写し(振込口座の確認のため)が必要になります(請求者のマイナンバーカードを記入した場合は、③及び④は添付省略可能です。)。
なお、未支給年金については、遺族が相続開始後に受け取るものですから、相続財産には当たりませんので、相続税の課税対象にはなりませんが、所得税法上の一時所得として課税対象になります(所得税法基本通達34-2)。
-
11ー3 老齢厚生年金を受給している夫が死亡した場合、妻には遺族厚生年金が支給されますか?
-
遺族年金は、亡くなった人の家族の生活保障を目的に支給されるもので、国民年金から支給される遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金と、厚生年金から支給される遺族厚生年金とがあります。
遺族年金を受給するためには、①死亡した人の要件、②受給対象者の要件(遺族の範囲)、③保険料納付要件の3つを満たさなければなりません。
遺族基礎年金は、18歳年度末までの子供(子供のいる配偶者)のための年金であり、寡婦年金や死亡一時金は、保険料掛け捨て防止のための年金となります。
一方、遺族厚生年金は、遺族の生活保障のための年金であり、例えば、老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合には、配偶者に対して、死亡した者が受給していた老齢厚生年金の4分の3相当額が支給されることになります(ただし、自身が受給している老齢年金との併給調整があります。)。
詳しい内容(受給要件や支給金額など)は、年金事務所に問い合わせる必要があります。
なお、年金は、すべて請求しないともらうことができませんので、ご注意ください。