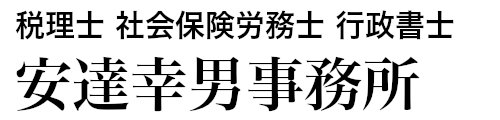(目次)
1 相続財産・債務の把握方法
2 タイムスケジュール
3 準確定申告
4 相続人、相続分、遺産分割
5 相続税の計算
6 名義預金
7 財産評価
8 贈与税
9 空き家の譲渡
10 相続税の節税対策
-
1ー1 相続税の申告が必要になりますが、相続財産はどのようにして把握すればよいでしょうか?
-
以下のものを手掛かりに相続財産の調査を進めましょう。
①預貯金は、キャッシュカードや「預金通帳」、銀行からの郵便物、公共料金の振替口座のハガキなど
②有価証券は、証券会社からの「取引通知書」又は「配当金支払通知書」、預金通帳への配当金の振込など
③不動産は、「登記済証」又は「登記識別情報」、「登記簿謄本」又は「登記事項証明書」の共同担保目録の記載、「売買契約書」や「贈与契約書」、市役所から送付される「固定資産税納税通知書」、市役所で「名寄帳」を入手する
④生命保険・損害保険は、「保険証書」、確定申告書の生命保険料控除・損害保険料控除の記載、生命保険会社・損害保険会社からのハガキ
⑤年金は、「年金手帳」、年金事務所からのハガキ
最近は、インターネットを使ったネットバンクやネット証券などもありますが、これらのデジタル遺産については、そもそもその存在自体を相続人が知らないことも多いようです。これを防止するには、エンディングノートなどにデジタル遺産の明細をメモしておくほか、アカウント、IDパスワードも併せてメモしておくことは必要です。
-
1-2 相続が発生した場合、債務はどのようして把握すればよいでしょうか?
-
借金については、借金の督促状が自宅に届いていないかどうかを確認します。
預貯金取引のある金融機関に対しては、借入金残高証明書の発行を請求して確認する方法もあります。
全く手掛かりがない場合は、信用情報機関(全銀行、CIC、JICC)に照会する方法もあります。
-
2-1 相続が発生した場合、税務関係の申告などのタイムスケジュールはどうなっていますか?
-
相続があった場合のタイムスケジュールは、次のとおりです。
速やかに 国民年金の受給手続の停止
⇓
14日以内 後期高齢者医療被保険者証・介護保険被保険者証の返却と資格喪失手続
世帯主の変更など
⇓
なるべく早期に 公共料金・電話等の支払方法の変更・解約
高額医療費の請求
未支給年金の請求、遺族年金の受給手続
「遺言書」の有無の確認
戸籍等の収集(相続人の確定)
「財産・債務の目録」作成
⇓
3か月以内 相続放棄の申述申立て(家庭裁判所へ)
⇓
4か月以内 被相続人に係る「準確定申告書」の提出(所得税、消費税)
事業を承継する相続人がいる場合は、開業届など各種届出の提出
⇓
適宜の時期に 遺産分割協議(遺産分割協議書への署名押印)
不動産などの名義変更
⇓
10か月以内 「相続税の申告書」の提出
以上のとおり、相続開始後は非常のやることが多い上、期限があるものも多いので注意が必要です。
やること一覧表のリスト(期限順)を作成し、チェックしていくと、手続漏れもなくよいでしょう。
-
3-1 準確定申告とは何でしょうか?
-
被相続人が、事業を営んでいた場合、不動産賃貸業を営んでいた場合については、被相続人に係る死亡した年の1月1日から死亡した日までの間の所得について、相続人が所得税の確定申告を行う必要があります(これを準確定申告」といいます。)。
また、高額な医療費を支払っていた場合や各種控除を受けることができる場合については、準確定申告をすることにより税金が還付となりますので、相続人が所得税の還付申告を行うことになります。
準確定申告の提出期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から4か月以内に相続人が行うことになっています。なお、還付申告については、翌年1月1日から5年以内となります。
さらに、被相続人の基準期間(相続のあった日の前々年)における課税売上高が1,000万円を超える場合には、同様に、1月1日から死亡した日のまでの期間について、相続のあったことを知った日から4か月以内に、消費税の純確定申告が必要になります。
準確定申告書の作成については、死亡日から4箇月以内と非常に短いことに加えて、亡くなった被相続人の帳簿や領収証書などの保存状態が悪いと、決算を組んで申告書を作成をすることは容易ではありません。
-
3-2 準確定申告において、不動産所得の計算上、相続開始から遺産分割成立までの間の賃料債権の帰属(未分割遺産から生ずる不動産所得は誰が申告すべきか)はどのようになるのでしょうか(未分割の不動産から生ずる不動産所得は誰が申告すべきか?)?
-
判例(最高裁平成17年9月8日判決)によると、相続財産について、遺産分割が成立していない場合、その相続財産は、各相続人の共有に帰属するものとなりますので、その不動産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分(法定相続分)に応じて帰属することになります。
したがって、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することになります。
なお、家賃地代の収入については、毎月末までに翌月分を支払うといった約定の場合には、月の途中に被相続人が死亡したとしても、月初から死亡日までの日割り計算をして収入に計上する必要はありません(当該月の家賃地代は相続人に帰属します。)。
-
3-3 準確定申告において、不動産所得の必要経費に算入する固定資産税は、どのように計算すれば様でしょうか?
-
準確定申告において、必要経費に算入できる固定資産税の金額は、相続開始日までに納付すべき税額が確定している金額となります。この場合、納付すべき税額が確定しているとは、具体的には、その年の納税通知書が相続開始前に被相続人に届いていることをいいます。逆に、納税通知書が被相続人に届いていなければ、被相続人の所得税の計算上必要経費に算入することができません。
さらに、納税通知書が被相続人に届いている場合、必要経費に算入する金額については、①通知された全額、②納期到来分、③納付済み分、のいずれを選択しても構いません。被相続人の所得税の計算上必要経費に算入した金額については、相続人の所得税の計算上は必要経費に算入できません。
-
3-4 相続により共有名義で不動産を取得している場合、所得税の青色申告特別控除(65万円)を受けるためには、どれだけのマンションの室数を所有していればよいでしょうか?
-
不動産所得について所得税の青色申告特別控除(65万円)を受けることができる事業的規模とは、5棟10室基準が一つの目安になります。
相続により共有名義で不動産を取得している場合には、各共同相続人が相続分に応じて申告することになりますが、その際の事業的規模の判定は、各自の法定相続分により按分した部屋数ではなく、全体の部屋数によって判定します。
-
3-5 不動産賃貸業を営んでいる納税者が死亡した場合、被相続人に係る税務署への届出書類には何がありますか?
-
不動産所得を生ずる事業を営んでいた納税者(青色申告)が死亡した場合、所轄の税務署に対しては、以下の届出書(被相続人に係るもの)を提出する必要があります。
①「個人事業の廃業届出」
②「所得税の青色申告の取りやめ届出書」
③「給与支払事務所の廃止届出書」
④「個人事業者の死亡届出書(消費税)」
-
3-6 不動産賃貸業を営んでいる納税者が死亡した場合、事業を相続した相続人は、所轄税務署に対してどのような届出書を提出すればよいでしょうか?
-
相続人は、所轄税務署に対して、以下の届出書(相続人に係るもの)を提出する必要があります。
①「個人事業の開業届出」
②「所得税の青色申告承認申請書」※必要に応じて
③「給与支払い事務所の開設届出書」※必要に応じて
④「所得税の減価償却費の償却方法の届出書」※必要に応じて
⑤消費税関係の届出書 ※必要に応じて
なお、複数の相続人いる場合、その後において遺産分割協議を行って、相続人のうちの一人が遺産分割によって賃貸不動産を相続したとしても、被相続人の死亡日から遺産分割成立日までの間は、各相続人が法定相続分に応じて不動産賃貸業を行っていたこと(賃料は法定相続分で各相続人に帰属します。)になります。
したがって、このような場合には、各相続人が、それぞれ「開業届」や「青色申告承認申請書」を提出しておいた方がよいでしょう。そうすることによって、各相続人が、それぞれ青色申告の特典(青色申告特別控除65万円など)を受けられますので、お得になります。
なお、開業届や青色申告承認申請書などの提出期限は、死亡後4か月以内となっており、被相続人に係る準確定申告書の提出期限と同じ期限となりますので、遺産分割協議が終わってからと考えていると、すぐに期限を過ぎてしまいますので注意が必要です。
-
4-1 相続が発生した場合、相続人は、誰がなりますか?
-
民法の規定(第887条から第890条)によると、相続人は、次の者がなります。
・配偶者(常に相続人になります。)※内縁の配偶者は、相続人になりません。
・配偶者と同順位で相続人となる者
(第一順位) 子(実子、養子を含みます。)
※子が既に死亡している場合は、孫が代襲相続人になります(再代襲相続もあります。)。
(第二順位) 直系尊属(父母、祖父母など) ※親等の近い者が優先します。
(第三順位) 兄弟姉妹
※兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(甥、姪)が代襲相続人になります。
※父母の一方を同じくする半血兄弟を含みます。
※同順位の相続人が複数いる場合には、それらの複数の相続人が共同相続人になります。
-
4-2 遺言書がない場合の法定相続分はどのようになりますか?
-
民法の規定(遺言がある場合は第902条、遺言がない場合は第900条によることになります。)によると、遺言がない場合には、法定相続分に従って相続することになります。
民法が定める法定相続分は、
①配偶者及び子が相続人である場合は、配偶者の相続分は2分の1、子の相続分は2分の1
②配偶者及び直系尊属(祖父母など)が相続人である場合は、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1
③配偶者及び兄弟姉妹が相続人である場合は、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1
となります。
なお、同順位の相続人が複数人いるときは、各自の相続分は相等しいものとなります。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
-
4-3 遺産分割を行う場合の留意点はどのようなものがありますか?
-
遺言書がない場合には、相続人間で相続財産の分割方法について協議をします。
遺産分割を行う場合、次の点に留意します。
①不動産はなるべく共有名義としないようにします。
共有名義不動産は、将来、売却や賃貸することが困難となります(共有者全員の同意や共有者の過半数の同意が必要となるためです。)。
②残された配偶者がいる場合には、配偶者の居住する自宅の確保や今後の生活費の手当を考えて、遺産分割協議を行います。
③相続税の申告期限までに遺産分割協議を成立するようにします。
相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議が成立しない場合には、相続税の申告の計算において、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などといった特典の適用ができませんので、(一旦は)多額の税金を支払うことになります。
④相続税の計算上土地の評価額が減額できる小規模宅地の特例については、適用要件を満たす相続人がその土地を相続する必要がありますので、遺産分割協議に当たってはこの点も考慮して行うとよいでしょう。
⑤各相続人が支払う相続税の納税資金の手当てを考慮して遺産分割の内容を決めるとよいでしょう。
仮に、自己資金での納税資金の手当てが困難な相続人が、他の相続人から納税資金をもらって納付すると、贈与税の課税問題が生じます。
⑥二次相続(夫婦の内の一人が死亡した後に、その後に残された他方配偶者が死亡すること)のことを考えると、一般的には、遺産総額を減らすために、現金・預貯金は消費してなくなりますので配偶者がこれを相続し、不動産は子供が取得するのがベターといわれています。
-
5-1 相続税の計算は、どのようにして計算するのでしょうか?
-
相続税の計算方法の概要は、次のとおりとなります。
①相続税が課税される財産について、遺産総額を計算します。
※死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を加算するとともに、非課税金額を除外します。
また、不動産評価に当たっては小規模宅地等の特例の適用をして評価額を調整します。
②葬式費用や債務の金額を計算します。
③遺産に係る基礎控除を計算します(基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数)。
④①の遺産総額から②の葬式費用及び債務を控除し、差引金額から③の基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
⑤課税遺産総額を各相続人が法定相続分で取得した者として各相続人の取得価額を計算します(仮計算)。
⑥各相続人の取得価額(仮計算)を基に、各人の相続税の算出税額を計算し、各人の算出税額を合計して、今回の相続における相続税の総額を計算します。
⑦相続税の総額を、各相続人の実際の取得価額により按分計算して、各相続人の納付すべき相続税額を計算します。
⑧相続又は遺贈により財産を取得した者が、被相続人の配偶者及び一親等の血族以外の者(孫養子など)であるときは、その相続人の相続税額に2割加算をします。
⑧配偶者税額軽減、未成年控除、障害者控除、相次相続控除、暦年贈与の贈与税額控除、相続時精算課税の贈与税額控除など、各種の控除額を控除して、各相続人ごとの納付税額を算出します。
-
5-2 相続税の計算で基礎控除とはどのようなものですか?
-
相続税には、基礎控除といって、この金額までの範囲内であれば相続税が課税されないというものがあります。
この基礎控除の金額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数により計算します。
なお、この場合の法定相続人とは、相続人の中に相続放棄をした者がいれば、相続放棄がなかったとした場合の法定相続人の数をいいます。また、民法上は、養子の数に制限はありませんので養子縁組によって何人でも法定相続人とすることができますが、相続税法上は、養子縁組によって法定相続人とすることができる養子の数は、実子がいるときは1人まで、実子がいないときは2人までに制限されています。
現在の基礎控除は、平成27年1月施行の相続税法の改正により、従来の金額を大幅に引き下げたもので、これにより、相続税の申告をする人が大幅に増加しました。
-
5-3 相続税の未成年者控除とは何でしょうか?
-
相続人の中に未成年者が含まれている場合、その者の納付すべき相続税額から、18歳に達するまで年10万円を差し引くことができます。なお、控除しきれない金額は、扶養義務者の相続税額から控除することができます。
※未成年者控除額=(18歳ー相続開始時の年齢)×10万円
(注)18歳に達するまでの年齢や1年未満の端数が出るときは、1年として計算します。
※2022年(令和4年)4月1日に、未成年者の年齢は20歳から引き下げられています。
なお、未成年者が相続人の場合には、遺産分割協議を行う際には注意が必要です。
未成年者と未成年者の親権者(親)とは、同じ相続人になりますので、親が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことは利益相反行為に該当しますので、親は未成年者の代理人となることができません。
この場合、家庭裁判所に対して、その未成年者のための特別代理人の選任の申立てをしなければならないことになっております。特別代理人を選任するには、費用と時間を要しますので、例えば、10か月以内の相続税の申告期限よりも少し先に成年になるような場合には、未成年者の子が成年になるのを待って遺産分割協議を行うのも一つの選択肢となります。
-
5-4 基礎控除の計算に当たって、第一順位の相続人が相続放棄した場合、どのような計算になりますか?
-
基礎控除の金額を計算する場合の「法定相続人の数」は、相続放棄がなかったとした場合の法定相続人の人数となります。
例えば、夫が死亡して、相続人は妻及び子2人のケース(被相続人の父母は既に死亡しているものとします。)において、第一順位の相続人である子2人が相続放棄を行ったために、次順位の被相続人の弟(1人)が相続人になったケースでは、法定相続人は妻と弟の2人になりますが、相続税法上の法定相続人の数は、妻と弟の2人となるのではなく、相続放棄がなかったものとした場合の法定相続人の人数となりますので、妻と子供2人の3人となります。
間違えやすい点ですので、注意が必要です。
-
5-5 相続放棄をした相続人が生命保険契約に基づく死亡保険金を受け取った場合、相続税法の非課税規定の適用はどのようになりますか?
-
相続放棄をした者は、相続人とはなりません。
ただし、被相続人が死亡した時に支払われる死亡保険金については、被相続人の本来の相続財産ではなく、受取人の固有の財産とされますので、相続放棄をした相続人であっても、死亡保険金を受け取ることができます。
なお、相続放棄をした者は、相続人ではないことから、相続税法上の生命保険金の非課税の規定(相続人1人当たり500万円)の適用はありません。また、相続放棄をした者は、債務控除についても適用がありません(ただし、相続放棄をした者が、。被相続人の葬式費用を負担した場合は、当該負担額は債務控除しても差し支えないことになっています。)。
-
5-6 相続税法上の非課税規定の適用のある生命保険にはどういうものが含まれますか?
-
被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金(被相続人の死亡に伴い支払われるものに限ります。)を取得した場合には、民法上は、本来死亡保険金については受取人固有の財産であって、相続財産にはならないとされています。しかしながら、民法上の相続又は遺贈によって取得した財産でなくても、実質的にみると相続又は遺贈によって取得したことと同様の経済的効果があると認められる場合には、課税の公平を図るために、相続又は遺贈によって取得したものとみなして、相続税の課税財産とすることとしています(「みなし相続財産」)。
被相続人の死亡により取得した生命保険契約の保険金で、その生命保険金などのうち被相続人が負担した保険料に対応する部分の保険金が、相続財産とみなされます(相続税法第3条第1項第1号)。
この金額は、次の計算式によって計算します。
生命保険金の額 × 被相続人が負担した保険料の額 / 払込保険料の総額 = 相続財産とみなされる生命保険の価額
なお、契約者に対する貸付金、保険料の振替貸付に係る貸付金や未払保険料の額があるときは、保険金の金額からその貸付金等の金額を控除した金額をみなし相続財産の金額として評価します。
このようなみなし相続財産とされる生命保険金には、保険金受取人が保険契約に基づき取得する死亡保険金のほか、剰余金、割戻金、前払保険料の額を含みます(相続税法基本通達3-8)。これらは、いずれも生命保険の非課税の対象になります。
これに対して、被相続人の死亡後に支払われた入院給付金、疾病給付金や特約還付金(積立部分が返還されるもの)については、本来の相続財産となりますので(当然、遺産分割協議の対象にもなります。)、非課税規定の適用はありません。
-
5-7 孫養子をした場合の注意事項は何でしょうか?
-
民法上は、養子の数には何ら制限はありませんので、何人でも養子とできます。
これに対して、相続税法上では、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)の計算に当たり、相続人としてカウントできるのは、実子がいるときは養子は1人まで、実子がいないときは養子は2人までに制限されています。
なお、特別養子や配偶者の連れ子養子については、実子とみなされますので、人数の制限はありません。
また、納付する相続税額の計算に当たり、孫養子は、配偶者又は第一親等の相続人のいずれにも該当しないため、孫の相続税額については2割加算がされます。
-
5-8 配偶者の税額軽減とは何でしょうか?
-
被相続人から配偶者に対する相続については、①同一世代間の財産移転であることが多く、その場合、遠からず次の相続が発生し、その際に相続税が課税されること、②長年共同生活が営まれてきた配偶者に対する配慮をすべきこと、③被相続人の死亡後における生存配偶者の老後の生活保障を考慮すべきこと、④遺産の維持形成に対する配偶者の貢献を考慮することなどから、一定の軽減措置が講じられております。
具体的には、1億6,000万円か配偶者の法定相続分(例えば、妻と子が相続人ならば相続財産の2分の1が妻の法定相続分になります。)のどちらか高い方の金額までは、相続税を課税されることなく、財産を相続することができます。
なお、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税の申告書(期限後申告書を含む。)を提出しなければ適用を受けることはできません。
ただし、配偶者の税額軽減の適用については、次の点に注意したいです。
①配偶者税額軽減を最大限活用して一次相続の相続税を減らすことができたとしても、二次相続での相続税を合わせた一次二次通算の合計税額では、逆に相続税負担が多くなることがあるということです。
したがって、相続税の節税だけを考えるならば、一次相続、二次相続をシュミレーションしてみて、トータルでの相続税額を計算してみる必要があります。その際は、配偶者税額軽減を考慮しながら、配偶者が取得する相続財産をどうするかシュミレーションして決めるということになります。
②配偶者が相続した財産について小規模宅地等の特例を適用すると、せっかく小規模宅地等の特例の適用を受けて土地の評価額を減額しても、配偶者税額軽減を受けることによって小規模宅地等の特例の適用を受けたメリットがなくなってしまうことがあります。このような場合、できれば小規模宅地等の適用を受けることができる子から、この特例の適用を受けるようにしたいところです。
③遺産分割協議が相続税の申告期限までに成立していない場合には、配偶者の税額軽減の適用を受けることができません。
仮に、申告期限までに、遺産分割協議が成立しない場合には、申告期限までに法定相続分により計算した相続税の申告書とともに「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することによって、後日、遺産分割が成立した際に、更正の請求又は修正申告書の提出をすることで、配偶者の税額軽減の適用を受けることができます。
以上述べたことは、相続税の節税といった観点から述べたものであり、配偶者の今後の住まいや生活費の確保については考慮していませんので、注意してください。
-
5-9 相続税の申告を行うに当たり、加算対象となる相続開始前3年以内の贈与税の申告内容を確認する方法はありますか?
-
正しい相続税の申告書を作成するためには、相続開始前3年以内にあった贈与について、その申告内容を確認しないと作成することができません。
そのため、相続税法には、これに対応した規定を用意しており、相続税の申告(期限内申告、期限後申告、修正申告)や更正の請求をしようとする相続人は、相続税法第49条第1項の規定に基づいて、贈与税の申告内容の開示請求を行うことができることとなっています。
この開示請求に対して、所轄税務署長は、請求後2か月以内に、①被相続人に係る相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産の課税価額の合計額、②被相続人から取得した財産で相続時精算課税の適用を受けたものの合計額、について開示することになっています。
なお、いずれも合計額のみの開示となっており、相続人ごとに受けた贈与財産の課税価額は分かりませんので、請求に当たっては、相続人ごとに開示請求を行うなどの工夫をすることも必要になります。
-
5-10 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合の相続税の計算はどうなりますか?
-
相続又は遺贈のより財産を取得した者が、当該相続の開始前3年以内に当該被相続人からの贈与により財産を取得したことがある場合には、当該受遺者については、当該受贈財産の価額を相続税の課税価格に加算することになります。
加算する財産の評価は、贈与時における相続税評価額で計算した価額であり、例え当該受贈財産が相続開始時に滅失等で不存在であったとしても、理由の如何を問わず必ず加算して計算することになります。また、当該相続税の課税価額に加算された受贈財産について納付した贈与税額のうちの一定金額については、相続税額から控除することになっています。
これに対して、今回の相続において、相続財産を取得しなかった者については、当該贈与財産の価額を相続税の課税価額に加算する必要はありません。また、相続開始前3年を超える時期に被相続人から贈与された財産については、加算する必要はありません。
-
5-11 相続税の申告期限までに遺産分割が成立しなかったとき(未分割のとき)は、どのようなデメリットがありますか?
-
相続人間に争いがあり、遺産分割が相続税の申告期限までに成立しなかった場合には、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、農地等についての相続税の納税の猶予及び免除等の適用を受けることができません。したがって、一旦は多額の相続税を納付することになります。
なお、申告期限までに遺産分割が確定しない場合において、「申告期限後3年以内の分割見込書」を相続税の申告書とともに提出し、その後3年以内に遺産分割が成立したときには、更正の請求をすることによって、配偶者の税額軽減及び小規模宅地等の特例の適用を受けることができます。
これに対して、農地等の相続税の納税の猶予及び免除等については、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例とは異なり、申告期限後一定の危難内に遺産分割協議が整った場合であっても、この農地等の相続税の納税の猶予及び免除等の規定の適用はありません。したがって、この規定の適用を受けようとする場合には、必ず申告期限までに遺産分割協議を成立させておく必要がありますので注意してください。
-
5-12 遺産分割の仕方によって、相続税額は変わるのでしょうか?
-
課税遺産総額、法定相続人の数に応じた基礎控除額によって算出される、相続人全員の相続税の総額については変わることがありません。ただし、この相続人全員の相続税額の総額は、あくまでも途中経過の数字であり、最終的な各相続人の納付すべき税額の合計金額とは違います。
つまり、各相続人が最終的に負担する相続税額の合計金額については、遺産分割の仕方によって配偶者の税額軽減の適用を受けることができる金額が異なったり、あるいは遺産分割で誰が土地を相続するかで小規模宅地等の適用をいくら受けれるかが大きく異なることがあるということです。
例えば、配偶者がすべての財産を相続すれば、配偶者の税額軽減の適用により相続税額は0となります。
また、残された配偶者が居住している自宅及び敷地について、生計を一にしない別居の子が相続すると、小規模宅地等の特例の適用を受けることができませんので、土地の評価額が減額されることはありません。逆に、残された配偶者と同居している子が、自宅及び敷地を相続すれば、その子には小規模宅地等の特例が適用できますので、相続税額の減額ができます。
このように、遺産分割の仕方によっては、最終的な各人の相続税額の合計金額は変わってきますので、遺産分割の仕方を考える際には、このようなことを頭に入れておくとよいでしょう。
ただし、相続税の節税のことだけを考えて遺産分割の内容を決めると、かえって相続人間での相続争いが生じる可能性が発生するかもしれません(遺産分けに不満を持つ相続人も出てきます。)。
むしろ、どの財産を誰に承継させたいのか(例えば、自宅は誰が相続するのか)、残された配偶者の今後の生活費はどう確保するか(例えば、配偶者に預貯金を相続させるのか)などを考えて、遺産分割を決定すべきといえます。
各人の相続税の負担額を考慮した遺産分割の内容については、専門の税理士に相談した方がよいでしょう。
-
5-13 相続税の2割加算とは何でしょうか?
-
相続税の負担額を計算する場合において、その財産取得者がその被相続人の配偶者又は一親等の血族(直系尊属の孫養子は除き、代襲相続人は含みます。)以外の者であるときは、その者の相続税額は、計算した相続税額に2割を加算することになっています(相続税法第18条)。
これは、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人との血族関係が疎い者である場合や全く血族関係のない者である場合には、被相続人の財産形成に余り貢献していないことから、このような偶然性が高い相続に対しては、より重い相続税を課すことが課税の公平にも資することにつながること、
また、子が生存しているにもかかわらず被相続人が孫と養子縁組をして、子を飛び越えて孫が被相続人の財産を直接取得することによって相続税の課税を1回免れるといった租税回避行為がよく行われていることから、通常の場合に比べて高い率の相続税を課税することによって、このような租税回避行為の防止を図る必要があること
から、2割加算が行われることになっています。
2割加算は、被相続人の孫養子(孫が代襲相続人である場合を除きます。)、被相続人の祖父母、被相続人の兄弟姉妹、被相続人の甥、姪、さらに相続人以外の第三者が対象となります。
-
5-14 被相続人からの遺言によりすべての財産を取得することになり、他の相続人からの遺留分侵害額の請求に対して、金銭での支払に代えて遺言により取得した土地を譲渡した場合は、譲渡所得税は課税されますか?
また、自己の所有する土地を譲渡した場合は、譲渡所得税が課税されますか?
-
民法改正に伴い、令和元年7月1日以後に開始した相続について遺留分侵害額の請求があった場合において、遺留分侵害額を金銭で支払うことに代えて、遺言により取得した土地を遺留分権利者に対して譲渡したときは、その履行をした者は、その履行をしたときにおいて、遺留分侵害額の履行により消滅した債務の金額に相当する価額によりその土地を譲渡したことになります。したがって、あなたには、遺留分侵害額でその土地を譲渡したことになりますので、譲渡所得税が課税されることになります。
また、他の相続人からの遺留分侵害額の請求に対して、もともと自己が所有していた土地を譲渡した場合も、上記と同様に譲渡所得税が課税されることになります。
このように余分な税負担が生じることを考えますと、他の相続人の遺留分を侵害するような内容となる遺言書を作成する場合には、別途、その請求に対して遺留分侵害額に相当する金銭を支払うことができるような手当てをしておくことが必要になります。例えば、生命保険契約を締結し、遺言で財産を相続する者を死亡保険金の受取人として指定おくことにより支払資金を手当てすることができます。
-
5-15 相続税の納税資金を予め確保しておく方法には、どのようなものがありますか?
-
一番有効な方法は、被相続人が死亡した場合に備えて生命保険契約を締結しておくことです。
生命保険契約の死亡保険金は、相続税法上、法定相続人1人当たり500万円まで非課税となっておりますので、相続税の節税効果があります。さらに、死亡保険金の受取人を特定の相続人にすることによって、その特定の相続人は相続税の納税資金を手当てすることができるようになります。
もう一つの方法としては、家賃収入などが入る賃貸物件を子に対して相続時精算課税の方法により生前に贈与することにすれば、贈与後の家賃収入は子の収入になりますので、所得が分散されて所得税の節税になるほか、子にとっては将来の相続税の納税資金を事前の段階から用意できるようになります。
-
6-1 名義預金とは何でしょうか?
-
名義預金とは、口座名義は被相続人以外の者であるが、実質的な預金の所有者(帰属者)は被相続人であることから、実質的には被相続人の預金と認定されて被相続人の相続財産に計上することになる預金をいいます。
このような名義預金に該当するかどうかの判断については、①預金の出捐者(預金の原資となるお金を出した人)は被相続人であるかどうか、②取引や口座開設の意思決定をして、その手続きを行っていたのは被相続人かどうか、③当該預金の管理・運用は被相続人が行っているかどうかなど諸要素を考慮して総合的に判断することになります。
このような諸要素を基に、税務署が被相続人に帰属する名義預金であると判断した場合には、預金名義人からは、一般的には贈与によって取得したものであるとの主張がされることが多いようですが、贈与があったという事実が認められるかどうかは、贈与の事実があったと立証できるかどうかにかかっています。
贈与があったことの立証については、①贈与者と受贈者との間に贈与する・もらうという合意が存在すること(贈与契約書が存在するとよい。)、②贈与したお金については、被相続人の預金口座から受贈者の預金口座への振込みによって行うこと、③贈与された者は預金通帳及び印鑑を管理していること、④受贈者は、贈与された預金を自分のために管理し使用していること、⑤贈与税の申告書を提出していること、によって行うことができます。
特に、①のあげる・もらうという意思の合致(合意)の存在と、預金通帳及び印鑑を管理支配していることが重要なポイントになります。当然、贈与契約書が存在していたとしても、もらったとする者が、預金の存在を知らないとか、通帳や印鑑を保管していない場合には、受贈者の預金とは認められませんので、注意が必要です。
-
7-1 相続財産の評価は、どのようにして行うのでしょうか?
-
相続税の課税対象となる財産の価額は、相続、遺贈又は贈与により取得した時における「時価」により算定するとされています(相続税法第22条)。
この場合の「時価」については、法令には規定がありませんが、客観的な交換価値をいうとされています。
なお、相続税基本通達では、「時価」とは課税時期において、それぞれの財産の状況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいい、この価額は、この通達の定めによって評価した価額によると規定しております(相続税法基本通達の1の1(2))。
現実には上記の条件で財産の評価額を算定することは困難でありますので、この通達の定めに従って評価することになります。
ただし、評価通達に基づく土地建物の評価額の圧縮効果を利用して相続税の申告を行ったケースでは、例えば、被相続人が90歳以上の高齢であるにもかかわらず、死亡する直前に金融機関からの多額の借入金によってマンションを建設して、低い相続税評価通達に基づく評価額で相続税の申告を行った上で、死亡から1、2年後においてマンションを高額な時価で売却するといったようなケースでは、課税庁から評価通達に基づく評価額を否認されて、時価(不動産鑑定士による評価額)で評価額を算定されるといったこともありますので、注意が必要です。
-
7-2 配偶者居住権とはどのようなものでしょうか?
-
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた居住建物(自宅)を相続しなくても、配偶者が、終身又は一定期間の間引き続きその居住建物に住むことができる権利となります。つまり、自宅の建物に対する権利について、配偶者居住権と居住建物の所有権とに分けて、配偶者居権を相続した配偶者に住む権利を認める一方で、他の相続人に居住建物の所有権を認めるというものになります。また、土地については、敷地を利用する権利と所有権に分けて、配偶者が敷地利用権を相続し、他の相続人が敷地の所有権を相続することになります。配偶者居住権の評価は、存続期間を配偶者の終身とした場合、完全生命表による余命年数などを参考に評価することになっています。これによって、配偶者は、配偶者居住権と敷地利用権を相続し、他の相続人は、建物所有権と敷地所有権を相続することになりますので、配偶者は、配偶者と子が相続人のケースにおいて、たとえ法定相続分の2分の1しか相続できないとしても、配偶者居住権と敷地利用権の評価額は自宅の建物及び土地を相続するケースに比べて低いので、自宅に居住しながら他の預貯金も相続できることになり、配偶者は老後の生活資金を得ることができるというものです。
このような配偶者居住権は、遺産分割、遺贈又は審判によって取得した場合には、配偶者居住権の設定登記が可能となり、登記をすることによって第三者に対抗することが可能となりますが、配偶者居住権を譲渡することはできません。
また、配偶者が死亡した場合には、配偶者居住権の権利は消滅することになります。この場合、他の相続人は、配偶者居住権の消滅に伴い配偶者居住権及び敷地利用権に相当する価額を取得することになりますが、これは相続又は遺贈による取得ではないため、相続財産にはなりません(この点を利用することで、相続税の節税につながるという仕組みとして活用が宣伝されています。)。
このような配偶者居住権は、本来は、相続財産として自宅と預貯金しかない場合に、子供が法定相続分を主張すると、配偶者は、自宅を相続すると預貯金が相続できなくて老後の生活資金が不足するケースで、この配偶者居住権を利用することによって、自宅に住み続けることができて、さらに老後の生活資金として預貯金も相続できるという活用の仕方として考えられていました。
しかし、本来的な活用法としての配偶者居住権は、実際にはほとんど活用されておらず、最近では、むしろ相続税の節税対策としての活用が注目されているようです。つまり、配偶者居住権は、配偶者の死亡によって消滅するのであって、子供は相続又は遺贈のよって配偶者居住権を取得するわけではないので、相続税の課税対象にならず、したがって、二次相続の際に相続税を大幅に減額できるということです。
ただし、配偶者居住権は売却することができないため、仮に配偶者が介護施設に入ることになったとしても、配偶者居住権を売却してその入居資金に充てることができないというデメリットがあります。
配偶者が長生きするか短命に終わるかは不確定であり、こういったことからも配偶者居住権は、安易に節税対策で利用しない方がよいかもしれません。
-
7-3 小規模宅地等の特例というのはどのようなものでしょうか?
-
小規模宅地等の特例とは、相続又は遺贈によって取得した財産のうち、相続開始直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用又は事業の用に供されていた宅地のうち、納税者が選択した宅地につき一定の限度面積までの部分について相続税の課税価額を減額することができる制度になります。
この小規模宅地等の特例によって減額することができる割合は、①特定居住用宅地等については、限度面積330㎡まで、減額割合は80%、②特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等については、限度面積400㎡まで、減額割合は80%、③貸付事業用宅地等については、限度面積200㎡まで、減額割合は50%となっております。
小規模宅地等の特例の要件は、いろいろあり複雑ですので、適用できるかどうかの判断については税理士に相談した方が良いでしょう。
また、誰が取得したどの土地について選択して適用するか、選択適用の仕方によっては、最終的な相続税額が大きく変わってくることもありますので、専門の税理士に相談した方が良いでしょう。
-
8-1 長年連れ添った配偶者に居住用不動産やその購入資金を贈与すると非課税となりますか?
-
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産や居住用不動産を取得するための現金を贈与した場合には、贈与税の計算上、贈与税の配偶者控除(2,000万円)が控除されます。また、これとは別に、贈与税の基礎控除(110万円)も受けられますので、結果的には合計2,110万円までは贈与税がかかりません。
なお、相続税法には、相続発生前3年以内贈与は相続財産に加算しなければならないというルールがありますが、この贈与税の配偶者控除は、そもそも加算の対象外となっておりますので、相続財産に加える必要はありません。
以上のことからすると、贈与税の配偶者控除は、たとえ相続人間で争族争いになったとしても、残された配偶者の居住する自宅を確保することができて、かつ相続税の節税にもつながりますので、非常に良い方法だと考えられます。
ただし、生前贈与の形で自宅及び土地の所有権を配偶者に移転するケースでは、移転に伴う不動産取得税(固定資産税評価額の100分の3、土地は2分の1の減額あり)や登録免許税(固定資産税評価額の1,000分の20)及び司法書士の報酬といったコストを負担する必要があります。この金額は、数十万円といった具合に結構な金額にもなります。
一方、生前贈与をしない場合、残された配偶者が自宅の土地及び建物を相続すれば、小規模宅地等の特例の適用により、土地の評価額は8割減額できますし、配偶者の税額軽減により結果的には相続税を負担しなくてもよいことになりますので、相続税の節税の観点からは、あえて贈与税の配偶者控除を活用して生前贈与をする意味はないかもしれません。また、相続による移転では、不動産取得税はかからない、登録免許税は固定資産税評価額の1,000分の4で済むため、移転コストも贈与による移転よりも安くなります。
したがって、自宅を配偶者に贈与するかどうかは、これらの点も含めて慎重に判断した方が良いでしょう。
-
8-2 住宅資金贈与とはどのようなものでしょうか?
-
父母や祖父母などの直系尊属(贈与者の年齢制限はない)からの贈与により、子又は孫(贈与を受けた年の1月1日現在で18歳以上であること)が、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、省エネ住宅(消費税10%)であれば1,500万円、それ以外の住宅(消費税10%)であれば1,000万円までの金額について、贈与税が非課税となる制度になります。適用期限は、現在のところ令和5年12月31日までとなっており、延長されるかどうかは不明です。
住宅資金贈与が適用される一定の要件は、①贈与者は受贈者の直系卑属(父母、祖父母)であること、②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること、③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること、④贈与を受けた翌年3月15日までにその家屋を取得し居住すること、などになります。
なお、この制度の適用を受けた後の残額については、別途、暦年課税の基礎控除(110万円)又は相続時精算課税の特別控除(2,500万円)の適用が認められます(他の制度との併用が可能になります。)ので、基礎控除後又は特別控除後の金額に対して贈与税がかかります。
住宅資金贈与は、相続税の計算上、もともと3年(改正により令和6年1月1日から段階的に7年に延長)以内加算の対象から除外されていますので、相続税の節税対策としては非常に有効な方法になります。
-
8-3 教育資金の一括贈与とはどのようなものでしょうか?
-
もともと子や孫の日常的な教育費を、必要な都度贈与しても贈与税はかからないことになっています(相続税法第21条の3第1項第2号)。しかしながら、祖父母が孫の教育資金をまとまったお金で贈与したいという場合には、当面使わない部分について贈与税が課税される可能性もあることから、この場合でも贈与税の課税が生じないようにしてほしいとの要望に沿ってできた制度がこの教育資金の一括贈与の制度になります。
令和8年3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金に充てるために、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母などの直系尊属から、信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入した場合には、孫などは、それらの信託受益権の価額のうち1,500万円まで贈与税が非課税になります。
しかも、この教育資金一括贈与を使って贈与した分については、相続税の計算上は加算対象になっていませんので、生前贈与を活用した相続税対策としては非常に有効な方法になります。
ただし、この制度を活用する上で注意しなければならないのは、受贈者が30歳になるまでに使いきれなかった分(管理残額)については、贈与税がかかることです。
この教育資金管理契約の期間中に贈与者が死亡した場合における管理残額に対する課税の取扱いについては、教育資金贈与の拠出時期により、次の3つに分かれています。
①平成31年3月31日までの教育資金贈与のケースであれば、贈与者が死亡した場合には、何らの課税関係も生じません。
②平成31年4月1日以後令和3年3月31日までの教育資金贈与のケースで、贈与者が死亡した場合には、相続開始前3年以内に贈与されたもの(拠出分)について使い残しの管理残額があれば、相続財産として相続税の課税対象になります(逆に、3年以内の贈与に該当しなければ、相続税の課税問題は生じません。)。なお、受贈者が孫であっても、相続税の2割加算はありません。
③令和3年4月1日以降の教育資金贈与のケースで、贈与者が死亡した場合には、使い残しの管理残額があれば、贈与(拠出)された日がいつであっても、相続財産として相続税の課税対象になり、さらに、受贈者が孫であるときには、相続税額の2割加算が適用されます。
ただし、②又は③に該当する場合であっても、贈与者が死亡した時点で、①受贈者が23歳未満である場合、②在学中であった場合、③教育訓練を受けている場合には、相続財産に加算する必要はありません(相続税の課税はありませんし、贈与税の課税もありません。)。なお、このように贈与者死亡時に課税がされないケースであっても、最終的に受贈者が30歳になった時点で使い残しがあれば、贈与税がかかることになる点にも注意が必要です。
以上のように、この制度はできた当時は贈与者が死亡した場合において、使いきれなかった管理残額について相続税の課税も贈与税の課税も全くありませんでしたが、その後、富裕層が教育資金一括贈与で相続税の節税につなげる動きが目立ってきたことから、格差の固定化を招くという批判を受けて、一定の範囲で課税が行われるように変更になりました。
したがって、仮に教育資金一括贈与を行うとしても、一度にまとまったお金を教育資金贈与で渡す場合は、使い残しが生じないように、受贈者の年齢や進学の方向性をよく検討してシュミレーションをすることも必要です。
なお、最初に述べたように、孫や子に必要な教育資金をその都度直接祖父母から援助してもらうことは、金額の多寡を問わずもともと贈与税がかかりませんので、こちらの方法を活用することも一つの方法です。
-
8-4 暦年贈与のメリットとデメリットは何でしょうか?
-
暦年贈与とは、1年間に受けた贈与の額について、贈与税が課される方式の贈与であり、受贈者(贈与を受ける人)一人当たり年間110万円までは非課税となる非課税枠があります。
この暦年贈与の基礎控除110万円をうまく活用すれば、相続税の負担を軽減することができます。どちらかというと、相続が発生するまでにまだまだ時間があると見込まれる方が、長期間に渡って計画的に節税対策を行っていくことになります。
暦年贈与で気を付けたいことは、後日税務署から贈与の事実を否認されないようにするために、①贈与契約書を必ず作成しておくこと、②現金贈与については現金の手渡しではなく銀行の口座を通して金銭の移動を行うこと、③交付した現金(またはその現金で預入した預金通帳)については受贈者が管理していること、④毎年現金贈与する場合には定期贈与と認定されないように、贈与の日付、金額を毎年変えること(毎年同じ日に同じ金額の贈与をしないこと)、などの対策を行っていくことです。
ただし、暦年贈与については、被相続人が死亡する前3年(令和6年1月1日以降は順次7年まで延長)以内に行われた贈与については、相続税の計算上は課税対象に含めることになっていますので、3年以内に該当する暦年贈与については、相続税対策としては無駄になってしまいます。でも、3年以内贈与が加算されるといっても、いつ相続が起こるかは誰にも分かりませんので、この点は気にしないで暦年贈与を計画的に実行すべきかと思います。
このような暦年贈与のメリットとしては、①長期間にわたり多くの子や孫に贈与を行うことで相続税の負担を軽減することができること、②年110万円の範囲内の贈与では贈与税が課税されないこと(無税で資産の移転ができること)、があります。
一方、デメリットとしては、①一時に多額の財産を贈与することができないこと、②相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の計算上相続財産に取り込まれて相続税がかかること(納付済みの贈与税は控除できます。)、があります。
令和6年1月1日以降は、改正された暦年贈与と相続時精算課税とどちらを活用するのが良いかは、よく検討して実行するべきです。
-
8-5 相続時精算課税とはどのようなものでしょうか?
また、相続時精算課税のメリットとデメリットは何でしょうか?
-
相続時精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から18歳以上の子又は孫への贈与を行い、贈与をした者が死亡した場合には、相続税の計算上相続財産に加算して精算するという方式になります。
相続時精算課税方式による贈与では、贈与税の計算上2,500万円の特別控除枠があり、この特別控除額を超える部分は一律20%の税率となっています。最終的には、相続が発生した時点において、相続又は遺贈によって取得した財産と相続時精算課税で取得した財産を基に相続税の計算を行い、既に納付した贈与税額の精算をすることになります。
つまり、この制度を活用すれば、2,500万円までの範囲内での贈与であれば、一切贈与税がかからないということです。ただし、相続発生時に相続税がかかることもありますので、活用に当たっては注意が必要です。
注意すべき点は、この相続時精算課税制度は、①暦年贈与との併用できないこと、②一度その贈与者との間で相続時精算課税を選択した場合には、再び暦年贈与を使うことができないこと、です。
このような相続時精算課税のメリットとしては、①子供世代にとっては、相続を待たずに早めに多額の贈与を受けることができること、②相続財産の計算に当たっては、贈与した時点での価格で計算されるので、値上がりが見込まれる財産(収用予定の土地、業績好調な株式など)については低い評価額での計算となり有利となること、③相続税より過去に納めた贈与税の方が多ければ、多い分は還付されること、④家賃収入などが入る賃貸物件を早期に子に贈与することにより、贈与後は家賃収入は子の収入となり、所得分散の効果により所得税の節税になるほか、子にとっては将来の相続税の納税資金を用意できること、があげられます。
一方、デメリットとしては、①一度相続時精算課税を選択した場合には再び暦年贈与を行うことができないこと、②贈与時の時価で相続財産に加算されることから、贈与財産の価格が値下がりした場合には相続税の計算上不利となること、③相続時精算課税は実質的には課税を先延ばしするだけで相続税の節税効果はないこと、④受贈財産が消費されて(滅失して)なくなったとしても、相続税の課税上は計算に入れられること、⑤相続税の計算に当たり小規模宅地等の特例の適用(評価減)ができないこと、があげられます。
特に、①と④のデメリットが非常に大きなものとなります。
以上のメリットとデメリットを踏まえて、相続時精算課税を選択するかどうか、慎重に検討する必要があります。
もともと相続時精算課税の贈与分を加算しても、遺産総額は相続税の基礎控除の範囲内しかないという家庭では、最終的に相続税もかかりませんので、生前に早期に財産を移転できて、相続争いも防止できるという点で非常に大きなメリットがありますので、積極的に活用した方が良いでしょう。
なお、相続税法の改正により、令和6年1月1日以降は、申告等に事務負担を軽減するといった観点や、もっと相続時精算課税を利用して早期に子孫代への資産移転を行ってもらい消費の喚起及び経済の活性化につなげたいという理由から、相続時精算課税を適用した場合においても、毎年110万円までの基礎控除を設けて、この金額の範囲内は贈与税の課税対象から控除されて、しかも相続時の相続税の計算上も加算対象にもならないようになる予定です。
一見すると、暦年贈与よりも相続時精算課税の方が、相続税対策としての生前贈与として利用価値が高いようにも見えますが、あらかじめ税務署に対して相続税対策をやりますと宣言することになりますので、税務調査のリスクは高まるかもしれません。
-
9-1 相続後に空き家となっていた自家の建物及び土地を譲渡した場合の税金はどうなりますか?
-
不動産(空き家)を売却して得た利益(譲渡所得)には、原則として一定の所得税がかかります(所得税は、原則として譲渡した年の1月1日において所有期間が10年超ならば15%、10年以下ならば30%)。
ところで、被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除(空き家譲渡特例)の適用があれば、納付すべき所得税は大幅に減らすことができます。この空き家譲渡特例は、毎年ものすごい勢いで増え続ける空き家対策として制定されたものであり、また、耐震基準を満たさない家屋(空き家)の取壊しを促進するためにできた制度になります。
ただし、この空き家譲渡特例を適用するには、確定申告が必要です。
例えば、被相続人である父又は母が一人で住んでいた家屋及び敷地を子が相続し、相続後に空き家を売却した場合において、一定の要件を満たせばこの制度の適用が可能となりますが、制度を利用する上での要件が非常に厳しいことから、なかなか利用が進んでいません。特に、空き家を取り壊す費用は何百万円と多額になりますので、相続人が事前に取壊費用を負担することが難しいことも多く、利用が進まない一つの要因ともなっていました。
この空き家特例の要件としては、①昭和56年5月31日以前に建築された建物であること、②被相続人が一人で住んでいたこと(要介護認定や要支援認定を受けていた被相続人が特別養護老人ホーム、介護老人健康保健施設、介護医療院、サービス付高齢者向け住宅などに入居していたため、相続の開始直前において被相続人が居住していなかった場合を含みます。)、③区分所有建物以外の家屋であること、④相続時から売却時までの間ずっと空き家であること(つまり賃貸していないこと)、⑤譲渡に当たり被相続人の居住用家屋につき耐震リフォームを行うこと又は被相続人の居住用家屋の取壊しを行うこと、⑥相続開始後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、⑦売却価額が1億円以下であること、⑧売主と買主とは親子や夫婦など特別の関係がないこと、が必要になります。
この空き家譲渡特例は、令和5年12月31日までの間に譲渡した場合に適用できますが、令和5年改正により、令和9年12月31日まで4年間延長がされています。また、令和6年1月1日以降は、売買契約に基づき、買主が譲渡の日の属する日の翌年2月15日までに耐震工事又は除却工事を行った場合には、工事の実施が譲渡後であっても適用できるようになります。
この空き家譲渡特例を有効に活用する例としては、不動産(家屋及び土地の両方)を共有名義で相続した場合には、相続人それぞれが要件を満たせば、それぞれに対して空き家特例(3,000万円の特別控除)が適用されますので、例えば相続人が子2人ならば、合計6,000万円まで控除が可能になりますので、非常にメリットが大きいものです(ただし、令和5年改正により、令和6年1月1日以降は、相続人の数が3人以上の場合には、特別控除額は一人2,000万円に制限されます。)。
ただし、この空き家譲渡特例を受けるためには、事前に空き家のある市町村役場で「確認書」の交付申請手続を行う必要がありますので、事前の段階から準備をしておく必要があります。なお、更地で売却する場合には、解体してから譲渡までの土地の使用状況の写真も必要になりますので、取壊し・除却・滅失時、敷地の譲渡時までの使用状況が分かる写真が必要になりますので、注意します。
なお、この空き家の特例を受けるためには、現行制度の下では、原則として耐震リフォームを行うか空き家の取壊しを行うことが条件となりますので、土地の活用法や売却話がある程度決まって、売却による収入と控除する費用の総額の見込みがついてからリフォームや取壊しを行わないと、場合によっては適用期限までに売却できなかったり、あるいは空き家を取り壊して更地にしたため固定資産税が最大6倍になり予想外に費用がかかったりするなど様々な不利益が生じますので、十分に注意する必要があります。
-
10-1 生前には特に相続税対策を行ってきませんでしたが、今から相続税の申告までの間に、相続税を節税できる方法は何かありますか?
-
特殊な節税対策は別として、相続後においても、以下のように、少しの手間と時間をかけることにより、相続税額を減額できる方法はいろいろとあります。
①土地の評価額について、路線価評価額のままで評価するのではなく、現地調査及び市町村調査などを行って、土地の評価減の要因をできるだけ見つけて土地の評価額を引き下げることです。
例えば、不整形地の評価減、旗竿地の評価減、無道路地の評価減、セットバックを必要とする土地の評価減、市街化農地の宅地造成費の控除、私道の用に供されている土地の評価減、地積規模の大きな土地の評価減、都市計画道路予定地区域内にある土地の評価減など、土地の評価額を引き下げる方法はいろいろとあります。
②配偶者税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できるようにするために、相続税の申告期限までに遺産分割協議を成立させることです。
これらの規定は、相続税の申告期限までに遺産分割が成立していないと適用ができないことになっているからです(例外として、申告期限後3年以内に分割見込書を提出することで、事後に更正の請求をすることでこれらの規定の適用を受けることはできますが、いったんは多額の相続税額を納付する必要があります。)。
③土地については、誰が、どの土地を相続するか、また、どの土地について小規模宅地等の特例を適用するかによって、小規模宅地等の特例の適用による土地の評価減の金額に大きな差が生じますので、その辺りを考慮して遺産分割協議を進めることです。
小規模宅地等の特例の適用に当たっては、適用面積と路線価との関係で、最も単価が高い土地について特例を選択適用するとか、あるいは、配偶者税額軽減が適用される配偶者に適用するよりも、適用要件を満たす子が相続した土地について適用した方が、家族でのトータルの相続税額を減らすことができます。
④相続した土地や建物を、相続後において売却する予定がある場合(例えば、相続税の納付のために不動産を売却するとか、あるいは、共有名義とした不動産を売却して相続人間で金銭を分ける。)には、相続税額を直接減らすことはできませんが、事後に発生する所得税額を減らすことができる所得税法上の特例があります。このような特例には、譲渡期間についての制限などいろいろな要件がありますので、これらの要件を満たすように譲渡をすることです。
相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例(譲渡した財産に対する相続税額を取得費として加算できる特例)については、相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに譲渡を行うことが条件になっております。
空き家に係る譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例については、相続があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡を行うことが条件になっております。
なお、相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例と空き家に係る譲渡譲渡所得の3,000万円の特別控除の特例とは、選択適用になっていますので、注意が必要です。
-
10ー2 二次相続を踏まえた、一次相続における遺産分割のポイントは何でしょうか?
-
二次相続を踏まえた一次相続での遺産分割を考える際のポイントとしては、次の2点が挙げられます。
1 各相続人が遺産分割で取得する財産の選択について
二次相続のことを考えると、一般的には、一次相続では、配偶者は現金預金(現金預金を相続すれば、老後の生活費等の支出でいずれ減っていきますので、二次相続が発生した場合の相続財産が減ります。)を相続し、子は不動産を相続するという形での遺産分割が望ましいといえます。
特に収益物件である賃貸不動産がある場合、配偶者がこれを相続すると、相続後に賃料収入が入りますので、配偶者の相続財産がさらに積み上がってしまいます。
2 小規模宅地等の特例の適用を考えた遺産分割について
小規模宅地等の特例を適用できる土地が複数ある場合には、一次相続及び二次相続での、配偶者税額軽減と小規模宅地等の特例適用との組合せを考えながら、遺産分割を検討することも必要になります。
例えば、自宅について小規模宅地の特例を適用できる相続人は、いろいろな細かい要件は別として、配偶者、同居の子、家なき子のいずれかになります。そうすると、自分の自宅を所有している別居の子が、被相続人所有の自宅を相続しても、特例の適用はありませんので、相続税は減額されません。また、配偶者と同居の子がいる場合には、配偶者が相続するとせっかく特例の適用を受けて自宅敷地の評価額が減額となっても、結局は配偶者税額軽減の規定により相続税はかかりませんので、メリットがありません(この場合は、同居の子が相続する方が評価額の減額により家族トータルでの相続税額が少なくなります。)。
なお、以上に示した遺産分割での考え方は、あくまでも一次相続及び二次相続でのトータルでの相続税を減らすための遺産分割の提案にすぎません。したがって、残された配偶者の住まいを確保することや残された配偶者の老後の生活資金を確保するといった観点からすると、家族としてのベストな選択とはならないかもしれません。
いずれにしても、各制度の適用要件を満たすかどうかの検討も必要になりますので、専門の税理士に相談するのがおススメです。