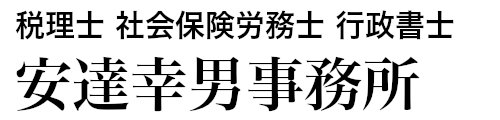-
0 相続税対策の基本的な考え方はどのようなものでしょうか?
-
相続税の節税対策は、ザックリ申し上げますと、次の相続税の計算式をいかに工夫して課税対象となる遺産額を減らすかということにあります。
[ ( 遺産額 + 3年~7年以内贈与 + 相続時精算課税 ) - 非課税財産、債務・葬式費用 ]
- 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)
= 課税対象となる遺産額
そうしますと、課税対象となる遺産額を減らすための具体策としては、次の方法が考えられます。
① 遺産額を減らすこと ⇒ 生前贈与(暦年贈与)をする、相続時精算課税の基礎控除(110万円)を使う
② 遺産額を増やさないようにする ⇒ 不動産管理会社(所有会社)を設立、賃貸物件を子に贈与する
③ 非課税財産への組換え ⇒ 生命保険に加入する、小規模企業共済(退職金)に加入する、生前に墓地・仏壇を購入する
④ 法定相続人の人数を増やす ⇒ 孫を養子縁する
遺産額の評価額を引き下げる方法として、
⑤ 評価額の低くなる財産に替える ⇒ 現金預金などの金融資産は評価額が低くなる不動産に替える
⑥ 時価と相続税評価額の差が大きい資産への組換えをする ⇒ 賃貸マンションの建設・購入をする、更地を有効活用する
⑦ 不動産の組換え ⇒ 小規模宅地の適用による評価減を増やすために地方の土地から都市の土地への買換え
⑧ 小規模宅地の特例の適用を満たすようにする ⇒ 適用要件に該当するように親の自宅に同居する(生計を一にする)
節税を考えるときのポイントとしては、相続財産(遺産額)の評価額の算定に関していえば、現金・預金などの金融資産については100%の評価額で課税されることになりますが、不動産については評価額の算定上いろいろな方法により評価額の引下げが可能となりますので、時価よりも低い評価額とすることができるということです。近い将来に確実に相続の発生が見込まれる場合には、金融資産を不動産に替えておくことは、節税対策としては非常に有効であるということです(ただし、評価額の引下げはできたとしても、相続後に処分できないような土地を取得することは避けるべきです。)。
-
1 現金贈与が税務調査で否認されない方法は?
-
相続税の節税のために、毎年のように暦年贈与の規定を使って非課税金額(110万円)の範囲内で現金贈与をすることはよくあります。この暦年贈与を使った相続税の節税対策は、非常に有効な方法といえます。
暦年贈与は、贈与する金額が少額となりますが、贈与する相手を増やすことによって、さらに長期間に渡って贈与毎年贈与を行うことによって、トータルでは大きな金額を子や孫の世代に移転させることができます。例えば、毎年、子2人、孫4人、子の配偶者2人の合計8人に対して110万円の暦年贈与を行うと、8人×110万円=880万円となり、10年間継続して行うと、880万円×10年=8,800万円となります。ただし、子に対する贈与については、相続開始前3年~7年以内贈与の加算の適用がありますので、できるだけ早い段階から生前贈与を行っていくことが有効であるといえます。
特に、相続税の計算上、相続開始前3年~7年以内贈与の加算の適用を受けない、子の配偶者や孫に対する暦年贈与は、相続税節税対策で最も有効な方法の一つであるといえます。
ところで、民法の規定によると、贈与契約は、贈与者が自己の財産を無償で受贈者に与える旨の意思表示を行い、受贈者が贈与を受諾することによってその効力を生じるとされており、両当事者の意思表示の一致が必要とされています。
仮に受贈者が未成年者の場合は、親権者が代わって贈与契約書に署名捺印をします。
なお、贈与契約自体は、書面ですることは必要ありません(口頭で贈与契約をすることも可能)。
したがって、受贈者が贈与を知らないという場合(親が勝手に子供名義の預金に100万円を入金しておくケース)は、両当事者の意思表示の合致がないことから、贈与契約は成立していないことになりますので注意が必要です。
ところで、税務調査の際に、現金の贈与があったことを否認されないようにするためには、どのようにすればよいでしょうか?この点については、税務調査の際に、贈与契約が存在することを立証することができればよいということですが、贈与契約があったということを立証するためには、次のような証拠をそろえておくとよいでしょう。
①贈与契約書を作成します(なお、公正証書で作成するとか、公証人役場で確定日付を押してもらうと、贈与契約の存在が確実なものとなります。不動産の贈与の場合は、印紙200円を貼付します。現金贈与の場合は、印紙は不要です。)。
②現金を贈与したというお金の流れが分かるように、贈与者の預金口座から受贈者の預金口座に振込する方法により行います。
③振込のあった受贈者名義の預金通帳及び印鑑は、受贈者が管理します。
④受贈者は、非課税金額(基礎控除110万円)以上の贈与であれば、贈与税の申告書を税務署に提出します。
⑤受贈者は、もらったお金を自分の個人的な支出に使用していることが分かるように使用事績を残しておきます。
以上のような証拠があれば、現金贈与の事実が税務調査で否認されることはまずないといえます(これに対して、贈与税の申告書を提出しているだけでは、贈与契約があったことを完全に証明することはできません。)。
なお、これらの証拠が不十分であったため、贈与の事実が立証できずに、受贈者名義の預金が名義預金と認定されてしまうと、この名義預金は相続財産として取り込まれることになりますので、相続税を余分に支払うことになります。
-
2 連年贈与と認定されないようにするにはどうすればよいでしょうか?
-
連年贈与は、例えば、父親が子に対して今後10年間毎年100万円ずつを贈与するとした場合に、この贈与行為の評価として、①毎年贈与税の非課税規定が適用になり、贈与税の課税はされないと考えるのか、それとも、②毎年100万円ずつ贈与を受けるという権利(約100万円×10年間=1,000万円)を無償で譲り受けたと考えるのか、ということが問題となります。
税務調査によって、連年贈与と認定されてしまうと、直系尊属から1,000万円の贈与を受けたこととなりますので、特例贈与財産として特例税率で贈与税の計算をすると、210万円(=1,000万円×30%ー90万円)贈与税がかかることになります。これに対して、毎年100万円ずつの贈与があったと認定されれば、贈与税は全くかかりません。
税務調査において、連年贈与と認定されないようにするためには、例えば、贈与をする月日を毎年変えるとか、あるいは、贈与する金額を毎年変える、といったことをしておくと、連年贈与と認定されることはないでしょう。
-
3 認知症になっている母から贈与を受けることは有効でしょうか?
-
相続対策として、暦年贈与の活用を考えている場合、もし贈与者である母親が認知症になってしまったときには、贈与契約はどうしたらよいでしょうか?
母親が認知症になってしまった場合には、認知症が悪化しているケースでは母親は判断能力(事理弁識能力)を有しないと判断されることもあります。 そうなると、母親は子供に対して財産を贈与するという意思表示をすることができないことになりますので、例えば、相続対策として、母親から子供に現金や不動産を贈与するといった契約をすることはできないことになります。
この点、不動産の贈与であれば、登記手続を行う司法書士が本人確認と意思確認を行いますので、そもそも所有権移転登記手続をすることができないでしょう。
これに対して、現金贈与となると第三者が介入しないので、贈与契約書の形式を整えてしまうことができてしまいます。
しかし、後になって訴訟等で贈与契約の有効性を争われた場合、裁判で母親に判断能力がないと判断されると、贈与契約は無効と判断されることになります。
そこで、判断能力が不十分な人を保護・支援する制度としての成年後見制度を活用することにより、成年後見人が本人を代理して贈与契約をすることができるのではないかとも考えられますが、成年後見人制度は本人の財産を守るための制度ですので、相続税対策などで本人の財産を減らすような行為は認められません。そうしますと、認知症の母親から子供への贈与をすることはできないということになります。
この点、認知症に罹る前に信託(家族信託)契約を締結しておくと、母親が認知症に罹った後でも、事前に定めた代理人(受託者)が推定相続人(受益者)に対して信託契約で定めたとおり贈与を継続して行うことができます。ただし、信託契約は初期費用が高く、設計が難しいといった面があります。
-
4 孫と養子縁組をして相続税を節税することはどうでしょうか?
-
祖父が孫を養子とすると、相続税法上の法定相続人の数が増えますので、基礎控除の金額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が増加し、超過累進税率も緩和されることから、孫養子をしなかった場合に比べて、相続税を大幅に節税することができます。
民法上は、養子は何人でも構わないことになっていますが、相続税法上は、養子の数に制限が設けられており、被相続人に実子がいるときは孫養子は1人まで、また、被相続人に実子がいない場合は孫養子は2人まで認められることになっています。
このほかに、孫養子をした場合には、死亡保険金や退職手当金の非課税規定(500万円×法定相続人の人数)がありますので、相続税をかなり減らすことが可能となります。
孫養子にするには、市町村に養子縁組届を提出するのみですので、費用もかからず、最速でできる、お手軽な相続税対策といえます。
ただし、孫養子をした場合、相続人間で争族争いが生じる可能性があるというデメリットがあります。
例えば、被相続人(父)の相続人は、妻、長男、次男、長女、長男の子A、B(2人とも孫養子に該当)、次男の子C(孫養子に該当)というケースにおいて、民法上は養子の数に制限はありませんから、孫養子A、B、Cはいずれも被相続人の相続人となりますので、仮に子(孫養子を含む。)は法定相続分に応じて均等に遺産を相続するとすると、最終的には、長男の家族(長男、A、B)が受け取る遺産額(6分の3)と、次男の家族(次男、C)が受け取る遺産額(6分の2)にはトータルで見ると大きな差が生じることになりますし、長女の相続分は養子縁組前の6分の1から12分の1に減少してしまいます。この結果を、次男家族や長女が良しとしないときは、遺産分割を巡って争族争いとなることもあります。
このように、相続税の節税だけを考えて安易に孫養子を行うと、一部の相続人の理解が得られずに遺産分割協議が紛糾することとなり、争族問題にもなりかねません。
孫養子を行うかどうかは、慎重に判断することが必要です。
-
5 死亡直前に借入金で賃貸マンションを建設することは相続税の節税になりますか?
-
相続対策として、生前に更地に賃貸マンションを借入金で建設することが未だに流行っているようです。
なぜ賃貸マンションを建設することが相続税の節税対策になるかといいますと、相続税財産評価通達を使った場合には、評価額を大幅に減額することができるからです。すなわち、
土地については、路線価で評価(時価の8割程度に設定されています。)することになりますが、マンションを建設した敷地である土地の評価については、貸家建付地として評価(借地権割合×借家権割合を控除する。)することになっております。例えば、借地権割合を50%として、借家権割合は30%ですので、貸家建付地として評価すると、更地価額よりも15%評価が低くなります。
また、建物については、固定資産税評価額で評価(建築費の6~7割程度)しますが、さらに貸家として評価(借家権価格の30%を控除する。)することになります。そうすると、現金1億円を出してマンションを建設すると、建物は約4割の評価額になります。
その上で、マンション建設の借入金については、債務控除として、借入金の金額をそのまま遺産額から控除しますので、結果的に課税対象となる遺産額がさらに減少することになります。
さらに、賃貸マンションの敷地については、相続税法上の特例である小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)の適用を受けることができますので、上記で算出した土地の評価額から、200㎡までの範囲で50%の評価額の減額をすることができます。
以上のように、現金と土地(更地)を保有する場合に比べて、賃貸マンションを建設した場合にはトータルでの相続税評価額はかなり安くなります。
このように更地にマンションを建設することは、土地を有効活用することや相続税の節約に役立つことから、非常に有効な手法であるといえます。
ただし、平成30年の改正(平成30年4月1日以後に適用)により、小規模宅地等の特例については見直しがあり、貸付事業用宅地の範囲から、相続開始前3年以内に貸付の事業の用に供された宅地等(ただし、相続開始前3年を超えて事業的規模で貸付事業を行っている者が行うケースを除きます。)は除外されることになっております。
したがって、相続税の節税のために死亡する直前に賃貸マンションを建設しても、小規模宅地等の特例の適用を受けることができなくなりましたので注意が必要です。
ところで、上記に記述したことは、あくまでも相続税の節税という観点から見た場合に限ってのお話ということです。
これよりももっと大切なことは、マンションを建設した場合、今後、事業主としてこの先何十年もマンション賃貸経営を行っていくということを忘れてはいけません。つまり、マンション賃貸経営の収支が、将来にわたってずっと黒字(あるいはキャッシュが残る)になるようにしていくように経営努力をしていくことが大切であるということです。そうでないと、せっかくマンション建設で相続税の節税はできたもけれども、経営は赤字続きであって、借入金の返済もできずに、結局はマンション及び土地を売却せざるを得ないといったことにもなりかねません(建設会社や金融機関のアドバイスに従って実行すると、意外とこうなるケースが多いようです。)。
なお、賃貸経営として今後も黒字が見込まれるかどうかという点について考えますと、一般論として、日本は人口減少社会にあって、地主の相続税対策により今後も新築マンションが続々と供給されていく中で、入居者が常に満室ということは余り考えられないかもしれません。
マンション建設をするか否かを検討するに当たっては、そもそも立地場所として入居者の需要が見込まれる地域かどうか(駅に近いかなど)、将来にわたって入居者が確保できるかどうか(近くに大学や工場があるかなど)、今後の修繕費や建物取壊し費用の支出を考えると果たして収支がプラスになるかどうか、といった点を踏まえて、賃貸経営の事業計画の中身をよく検討しておくことが大切といえます。
-
6 賃貸マンションを子供に贈与する場合の注意点は?
-
賃貸マンションを親から子に贈与することは、相続税対策としては非常に有効であり、かつ実効がしやすいとも言われています。
相続税対策として有効な理由は、親が賃貸マンションを保有していると、賃料収入がどんどんと貯まって遺産総額が増えますが、賃貸マンションを親から子に贈与することによって、親の預貯金の積み上げもなくなり、一方で、子にとっては贈与された賃貸マンションの収入を貯蓄することによって将来の相続税の納税資金を確保することができるようになるからです。
また、対策が実行しやすいという理由は、年数の経過した賃貸マンションは、既に減価償却費も相当計上しておりますので、建物簿価も低くなっており、当然、固定資産税評価額も相当低くなっています。そうしますと、土地を贈与する場合に比べて、建物を贈与する場合には、贈与税額も少なくて済むからです。
ただし、賃貸マンションを親から子に対して贈与する場合、注意しなければならない点が1つあります。
例えば、時価1,000万円(相続税評価額200万円)の賃貸マンション(敷金100万円を預かっている)を子供に対して売買契約をするケースで見ますと、
建物を相続税評価額の200万円で贈与すると、負担付贈与に該当すると認定されて、建物評価額が時価に引き直しされて計算することになるからです。
負担付贈与に該当するとなると、贈与者は負担額(敷金100万円のこと)でマンションを譲渡したものとみなされます。そうすると、譲渡所得の計算は、100万円(負担額)ー1,000万円(時価)=△900万円となります。
他方で、譲渡価額(100万円)が時価(1,000万円)よりも低額である場合、受贈者は時価と譲渡価額との差額を贈与者から贈与を受けたものとみなされることがあります。
つまり、負担付贈与の場合、贈与税の計算における贈与財産の評価額は、通常の相続税評価額で計算するのではなく、時価で計算することになっていることから、受贈者は、マンションの時価(1,000万円)から負担する敷金債務の額(100万円)を控除した金額(900万円)に対して、贈与税が課税されることになります。
このような結果を回避するためには、敷金の引継ぎを受けていないこと、つまり負担付の贈与には該当しない、とする必要があります。
そこで、負担付贈与に該当しないようにするためには、マンションの贈与と同時に、敷金相当額の現金100万円を併せて贈与することにより、敷金の引継ぎはなかったもの(贈与に伴う実質的な負担はないもの)とすることになりますので、贈与財産を相続税評価額で評価することができますので、贈与税の課税の問題は生じないことになります。
-
7 不動産の評価額を引き下げるには、どうすればよいでしょうか?
-
不動産のうち土地については、基本的には路線価×画地補正等×面積で評価額を算出します。
仮に、土地の上に自宅が建っていたとしても、土地の評価は自用地として上記の計算式は変わりません。
ただし、土地の上に建物が建っており、この建物を他人に賃貸している場合には、下記の算式のとおり、貸家建付地評価となり、土地の評価額を引き下げることができます。
貸家建付地の評価額=路線価×画地補正等×(1-借地権割合×借家権割合)×面積
※借地権割合は、路線価図に記載されている借地権割合(A(90%)~G(30%)で表示、通常はE(50%)が多い。)によります。借家権割合は、30%です。
ということは、更地の評価額からみると、例えば借地権割合E(50%)の土地であれば、マンションやアパートを建てることによって、15%の評価額の減額になるということです。
不動産業者や金融機関が、地主に対して相続税対策としてマンション建設を進める理由は、このように土地の評価額が減額されて下がるからです。加えて、建物の評価額も固定資産税評価額で計算しますので、建物評価額は建設費用の40%程度となり、さらにここから借家権割合の30%を控除しますので、建物の評価額も大幅に引き下げることができます。
地主の方が、現金1億円と土地(更地)1億円の合計2億円を持っているよりも、このケースで現金1億円でマンションを建設すると、土地は8,500万円、建物は2,800万円となり合計1億1,300万円の評価額となり、評価額が大幅に引き下げることができるということです。
ただし、相続税の節税対策としてマンション建設をすることがベストかどうかは非常に疑問があります。節税対策とは別で、マンション経営がうまくいかないと元も子もなくなりますので、注意してください。
-
8 遺産分割では地積規模の大きな土地の特例が使えるように?
-
三大都市圏(中部圏の都市開発地域で、愛知県の大半の市が入ります。)内の500㎡以上地積の土地については、地積規模の大きな土地の評価の特例(路線価に奥行価額補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほかに、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算する。財産評価通達20ー2)が適用できる可能性があります。
規模格差補正率とは、次の算式によって求めます。
規模格差補正率=A×B+C / 地積規模の大きな宅地の地積(A) × 0.8
※B、Cの数字については、財産評価基本通達の20-2に掲げる表によります。
一般的には、規模格差補正率によって、概ね20%くらい土地の評価額が減額できますので、非常に大きな相続税の節税対策につながります。
※地積規模の大きな土地の評価額の減額は、開発行為を行うとした場合の道路、公園等の施設用地の負担が生じ潰れ地が生じることから、評価額の減額が認められています。
この特例の適用要件としては、原則として
①路線価地域に所在すること(例外的に倍率地域内の土地についても、一定の条件を満たせば適用できます。)、
※国税庁HPの路線価図で確認できます。
※宅地だけでなく、雑種地や市街化農地についても、適用できるケースがあります。
※現に建物やマンションが建っていても、適用ができます。
②路線価地域の普通商業・併用住宅築又は普通住宅地域に所在すること、
※路線価図で、路線の上にある地区表示記号が、〇印(普通商業・併用住宅地区)となっているか、無印(普通住宅地区)となっていることです。
③三大都市圏においては、500㎡以上の地積を有していること、
※三大都市圏に該当する市町村は、国税庁HP、国土交通省HPで確認することができます。
愛知県は、大半の市町村がこれに該当しています(春日井市、小牧市は該当します。)。
④都市計画法の用途区域が工業専用地域に指定されている地域でないこと、
※市役所のHPで、該当する土地について都市計画図の用途地域を確認します。
⑤指定容積率が400%以上の地域の所在する土地でないこと、
※指定容積率とは、建築基準法第52条第1項に規定する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。
指定容積率は、該当する土地について、市役所HPの建築基準法の指定容積率を確認することで分かります。周りに住宅が建っている地域では、指定容積率はほとんどが200%となっています。
といったことがあります。
このうち、周りが住宅地になっている自宅や駐車場、あるいは市街化内農地の場合には、上記の要件のうち一番の問題になるのは、面積の要件です。
この面積要件については、遺産分割後に土地を取得した相続人ごとに判定することになっています。
そうしますと、仮に被相続人が、1筆で800㎡の土地を所有していたとしても(死亡時は面積要件を満たしていた。)、遺産分割によって2人の相続人に対して、2分の1ずつの面積になるように分筆した上で、各相続人がそれぞれ分筆後の土地を相続した場合には、各相続人の取得した土地の面積は、それぞれ400㎥しかありませんので、面積要件を満たすことができません。
このように、遺産分割の仕方によっては、地積規模の大きな土地の評価の特例を適用できたり、適用できなかったりしますので、遺産分割の仕方には十分に注意する必要があります。
では、先ほどの事例でいくと、どのように遺産分割をすればこの特例が適用できるかというと、
一つは、各相続人2分の1ずつの共有名義とする方法です。これは、共有名義の場合は、持分で按分する前の面積で面積要件を判定するからです。ただし、共有名義となりますので、その後の処分・管理を巡って意見がまとまらないと、何もできないというリスクがあります。
もう一つは、相続人の一人がこの土地を相続して、他の相続人には代わりにお金(土地評価額の半分)を支払うという方法(代償分割)です。この方法のネックは、土地を取得する相続人に、代償金を支払うだけのお金があるかどうかです。
以上のように、被相続人が500㎡以上の土地を所有しているケースでは、遺産分割の仕方に工夫をすることで相続税の節税が図られるケースもありますので、注意したいところです。
-
9 小規模宅地等の特例が適用できる条件を生前に整える?
-
小規模宅地等の特例は、被相続人の居住する自宅の敷地については、居住する者が多額の相続税の支払で居住用家屋及び土地を売却することなくそのまま居住することができるようにという趣旨から、一定の評価額の減額(330㎡まで80%の評価額の減額)ができることになっています。
この小規模宅地等の特例は、例えば自宅の敷地が300㎡あり、路線価が10万円/㎡のケースでは、土地の評価額は3,000万円のところ、10万円×300㎡×0.8=2,400万円の評価額が減額できますので、600万円しか課税遺産額に算入されないことになります。相続税の節税対策の中では、最も大きな効果があります。
ただし、適用ができる者は、①同居する親族、②同居家族がいない場合の生計一の親族、③家なき子に限られています。
仮に、被相続人である夫が死亡し、相続人は同居の妻、別居の長男(持ち家あり)、別居の長女(持ち家あり)のケースでは、同居する妻が自宅及び敷地を相続すれば、小規模宅地等の特例の適用を受けることができますが、持ち家のある長男や長女が相続すると、特例の適用はありません。
また、被相続人の父が死亡し(母はそれ以前に死亡)、相続人は別居の長男(持ち家あり)と別居の二男(借家住まい)のケースでは、二男が自宅及び敷地を相続すれば、③の家なき子として、特例の適用を受けることができますが、持ち家のある長男が相続すると、特例の適用は受けられません。
それから田舎の方ではよくあるケースになりますが、大きな敷地に被相続人の父の自宅(母はそれ以前に死亡)と長男の自宅(長男の自宅敷地は父から使用貸借で借りている。)の2棟建っているケース(母はそれ以前に死亡)では、相続人は長男のみとして、長男は父と生計を一(食事やお風呂が一緒で財布が一つの状態)にしていない限り、父の土地を相続した長男は、父の自宅の敷地部分はもちろん、長男の自宅の敷地部分についても、特例の適用を受けることができません。つまり、評価額の減額が一切受けられないということです。通常、父は、年金を受給しており、生活費も自分の収入で賄っていることが多いので、同じ建物に同居していない限りは、父と長男は生計一にしているとはいえません。このようなケースでは、父に介護は必要になった段階から、父の家に長男は同居するといった方法を取ることによって、特例の適用を受けることができます。
なお、同居をしていないので、住民票だけを父の家の方に移すとか、生活費を援助していると偽ることによって、小規模宅地等の特例を受けることは、税務調査において特例の適用を否認されるリスクがありますので注意してください。
-
10 小規模宅地等の特例対象の土地が複数ある場合、どの土地を選択したらよいでしょうか?
-
小規模宅地等の適用を受ける土地が複数存在する場合(例えば、自宅、賃貸マンションがあるケース)には、基本的には、それぞれの土地について限度面積まで特例を適用した場合の1㎡当たりの評価減の金額を比較して、最も1㎡当たりの評価減の金額が最も高い土地を選択して特例を適用することで、相続税の総額を少なくすることができます。限度面積との関係で、1㎡当たりの評価減の金額ではなく、適用した場合の評価減となる金額が最も高い土地を選択するということもあります。
ただし、配偶者と子が、それぞれ適用対象となる土地を取得したとした場合(例えば、配偶者は自宅の敷地を取得し、子は賃貸マンションの敷地を取得したケース)には、配偶者については、配偶者の税額軽減の規定により相続税額が軽減されますのでこの土地を選択するのではなく、子の取得した土地(賃貸マンションの敷地)について特例を適用した方が、結果的には相続税額の節税を図ることができることになりますので、一概に1㎡当たりの単価によって選択することがよいとはいえません。
したがって、特例が適用可能な複数の土地について、それぞれの土地を選択適用した場合の相続税額を計算して、さらに、配偶者税額軽減の適用をした場合の相続税額の試算とも比較して、どの選択が一番相続税が少なくなるかをシュミレーションして、特例を適用する土地を決定することになります。
-
11 配偶者居住権を活用した節税は?
-
配偶者居住権は、本来は、相続人として配偶者と子供(非嫡出子)がいるケースで、相続財産としては、自宅(2,000万円)と預貯金(2,000万円)がある場合において、子供(非嫡出子を想定)が法定相続分(2分の1)を主張したときには、配偶者は、仮に自宅を相続するとすると、預貯金は一切相続できなくなってしまいます。このような事例で、残された配偶者の老後の生活資金が不足する事態になることを回避するために、配偶者居住権(評価額を800万円と仮定)を設定することにより、残された配偶者は、自宅に住み続けることができて、しかも預貯金(1,200万円)も相続できるというものでした(制度制定時は、後妻である配偶者と先妻の子供との相続において活用することが想定されていました。)。
ところが、本来的な活用方法としては、配偶者居住権はほとんど活用されておらず(家族仲が良い親子間では円満に法定相続分にとらわれずに遺産分割をすれば足りるし、非嫡出子との間では「遺贈」により使うことはあるかもしれない。)、むしろ節税対策としての活用が注目されているようです。
相続税対策として活用できるという理由は、配偶者居住権を設定した配偶者がその後死亡した場合には、配偶者居住権が消滅することになりますので、相続人である子は完全な所有権を取得することができますが、これは相続又は遺贈による取得ではないことから、二次相続では相続税が課税されないこととなるというメリットがあるからです。
配偶者居住権はそもそも平均余命等を考慮して評価しますので、配偶者が一次相続後短期間のうちに死亡すれば、消滅する配偶者居住権の価額も大きくて、相続税の節税のメリットが大きくなりますが、反対に、配偶者が長生きすれば消滅する配偶者居住権の評価額も小さくなり、結果として相続税が課税されない金額も小さくなります。配偶者が短命になるか長生きするかどうかは非常に不確定でありますので、果たして相続税節税のメリットがどれくらい生ずるかは非常に不確定なものといえます。
また、それよりももっと大きなデメリットは、配偶者居住権はそもそも売却(譲渡)することができませんので、例えば、配偶者が、急に介護施設に入居することとなった場合、いったんは配偶者居住権を放棄(あるいは子供との間で合意解除)により消滅させた上で、その後に自宅を売却して介護施設の入居資金に充てるという方法しかありません。その際に、子が配偶者に対して対価を支払わなかったとき(又は著しく低い対価しか支払わなかったとき)には、子に対して配偶者居住権の価額に相当する利益金額の贈与があったものとして、贈与税が課税されてしまうことになる点です(相続税基本通達9-13の2)。反対に、子が配偶者に対して対価を支払うとすると、配偶者には所得税(総合課税の譲渡所得)が課税されることになります(この場合の譲渡所得の計算については、所得税法第60条第3項によります。)。
先々のことは、誰にも分かりませんので、相続税の節税ということで、安易に配偶者居住権による節税策を実行することは、慎重に検討した方がよいかもしれません。
-
12 相続した財産を共有名義とした場合のメリット・デメリットは?
-
相続により土地や建物を共有名義とすることは、一般的に避けた方がよいと言われています。
しかし、相続人間で争いがありやむを得ず当面の共有名義とするケースや、相続する財産が自宅しかなく相続人が子供2人で共有名義とするケースなどで、共有名義とするケースもよくあります。
共有とした場合のデメリットとしては、次の点があげられます。
①売却や賃貸をする際には、売却には全員の同意、賃貸には過半数の同意が必要になりますが、共有者間で意見がまとまらなければ何もできなくなってしまう可能性があります。
②共有者のうちの一人に相続が発生した場合には、共有者の数がさらに増えてしまうことになり共有者間の意見をまとめることが困難になります。しかも共有者の相続人の中に遠方に所在している者がいるとか、あるいは所在不明者がいるとかいった場合には、そもそも話し合うこともできないようなケースもあります。
一方で、共有名義とする方がメリットとなるケースもあります。
例えば、相続人が2人の場合で、相続した財産が自宅しかないケースでは、各相続人の持分を2分の1ずつの共有名義とすることにより、空き家譲渡の特例については、相続人がそれぞれ特別控除(3,000万円)の適用を受けることができることになりますので、家族トータルでは特別控除額3,000万円×2人分=6,000万円の控除額となり、譲渡所得税をかなり圧縮することができます。
また、相続税の納税資金を捻出するために、相続した自宅や土地を相続税の申告期限の翌日から3年以内に売却するケースでは、各相続人が譲渡所得の計算上相続税額の取得費加算の特例を受けることができますので、相続人間の公平(実質手取り額の公平)を図ることができます。
このように、相続した財産を相続後直ちに処分する方針が決まっているようなケースでは、共有名義とすることは非常に有効な節税の手法となります。
このほかに、相続人が2人の場合で、相続財産が賃貸物件一つしかないケースで、相続人全員の意向が賃貸物件を売却するよりも将来にわたって各相続人がそれぞれ法定相続分に応じて賃料を取得したいという希望がある場合には、共有名義とすることも選択肢の一つと考えられます(ただし、残念ながら将来の紛争の可能性は残ります。)。
さらに、相続税の計算において、土地の評価額を算定する際に、地積規模の大きな土地の適用関係が問題となることもあります。
これは、地積規模の大きな宅地の適用が可能な土地(三大都市圏内であれば500㎡以上)について、一定の土地の評価額を減額できる規定になりますが、例えば600㎡の土地を相続人AとBで分筆してそれぞれを単独名義として相続すること(Aは300㎡、Bは300㎡)とした場合には、各相続人が取得した土地の面積により適用を判断しますので、A、Bともに面積規模要件を満たしません。したがって、分筆した場合には、地積規模の大きな宅地の適用を受けることができませんので、土地の評価額の減額はありません。
一方、AB持分2分の1ずつの共有名義とした場合には、上記の500㎡の判定は共有持分割合で按分する前の共有地全体の地積により判定することになりますので、共有土地全体の面積は600㎡ですので、地積規模の大きな宅地の適用を受けることができます。したがって、共有名義とした場合には、土地の評価額を大幅に減らすことが可能となります。
いずれにしても、以上のようなメリット・デメリットを踏まえて、さらに土地の将来の処分・管理に問題が生じないかなどを検討した上で、共有名義とするか否か判断するべきでしょう。
-
13 生命保険は相続税の節税対策として有効でしょうか?
-
生命保険金は、その保険契約に定められた指定受取人が、保険契約から生ずる固有の権利として生命保険金請求権を取得するものとなりますので、受取人固有の財産となります。つまり、民法上は、生命保険金は被相続人の相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象にもなりません。したがって、相続人のうちの特定の相続人に対して、一定の財産(現金)を承継させたいといった場合には、生命保険を活用することにより、遺産分割などの相続手続によらずに、特定の者に生命保険金相当額の財産を確実に承継させることができます。
ただし、相続税法上は、課税の公平の観点から、本来は相続財産ではない生命保険金を相続財産とみなして(「みなし相続財産」といいます。)、相続税を課税することとしております。とはいっても、被相続人の死亡に起因して相続人が受け取る生命保険金については、遺族の生活保障のために支払われるという面もありますので、相続税法上は、一定額の非課税枠(生命保険金の非課税枠=500万円×法定相続人の数)があります。ただし、非課税枠を使える死亡保険金の受取人は、相続人に限られていますので、相続放棄をした者、相続権を失った者、もともと相続人ではない者(孫など)が受取人になっている場合には、その受取人については非課税枠を使うことはできませんので、注意が必要です。
この生命保険金の非課税枠を活用することで、次のようなことが考えられます。
一つ目は、相続税の節税策としての活用(財産の組換え)です。
例えば、現金1,000万円を持っていると、1,000万円がそのまま相続税の課税の対象になりますが、1,000万円を支払って生命保険に加入し、その後に被相続人の死亡に伴い1,000万円の死亡保険金を受け取る場合には、相続税の計算上、生命保険金の非課税枠分(例えば、法定相続人の数が2人で1,000万円)が控除されますので、相続税の課税がされない(生命保険金部分の相続税額は0)ということになります。
二つ目は、相続税の納税資金の確保対策としての活用です。
相続税の納付は、現金での一括納付が原則となっております。しかし、相続財産の大半が不動産であるとか、財産が自宅くらいしかないなどで現金は余りないといった場合には、生命保険契約に加入することにより、受取人となる相続人に多額の現金(納税資金)を用意することができます。
三つ目は、遺留分侵害額請求・代償分割への対策(争族争いの防止)としての活用です。
例えば、相続財産は自宅(あるいは賃貸マンション)しかないといった場合において、被相続人が、相続人の中の特定の相続人に対して、その自宅(あるいは賃貸マンション)を遺言書で相続させるとしたときには、他の相続人の遺留分を侵害することになります。他の相続人から遺留分侵害額の請求があった場合に、遺言で相続した相続人がこの遺留分侵害額の支払資金を手当てできない場合には、その自宅(あるいは賃貸マンション)を売却して平等に配分するしかなくなるといったこともあり得ます。
しかし、死亡保険金の受取人を自宅(あるいは賃貸マンション)を相続させる特定の相続人とすれば、死亡保険金はその特定の相続人の固有の財産となり、遺産分割の対象にもなりませんので、その特定の相続人は、受け取った死亡保険金を遺留分侵害額請求の支払に充てることができます。
このようにすれば、結果的に、特定の相続人は 、自宅(あるいは賃貸マンション)を取得することができて、しかも遺留分侵害額請求に対する支払額の資金手当ても用意できるということになります。
このような活用の仕方は、相続財産が自宅しかない場合において、遺産分割協議の中で自宅を相続する相続人が、他の相続人に対して代償金を支払う資金を生命保険金で用意するというときにも活用することができます。
-
14 孫を生命保険の受取人とした場合に問題は生じませんか?
-
生命保険の非課税枠を利用した相続税対策がありますが、推定相続人に該当しない孫を受取人とする生命保険契約(被保険者及び保険料負担者は祖父とします。)については、次のような問題点が発生しますので、注意が必要です。
①孫が受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、孫は相続人ではないことから死亡保険金の非課税規定の適用はありません。
②孫は相続によって財産(死亡保険金)を取得したことになり、また、孫は被相続人の一親等の血族以外に当たりますので、孫の相続税額については2割加算がされることになりますので、この分税金の負担が大きくなります。
③孫が死亡保険金を取得すると、子は遺贈により財産を取得したことになりますので、相続開始前3年~7年以内に被相続人である祖父から贈与により取得した財産が別にある場合には、この贈与された財産は生前贈与加算の対象になりますので、相続税の負担が増えます。
これらによって孫が相続により取得した財産が相続財産に加算されることになると、孫に相続税がかかるだけではなく、結果的には、他の共同相続人の相続税の負担も重くなってしまいます。 孫を生命保険の受取人とする場合には、これらの不利益があることをよく検討して行うことが必要です。
-
15 生命保険料相当額を子供に贈与する節税策は?
-
生命保険は、被保険者を被相続人とするものであっても、保険契約者と保険料負担者が誰であるかのよって、死亡保険金に対する課税が異なります。この場合、保険契約者以外の者が保険料を負担している場合には、実質の保険料負担者が誰であるかによって判断します。
例えば、保険契約者は子供、被保険者は父、保険料負担者は子供といったケースでは、死亡保険金の受取人は、保険契約者である子供となりますので、死亡保険金に対する課税は、相続税ではなく、所得税(一時所得)となります。
ところで、このような契約関係の生命保険について、子供に保険料の支払能力がないといった場合には、父が毎年子供に保険料相当額の現金を贈与し、子供は贈与された現金で保険料を支払うということがあります。
本来、相続税法では、保険契約に基づく保険料の支払の都度に贈与税を課税するという取扱い(入口課税)ではなく、保険事故発生時を課税時期として、保険金受取人と保険料負担者との関係により、相続税、贈与税、所得税を課税するという取扱い(出口課税)となっています。
しかし、国税庁は、一定の要件の下に、保険料相当額の贈与という考え方を容認し、未成年者又は無収入者を保険料負担者として取り扱うことにしました(昭和58年9月「生命保険料の負担者の判定について」(事務連絡)参照)。
これによると、先のケース (保険契約者は子供、被保険者は父、保険料負担者は子供 )では、保険料の支払者は、子供ということになりますので、子供が受け取った死亡保険金は所得税が課税されることになりますが、①父は毎年の現金贈与で相続財産を減少させることができて、②子供はもらった現金を保険料の支払に充てるので無駄遣いする(もらった現金を消費してしまう)といったこともありませんし、しかも③子供は保険料の支払の負担もなく死亡保険金を受け取ることができて相続税の納税資金を手当てすることができますので、非常にメリット(節税対策と納税資金対策になる)があります。
なお、所得税の一時所得の計算は、(受取保険料ー払込保険料ー50万円(特別控除))×1/2で計算しますので、受取保険料と払込保険料との差額が50万円を超えなけれな、所得税は課税されません。
ただし、保険料の負担者が子供ではなく、父と認定される可能性もあります(その場合は死亡保険金は相続税が課税されます。)ので、保険料の贈与があったことの事実を証明するために、①毎年の贈与契約書、②過去の贈与税申告書、③所得税の確定申告書における生命保険料控除の状況、④その他贈与の事実を証明できるものなどを用意しておく必要があります。
-
16 贈与税の配偶者控除は相続税の節税対策として有効でしょうか?
-
婚姻期間が20年以上あるとき、配偶者への自宅の贈与については、2,000万円プラス基礎控除110万円の合計2,110万円までの範囲内であれば、贈与税が非課税となっています。しかも、改正民法(第903条)では、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈又は贈与については、これを特別受益に該当しないものと推定(持ち戻し免除を行ったと推定)があったものとして取り扱われていますので、配偶者はより多くの財産を相続することができます。
一見すると、この贈与税の配偶者控除の規定を使うと、この分相続財産を減らすことができますので、将来の相続税が節税できるようにみえます。
しかし、例えば、自宅の贈与を受けた妻が、夫よりも先に死亡した場合は、夫は自宅について相続税を支払うことになることがあります。このように、死亡の順序が異なると、予定された節税の効果はありません。 また、贈与税は非課税であっても、贈与による所有権移転登記をするために必要な費用として、登録免許税、司法書士手数料が必要になりますが、この費用が思いのほか多額になることもありうるということを注意する必要があります。登録免許税は、贈与を原因とするときは、固定資産税評価額の1,000分の20かかりますので、例えば、評価額2,000万円の物件であれば、登録免許税として40万円かかります(これに対して、相続を原因とする所有権移転登記をする場合の登録免許税は、固定資産税評価額の1,000分の4ですみます。)。
さらに、相続の場合は小規模宅地等の特例の適用を受けられますが、夫婦間の自宅の贈与の場合は小規模宅地等の特定の適用を受けることができません。
したがって、わざわざ費用をかけて夫婦間の贈与により自宅の所有権を移転しなくても、相続によって所有権を移転すれば、配偶者は相続税の配偶者の税額軽減を使うことができるますし、また、配偶者が相続した土地について小規模宅地等の特例の適用を受けることができますので、これらの特例の適用の結果相続税がかからないケースもありますので、そのようなケースではあえて夫婦間で自宅の贈与をして贈与税の配偶者控除を適用する必要はないかもしれません。
これら点も考慮して、最終的に贈与税の配偶者控除を利用するかどうか検討する必要があります。
-
17 教育資金贈与一括贈与、結婚子育て資金一括贈与、住宅取得資金等贈与は相続税節税策として有効でしょうか?
-
上記の3つの一括贈与は、いずれも相続税の節税対策としては、非常に有効なものといえます。
すなわち、①祖父母から孫へと多額の資金を移転することができるので、一世代飛ばして財産を移転することができます。
②いずれの一括贈与も、一括贈与の非課税とは別に基礎控除(110万円まで非課税)を併せて適用できます。
③いずれも相続税法上の相続開始前3年~7年以内の贈与加算の対象(遺産額に生前贈与額を加算して相続税の計算をする。)になりませんので、後々相続税の課税がされるというリスクがありません(ただし、以下の例外あり)。
ただし、注意しなければならないのは、一つ目として、贈与者(例えば、贈与をした祖父母)が贈与直後に死亡した場合、住宅資金贈与を除いて、他の2つの一括贈与(教育資金贈与一括贈与及び結婚子育て資金一括贈与)では、使い残し(管理残額)があれば相続税の課税対象になるという点です(一方、住宅資金贈与については、贈与直後に死亡しても使い残しについては相続税が課税されないことになっています。)。
※教育資金贈与一括贈与については、ここ数年かなり改正がされており、次のとおり課税が強化されていますので、注意が必要であります。
つまり、平成31年4月1日以後に取得する教育資金贈与一括贈与に関しては、管理残額が相続財産に加算される取扱いとなったということです。
①平成31年3月31日までの拠出
・・・贈与者が死亡しても使い残しに対しては相続税は課税されません。
②平成31年4月1日から令和3年3月31日までの拠出
・・・贈与者が死亡した場合、相続開始前3年以内の贈与分について使い残しがあれば相続税が課税されます
(例外有、死亡時に受贈者が23歳未満のとき、学校に在学中のとき、教育訓練を受けているときなど)。
受贈者が孫であっても相続税額の2割加算の適用はありません。
③令和3年4月1日以降の拠出
・・・贈与者が死亡した場合、使い残しがあれば相続税が課税されます(例外有、②と同様)。
さらに、受贈者が孫等であれば相続税額に2割加算があります。
※結婚子育て資金の一括贈与については、次のとおり改正されています。
①平成31年3月31日までの拠出
・・・贈与者が死亡した場合、使い残しがあれば相続税が課税されます。
②平成31年4月1日以降の拠出
・・・贈与者が死亡した場合、使い残しがあれば相続税が課税されます。
さらに、受贈者が孫等であれな相続税額に2割加算がされます。
また、二つ目として、教育資金の一括贈与では、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る資金管理契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について贈与税が課税されるということです。同じく、結婚・子育て資金の一括贈与では、受贈者が50歳に達するなどにより結婚・子育て資金口座に係る資金管理契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て支出金を控除した残額について贈与税が課税されるということです。
このように、改正により、使い残しがあると相続税や贈与税が課税されるリスクがありますので、祖父母の方々が孫に贈与する場合には、ご自身の老後の生活費も考慮しながら、使い残しが生じないようにすることも考慮して、使い切れるだけの額を贈与することが必要になります。
-
18 法改正が予定されているので亡くなる直前の駆け込み贈与をしてはダメでしょうか?
-
暦年贈与(1年間に110万円までは贈与税は非課税)は、相続対策として非常に有効であると考えられています。
しかし、相続財産を取得した相続人が子である場合には、相続開始前3年以内(改正により令和6年1月1日からは段階的に7年前まで延長)の贈与については相続財産に持戻し(加算)されますので、この3~7年以内の贈与に係る分については相続対策にはなりません。
しかし、この持戻しの対象となる相続開始前3~7年以内贈与は、相続時に財産を取得する相続人及び遺贈を受ける受遺者が対象となりますので、これ以外の者(例えば、孫、子の配偶者(嫁))に対する贈与は、この加算の対象にならないことになります。
このように、相続税対策として暦年贈与を活用する場合は、子だけでなく、この配偶者や孫なども対象とすることで、110万円の非課税枠をたくさん使うことができます。トータルで見ると大きな節税になりますし、孫などに贈与することで相続税の課税を一世代飛ばすことができて、しかも孫は法定相続人には該当しないので3~7年以内贈与の加算の対象にもならないなど、相続税の節税対策としては非常に有効な手段となります。
したがって、令和6年1月1日以降についても、相続税計算上加算対象となる生前贈与の期間が3年から7年に延長されますが、暦年贈与は使い方によっては非常に有効な相続税節税対策だといえます。
また、加算期間が延長されるといっても、いつ死亡するかは誰にも分かりませんので、できるだけ早い段階(若い年齢)から子への暦年贈与をすれば、加算対象となる贈与を少しでも減らすことができます。長生きすれば、その分加算対象外となる生前贈与が増えるものと割り切って毎年実行していく気持ちが大切です。
-
19 相続税対策として家族信託は有効でしょうか?
-
認知症になったときの対策として、家族信託が有効だと言われている。
そもそも生前の相続対策としての遺言書の作成や認知症に備えての任意後見契約がありますが、それよりも家族信託を活用する方がよいのでしょうか?
まず、家族信託とは、委託者が信託契約によって信頼できる人(受託者)に対して財産を移転し、受託者は信託契約に定めた目的に従って受益者のためにその信託財産の管理・処分をする制度になります。信託財産が不動産の場合は、財産を移転することから、登録免許税(所有権移転登記は非課税ですが、信託登記は固定資産税評価額の1000分の4かかります。)や登記手続費用(司法書士の報酬)がかかります。遺言も任意後見契約も一定の費用がかかるという点では同じですが、信託の方が費用は多くかかるかもしれません。
次に、認知症になってしまった場合は、遺言があるだけでは、家族は全く財産を自由に管理・処分できません。
一方、任意後見契約では、基本的に財産の管理・維持に重点をおきますので、処分をするには任意後見監督人や家庭裁判所の許可が必要になりますので、基本的に所有する財産を処分することはできません。
これに対して、信託では、信託契約の内容に基づき受託者の判断で、財産の管理・運用・処分ができますので、最も自由度が高く柔軟な対応ができるといってもよいでしょう。
信託財産の課税については、委託者=受益者の自益信託のケースであれば(通常は課税の問題が生じないようにするため、委託者父、受託者長男、受益者父とします。)、信託財産は受益者が有する財産と考えますので、①信託設定時には所得税や贈与税が課税されることはなく、②信託期間中は信託財産から生じる収益は受益者に帰属することになり、③受益者死亡の時には新受託者に相続税が課税(信託受益権の評価は信託財産の評価額と同じ)されることになります。この点は、通常の相続と大きな違いはないでしょう。
ただし、信託で最も気をつけなければならないのは、大規模修繕を近々予定しており赤字が見込まれるケースでは、不動産所得の計算において、1の信託契約に係る不動産所得に生じた損失は生じなかったものとされること、つまり、信託以外の不動産所得との内部通算や他の所得と損益通算できないということです。この点が、信託の方法によった場合の最大のデメリットといえます。このほか、受託者は、年1回一定の時期に財産樹生興開示資料を作成して受益者に報告しなければならないという手間がかかります。
でも信託では、遺言では実現できないことが実現可能なこともあります。
例えば、後継ぎ遺贈型の受益者連続信託といって、
①妻との間に子供がいない夫が、夫の死後は妻を受益者とし、妻の死後は妻の兄弟に相続させるのではなく、自分の兄弟に承継させたいと望むケース、
②夫は再婚したが、妻との間に子供がいないけれども前妻との間には子供がいるケースで、妻に一旦相続させた後、妻死亡後は前妻との間の子に相続させたいと望むケース、
③特定贈与信託といって、障害を持つ子を有するケースで、親亡き後の生活費や療養費の支払のために障害を持つ子を受益者として信託銀行に金銭を預けて、信託銀行がその財産を管理するケース(このパターンは委託者≠受益者のため本来は贈与税が課税されるところ、上限3,000万円(特別障害者は6,000万円)までが非課税となっています。)
などでは、信託を活用すれば、上記の要望を実現できますが、遺言ではこれを実現することができません。
①や②のケースで、妻にも遺言書を作成させて自分の兄弟や前妻との間の子に遺贈させる方法もありますが、妻が新たな遺言を作成することを防ぐことはできません。
このように、信託には、信託でなければできないこともある反面、不動産所得で損益通算できないとか税務署への報告の手間がかかるなどのデメリットもあります。
結局は、遺言書作成、任意後見契約の締結、信託契約などの中から、その人のニーズに合った最もベストな組合せを検討することが望ましいということかもしれません。いずれにしてもお金がかかる話なので、安易に家族信託を行わないで、慎重に検討したいものです。
-
20 生前贈与について改正がされますがどのような内容でしょうか?
-
相続税と贈与税の一体化の議論の中で、毎年110万円の贈与税の非課税枠(暦年贈与)を活用した節税策に対する対応として、暦年贈与を廃止又は改正すべきであるとの意見がありました。背景には、相続時精算課税の適用者が年々減少し、この制度を活用して親の世代から子供への資産の移転が進んでいないことや、暦年贈与制度は富裕層が相続税の節税対策で活用しているという現実があるようです。
令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降に行われる贈与について適用されます。
暦年贈与については、生前贈与加算の対象期間を、現行の相続開始前3年以内から7年以内に延長されました。
ただし、延長された4年間から7年までの間の贈与については、事務処理の手間を考慮して、延長期間での贈与は総額100万円までは相続財産に加算されません。
ただし、加算対象となる者については見直しがなく、孫やこの配偶者への暦年贈与は従来と同様に生前贈与加算の対象外となっています(この点は、暦年贈与の改正がされて加算期間が延長されたからといっても影響がないことから、従来通り有効に活用したいものです。)。
一方、相続時精算課税については、一層の利用促進を図かるため、2,500万円の特別控除とは別枠で、毎年110万円までの基礎控除(非課税枠)が新たに設けられました。
これにより、一見すると暦年贈与よりも相続時精算課税の方が非常にお得(節税対策になる)に見えるかもしれません。
しかし、以下の点に注意して、相続税精算課税を選択するかどうかを決定した方がよいと考えます。
①もともと基礎控除の範囲内の遺産しかなく、相続税がかからない家庭では、改正に関係なく、相続時精算課税を選択して早期に多額の財産を移転することで問題ないでしょう。ただし、相続税がかからない家庭において、老後の生活費のことを考えると、果たして多額の財産を生前贈与できるかどうかは問題が残ります。
②財産が多い家庭において、相続時精算課税の毎年110万円の範囲内の贈与を行えば、結果的に暦年贈与で行うよりも3~7年以内の加算の問題もないので、お得だといえるかもしれません。しかし、多額の財産を所有する家庭で、相続時精算課税を使ってこれから節税対策をしますと税務署に宣言することになりますので、税務調査のリスクが高まるかもしれません。
③いったん相続時精算課税を選択すると、暦年贈与には二度と戻れませんので、将来の改正の可能性(?)も踏まえると、果たしてお得になるかどうかはよく分かりません(教育資金一括贈与の例など一旦できた制度もその後の問題点を踏まえて納税者に不利な方向で改正されることがよくかるからです。)。