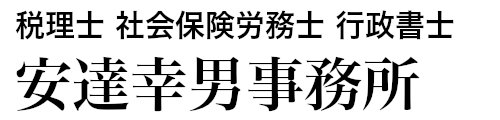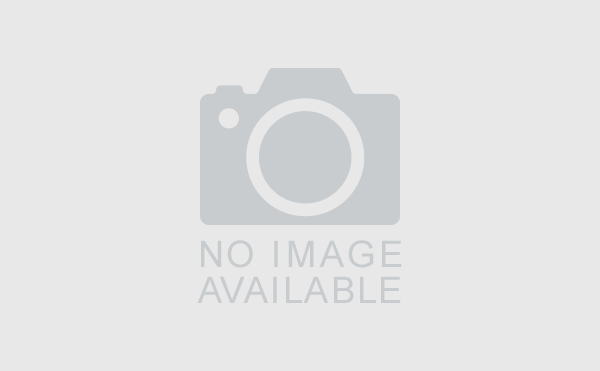基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言7)
遺言にはどのようなものがありますか?
一般的な遺言には、①自筆証書遺言(民法第968条)、②法務局保管の自筆証書遺言(法務局における遺言書保管等に関する法律)、③公正証書遺言(民法第969条)、④秘密証書遺言(民法第970条)の4つがあります。
このほかに、特別方式による遺言として、死亡危急時遺言(民法第976条)、伝染病隔離時遺言(民法第977条)、在船時遺言(民法第978条)、難船時遺言(民法第979条)がありますが、ほとんど利用はありません。
① 自筆証書遺言
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押したものになります。
なお、財産目録については、2019年1月13日以降、自筆でなくてもよくなりました(ワープロでの作成のほか、登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付することでも可となりました。)。
自筆証書遺言は、手軽に作成できて、費用もかからず、内容は秘密にできますが、方式・内容に誤りがあると無効になるリスクがあります。また、遺言書の偽造・変造・改ざん・破棄・紛失・未発見といったリスクもあります。
さらに、遺言の執行に当たっては、家庭裁判所の検認手続が必要になり、相続手続に時間がかかります。
このように様々なデメリットがありますので、やめた方が良いでしょう。
② 法務局保管の自筆証書遺言
法務局で自筆証書遺言を保管する制度が2020年7月10日から始まりました。
費用は安く(保管申請に係る手数料は3,900円)、しかも遺言者の死亡日から50年間保管されます。法務局が保管するので、偽造・変造・改ざん・破棄・紛失のリスクがなく、さらに家庭裁判所の検認手続が不要です。
非常にメリットが多いのですが、唯一のデメリットは、遺言書の内容の有効性を担保するものではないということです。法務局では、形式面の審査はしますが、内容面の審査はしませんので、後日内容の有効性を巡って争いとなるリスクはあります。できれば、内容面の有効性を担保するために、事前に専門家にチェックしてもらった方が良いかもしれません。
③ 公正証書遺言
公証役場において、又は公証人に出張を求めて、公証人に作成してもらう遺言になります。費用は、公証人の費用のほか、証人の日当、専門家のサポート料などによって異なりますが、5万円~20万円程度かかります。
公正証書遺言は、裁判官や検事をやめた法律のプロが作成しますので、遺言書が内容面で無効になることはほとんどありません。遺言者本人の遺言能力の有無の点についても、公証人が面前で本人に確認しますので、後日争いとなっても遺言能力がなかったとして無効になることもほとんどありません。また、公証役場で保管されるため、遺言書の偽造・変造・改ざん・紛失のリスクはなく、さらに家庭裁判所の検認も不要です。
④ 秘密証書遺言
公証人や証人の前に封印した遺言書を提出して、遺言の存在は明らかにしながら、内容を秘密にして遺言書を保管することができる方式のものをいいます。実務上、ほとんど利用されていません。