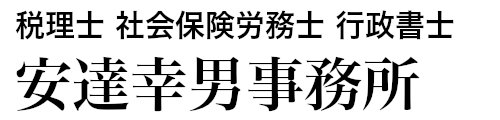基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言31)
遺留分侵害額請求があったときはどうするのですか? 遺留分侵害額請求があった場合には、遺言によって財産を取得した相続人などは、遺留分に相当する金銭を支払う必要があります。 もちろん相手方が了解すれば、分割で支払うことも […]
基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言30)
遺留分侵害額請求の仕方は? 遺留分侵害額請求権の行使は、相手方に対する意思表示によってすることになっています。これは、裁判上で行使する必要はなく、必ずしも書面によって行使する必要もなく、口頭での行使も可能です。ただし、 […]
基礎から学ぶ遺言相続講座(相続40)
資産凍結を防ぐ方法は? 認知症などに罹っており、判断能力が低下している段階において、ご家族が資産凍結を予め防ぐ方法としては、次のような方法があります。 1 預金については、家族があらかじめ「代理人カード」を作成しておく […]
基礎から学ぶ遺言相続講座(遺言29)
遺言の有効性を争うときはどうすればよいか? 遺言の有効性(遺言が無効であること)を争う場合には、遺言の有効性を争う者が、地方裁判所に対して、遺言書無効確認の訴えを提起する必要があります。 遺言書が無効であると主張する […]
基礎から学ぶ遺言相続(遺言28)
認知症の者であっても遺言を作成することができますか? 認知症といっても、本人の判断能力のレベルは様々であり、まだら認知症といって、その日の天気や時間帯によっても判断能力に差が生じることがあります。 したがって、認知症 […]
基礎から学ぶ遺言相続(遺言27)
遺言能力とは? 遺言を書くには、判断能力が必要であると言われています。ただし、法律上は、満15歳に達した者であれば、誰でも遺言書を作成することができます(民法第961条)。 したがって、通常は単独では契約などの法律行 […]
基礎から学ぶ遺言相続講座(相続39)
資産の凍結は、なぜ起こるのか? 資産凍結とは、本人の判断能力の低下や喪失、あるいは、死亡・共有といった事実によって、本人又は家族が自由に財産を処分できなくなることをいいます。 資産凍結は、具体的には、次のようなケース […]
基礎から学ぶ遺言相続講座(相続38)
おひとり様の老後対策とは、何でしょうか? おひとり様の老後対策・終活対策としては、次のようなことが考えられます。 1 老後破産しないための生活費の確保 老齢国民年金は、月額約7万円しかありません。老齢厚生年金でも、月 […]
基礎から学ぶ遺言相続講座(相続37)
おひとり様の老後・相続対策は何をすればよいか? 前回(相続36)の話を踏まえて考えますと、おひとり様の老後・相続対策としては、次のようなことを検討していく必要があります。まず、今回は、相続対策について考えてみます。 1 […]
基礎から学ぶ遺言相続(相続36)
おひとり様の相続は、何が問題になるでしょうか? おひとり様にとっては、余り考えたこともない(あるいは考えたくない)ことでしょうが、おひとり様の老後・死後に起こる問題については、いろいろとあります。 一般的には、次のよ […]