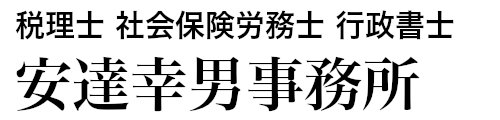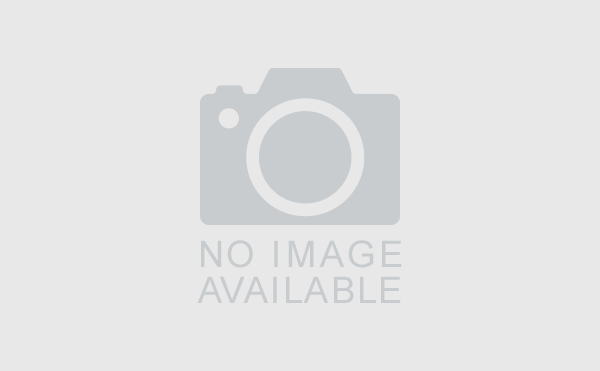基礎から学ぶ遺言相続講座(相続17)
名義預金とは?
名義預金とは、預貯金について、預金名義人と真実の所有者とが違うケースにおいて、真実の所有者に帰属する預金のことをいいます。
このような名義預金の帰属に関しての判断基準については、①預貯金の預け入れの原資の出捐者は誰であるか、②預貯金の管理及び運用は誰が行っていたか、③預貯金から生じる利益は誰に帰属するか、④被相続人と名義人との関係はどのようなものか、⑤名義人名義で預貯金がされた経緯はどのようなものか、といった事項を総合的に勘案して判断することになります。
実務では、被相続人が子や孫名義で定期預金を作成していたケースや、被相続人の妻(専業主婦又はパート)が夫の収入から生活費のやりくりをして余ったお金を妻名義の預金として貯めていたケースなどで、その預金の帰属が被相続人のものと判断されるか否かがよく問題になります(名義預金と認定されれば、被相続人の相続財産として相続税の課税対象に加算されることになってしまいます。)。
上記の前者のケースでは、預貯金の預入の原資は被相続人のお金であり、また、一般的には被相続人が預金通帳や印鑑を支配管理しているケースが多いでしょうから、被相続人の預金と認定されることが多いかと思います。仮に、被相続人から子や孫に対して預貯金が贈与されたとの主張をしても、子や孫が預金通帳や印鑑の交付を受けていないケースでは、贈与があった旨の主張は認められないでしょう。
後者のケースでは、預貯金の預入の原資は被相続人のお金でありますので、たとえ妻が預金通帳と印鑑を管理していたとしても、一般的には、妻は夫から委任を受けて管理・使用しているとみるべきですから、夫の預金と認定されるケースが多いでしょう。このケースでも、妻が夫から贈与を受けたものであるとの主張がされることがありますが、通常は贈与の履行があったとみるべき証拠が何も存在しませんので、認められないことが多いでしょう。
相続税対策として子や孫名義の預貯金を作成するケースでは、税務署による相続税調査において名義預金との認定を受けないためには、預金通帳及び印鑑は子や孫に渡して管理させること、子や孫に自由にお金を使わせること、贈与契約書を作成すること、税務署に対して贈与税の申告書を提出しておくこと、がベストな対策となります。