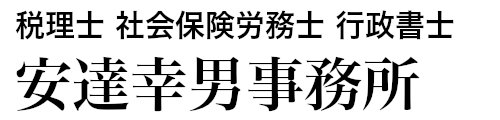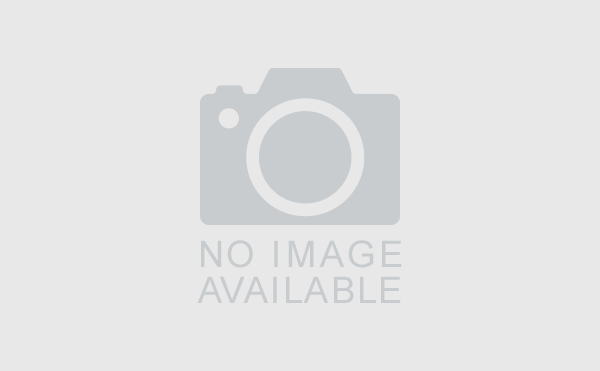基礎から学ぶ遺言相続(相続25)
相続における遺産分けのルールはどうなっていますか?
遺言書がある場合の手続と遺言書がない場合の手続とは、全く異なります。
1 遺言書がある場合
① まず、遺言書があれば、遺言書の内容に従って遺産分けを行います。
つまり、遺言書>遺産分割協議 という関係にあります。
この場合の遺言書は、自筆証書遺言でも、公正証書遺言でも、効力に違い(優劣)はありません。
遺言書は、日付が後の者が優先します。また、前の遺言と後の遺言とが抵触するときは、抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を取り消したものとして扱われます。
② 遺言書があって、遺言書の内容によると「全財産を長男に相続させる。」となっていた場合でも、他の相続人には、最低保障としての遺留分があります(例えば、相続人が、配偶者と子の時は、全体の2分の1が遺留分になります。その上で、各相続人の遺留分は、遺留分×法定相続分となりますので、結果的には、配偶者の遺留分は4分の1、子の遺留分は4分の1となります。)。
なお、遺留分を無視した遺言書であっても、有効として取り扱われます。その上で、遺留分を侵害された相続人は、受贈者に対して、遺留分侵害額請求(お金で支払えという請求)をすることができることになっています。この場合、遺留分侵害額請求をするかどうかは、各相続人の自由です。
③ 遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、これと異なる内容の遺産分割協議書を作成することもできます。
④ 遺言書がある場合は、遺言書によって、預金の解約払戻や不動産の相続登記を行うことになります。
2 遺言書がない場合
① 相続人全員の遺産分割協議の合意によって財産分けを決定することができます。遺産分割をする期限は、特にありませんが、民法の改正(令和5年4月1日から施行)により、相続開始から10年以内に遺産分割協議が成立しないと、もはや特別受益や寄与分の主張をすることができないというデメリットがありますので注意が必要です。
この場合、法定相続分と異なる遺産分割の内容であっても、相続人全員の同意があるならば全く構いません。
また、寄与分、特別寄与分、特別受益についても、相続人間の合意によってその取扱いを決めることができます。
② どうしても遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して、遺産分割の調停・審判の申立てを行うことになります。
③ 預金の解約払戻や不動産の相続手続等の相続手続については、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)によって行います。